
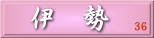
難波潟みじかき芦のふしの間も
あはでこの世を
過ぐしてよとや |

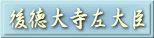
ほととぎす鳴きつる方を眺むれば
ただ有明の
月ぞのこれる |

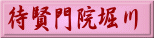
ながからむ心も知らず黒髪の
乱れて今朝は
ものをこそ思へ |

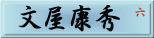
吹くからに秋の草木のしをるれば
むべ山風を
あらしといふらむ |

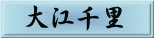
月見ればちぢにものこそ悲しけれ
わが身ひとつの
秋にはあらねど |

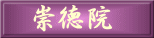
瀬をはやみ岩にせかるる滝川の
われても末に
逢はむとぞ思ふ |

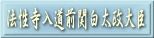
わたの原漕ぎ出でて見れば久かたの
雲ゐにまがふ
沖つ白波 |

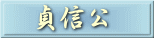
小倉山峰のもみぢ葉心あらば
今ひとたびの
みゆき待たなむ |

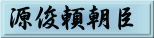
うかりける人を初瀬の山おろしよ
はげしかれとは
祈らぬものを |

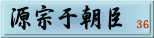
山里は冬ぞさびしさ
まさりける
人めも草も
かれぬと思へば |

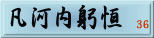
心あてに折らばや折らむ初霜の
おきまどはせる
白菊の花
|

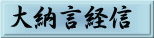
夕されば門田の稲葉おとづれて
芦のまろやに
秋風ぞ吹く
|


寂しさに宿を立ち出でてながむれば
いづこもおなじ
秋の夕暮 |

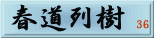
山川に風のかけたるしがらみは
流れもあへぬも
みぢなりけり
|

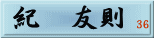
久かたの光のどけき春の日に
しづ心なく
花の散るらむ |

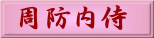
春の夜の夢ばかりなる手枕に
かひなく立たむ
名こそ惜しけれ |

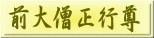
もろともにあはれと思へ山桜
花よりほかに
知る人もなし |


夏の夜はまだよひながら明けぬるを
雲のいづこに
月やどるらむ |

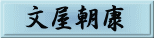
白露に風の吹きしく
秋の野は
つらぬきとめぬ
玉ぞ散りける |

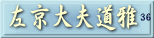
今はただ思ひ絶えなむとばかりを
人づてならで
言ふよしもがな |


夜をこめて鳥のそら音ははかるとも
世に逢坂の
関はゆるさじ |

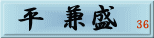
しのぶれど色に出でにけりわが恋は
ものや思ふと
人の問ふまで |

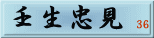
恋すてふわが名はまだき立ちにけり
人知れずこそ
思ひそめしか |


やすらはで寝なましものを小夜更けて
傾くまでの
月を見しかな |
 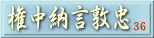
逢ひ見ての後の心にくらぶれば
昔はものを
思はざりけり |

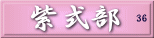
巡りあひて見しやそれともわかぬ間に雲がくれにし
夜半の月かな |

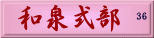
あらざらむこの世のほかの思ひ出に
今ひとたびの
逢ふこともがな |
 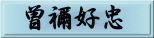
由良のとをわたる舟人かぢをたえ
行く方も知らぬ
恋の道かな
|


八重むぐらしげれる宿のさびしきに
人こそ見えね
秋はきにけり |

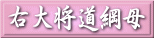
歎きつつひとりぬる夜の明くる間は
いかに久しき
ものとかは知る |

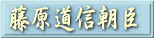
明けぬれば暮るるものとは知りながら
なほ恨めしき
あさぼらけかな
|

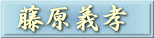
君がため惜しからざりし命さへ
ながくもがなと
思ひけるかな |


かくとだにえやは伊吹のさしも草
さしも知らじな
燃ゆる思ひを |

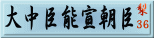
御垣守衛士のたく火の夜はもえ
昼は消えつつ
ものをこそ思へ |

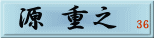
風をいたみ岩うつ波のおのれのみ
砕けてものを
思ふころかな |


忘れじの行末までは難ければ
今日をかぎりの
命ともがな |

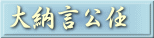
滝の音は絶えて久しくなりぬれど
名こそ流れて
なほ聞こえけれ |

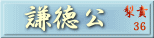
あはれともいふべき人は思ほえで
身のいたづらに
なりぬべきかな |

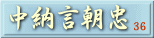
逢ふことの絶えてしなくはなかなかに
人をも身をも
恨みざらまし |

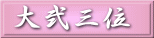
有馬山猪名のささ原風吹けば
いでそよ人を
忘れやはする |

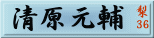
契りきなかたみに袖をしぼりつつ
末の松山
波こさじとは |


大江山いく野の道の遠ければ
まだふみも見ず
天の橋立
|

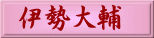
いにしへの奈良の都の八重桜
今日九重に
匂ひぬるかな
|

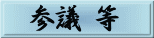
浅茅生のをののしの原しのぶれど
あまりてなどか
人の恋しき |


忘らるる身をば思はず誓ひてし
人の命の
惜しくもあるかな
|

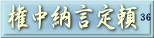
朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに
あらはれわたる
瀬々の網代木 |

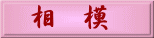
恨みわびほさぬ袖だにあるものを
恋に朽ちなむ
名こそ惜しけれ
|

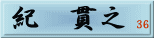
人はいさ心も知らずふるさとは
花ぞむかしの
香ににほひける |
 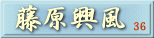
誰をかも知る人にせむ高砂の
松もむかしの
友ならなくに |

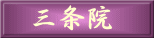
心にもあらでうき世にながらへば
恋しかるべき
夜半の月かな |


あらし吹く三室の山のもみぢ葉は
龍田の川の
にしきなりけり
|

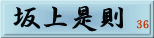
朝ぼらけ有明の月と見るまでに
吉野の里に
ふれる白雪
|

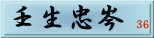
有明のつれなく見えし別れより
暁ばかり
うきものはなし
|

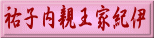
音にきく高師の浜のあだ波は
かけじや袖の
濡れもこそすれ |

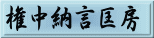
高砂の尾の上の桜
咲きにけり
外山の霞
たたずもあらなむ |

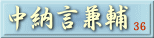
みかの原わきて流るる泉川
いつみきとてか
恋しかるらむ |

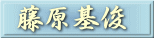
契りおきしさせもが露を命にて
あはれ今年の
秋も去ぬめり |

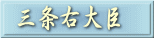
名にしおはば逢坂山のさねかづら
人に知られで
くるよしもがな |

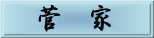
このたびは幣も取りあへず手向山
紅葉のにしき
神のまにまに |

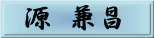
淡路島通ふ千鳥の鳴く声に
幾夜ねざめぬ
須磨の関守 |

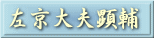
秋風にたなびく雲の絶え間より
もれ出づる月の
影のさやけさ |

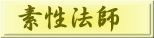
今来むといひしばかりに長月の
有明の月を
待ち出でつるかな |

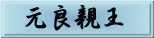
わびぬれば今はた同じ難波なる
身をつくしても
逢はむとぞ思ふ |

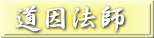
思ひわびさても命はあるものを
憂きに堪へぬは
涙なりけり |

