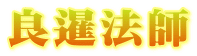
(りょうぜんほうし)
<998年~1064年頃>
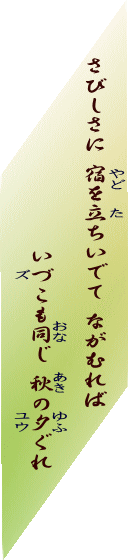



「後拾遺集」にある「題不知(だいしらず)」の歌です。良暹法師は比叡山・祇園別当を経て、大原に庵をかまえて隠棲していた時期があります。「詞花集」には大原に住み始めた頃の歌が何首かあるので、この歌もその頃詠まれたものかもしれません。修行の場とはいえ、僧侶が数千人もいた比叡山から、話を交わす友はおろか、誰も見かけない山里での一人暮らし。僧侶といえども寂しさはつのるばかりです。思わず庵から外へ出てみても、同じように寂しい風景が広がっているだけです。「いづくも同じ」という表現に、自分の内面の寂しさを見つめる作者の姿が浮かんできます。寂しさは必ずしも苦痛や悲しみではなく、あえてそこに身をおくことで受け入れ、味わおうとする心で詠まれています。結句を「秋の夕暮」と体言止めにする手法も、しみじみとした趣を引き出しています。「新古今集」では、こうした枯れゆくような寂寥感(せきりょうかん)を美しいとする感覚が大切にされました。

平安時代の「寂しさ」は、秋や冬の寂寞とした感じを表します。特に一人住まいや無人の荒れ果てた家や野山など、あまり人がいない場所の寂しさを示しています。格助詞「に」は原因や理由を表し、全体で「さびしさのせいで」という意味になります。
【宿を立ち出でて】
この場合の「宿」は自分が住んでいる庵のことです。「庵を出て」という意味になります。
【眺むれば】
下二段動詞「眺む」は、単に眺めているだけではなく、「いろいろな思いにふけりながらじっと長い間見ている」というニュアンスがあります。「眺む」の已然形に接続助詞「ば」がつき、順接の確定条件を表します。
【いづこも同じ秋の夕暮れ】
「どこも同じように寂しい秋の夕暮れがひろがっていた」という意味です。「同じ」は形容詞の連体形の特殊な形です。最後の体言止めの「秋の夕暮れ」は、定家の編纂した「新古今集」の時代に流行した結句(むすびのことば)でした。


●「後拾遺集」には藤原国房が良暹法師に贈った歌があります。詞書に「良暹法師のもとにつかはしける」として「思ひやる 心さへこそ 寂しけれ 大原山の秋の夕暮」(大原山の秋の夕暮は、はるかに思いやる私の心さえさびしくなります。)とあります。
●「枕草子」初段の「秋は夕暮」の流行によるものかもしれませんが、良暹法師の歌は、秋の夕暮れの寂しさを定着させる役割を果たしました。この後、「秋の夕暮れ」は「新古今集」で盛んに詠まれるようになっていきます。王朝の華麗な美の世界から、「わび・さび」へと美意識が変化していくきざしを感じさせます。

