
(おののこまち)
<生没年未詳、820年~870年頃>
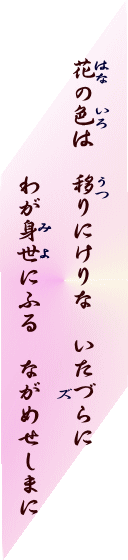

![]()
桜の花の色は、はかなくあせてしまったなあ、春の長雨が降っている間に。同じように私の容姿も衰えてしまった,むなしくもの思いにふけっている間に。
「咲き誇った桜の花も、むなしく色あせてしまったわ。降り続く長雨にぼんやり時を過ごしているうちに。かつては絶世の美女と謳われた私の若さも容色も衰えてしまったものね。恋の物思いをして過ごしている間に。」と、下の句に掛詞や縁語などの技巧を凝らして、色あせた桜に老いた自分の姿を重ねあわせた歌です。声に出して読むと柔らかい響きがします。「な」の音が3つ、「に」の音が4つ使われ、ナ行、マ行の音が凝縮されているからです。定家は、この歌を古今第一の歌として、「余情妖艶(よじょうようえん)の体(てい)」と高く評価しています。余情とは表現の奥に感じられる情緒、妖艶とはあいまいで深みのある美のことです。歌の奥深くになんとも言いがたい情感があるということでしょうか。

「花」とだけ書かれている場合、古典では「桜」を意味します。日本では古来桜が愛され、春を表す花の代表とされてきました。和歌で「花」が桜を指すようになるのは平安時代以降です。「桜の花の色」という意味ですが、ここでは「女性の若さ・美しさ」も暗示しています。「花の色」は、漢語の「花色」からきたものらしく、漢詩では「花のような顔色」「女性の容顔」について使われることが多いようです。
【うつりにけりな】
動詞「うつる」は花の色のことなので、「色あせる・衰える」というような意味です。「な」は感動の助動詞で、「色あせ衰えてしまったなあ」という意味になります。
【いたづらに】
「むだに」や「むなしく」という意味で形容動詞「いたづらなり」の連用形です。
【世にふる】
ここでの「世」は「世代」という意味と「男女の仲」という2重 の意味が掛けてある掛詞です。さらに「ふる」も「降る(雨が降る)」と「経る(経過する)」が掛けてあり、「ずっと降り続く雨」と「年をとっていく私」の2重の意味が含まれています。
【ながめせしまに】
「眺め」は「物思い」という意味と「長雨」の掛詞で、「物思いにふけっている間に」と「長雨を眺めている間に」という2重の意味があります。さらに「ながめせしまに→我が身世にふる」と上に続く倒置法になっています。


●「古今集」の撰者だった紀貫之は、その「仮名序(かなで書かれた序文)」で、小野小町の歌について「あはれなるやうにて、つよからず。いはばよき女の悩める所あるに似たり」(しみじみと身にしみるところはありますが、弱々しいです。いうなれば病に悩んだ高貴の女性に似ています。)と述べていますが、小町の代表歌として挙げた3首に「花の色は」の歌は入っていません。さまざまな小町説話(美人の悲惨な末路)の影響を受けて、悩める美女の嘆きの歌として、97番・藤原定家の頃から再評価されたようです。

