
陰暦 6月 8日
(7月24日) |
 |
|
|
八日、月山にのぼる。木綿しめ身に引きかけ、宝冠に頭を包み、強力といふものにみちびかれて、雲霧山気の中に氷雪を踏んてのぼる事八里、更に日月行道の雲関に入るかとあやしまれ、息絶え身こごえて、頂上に至れば、日没して月あらわる。笹をしき、篠を枕として、臥して明くるを待つ。日出でて雲消ゆれば、湯殿に下る。
谷の傍に鍛冶小屋といふあり。この国の鍛冶、霊水を選びて、ここに潔斎して剣をうち、終に月山と銘を切つて世に賞せらる。かの竜泉に剣を淬ぐとかや。干将・莫耶のむかしをしたふ。道に堪能の執あさからぬ事しられたり。岩に腰かけてしばしやすらふほど、三尺ばかりなる桜のつぼみ半ばひらけるあり。ふり積む雪の下に埋もれて、春を忘れぬ遅ざくらの花の心わりなし。炎天の梅花ここにかをるがごとし。行尊僧正の歌のあはれもここに思ひ出でて、なほまさりて覚ゆ。惣じて、この山中の微細、行者の法式として他言する事を禁ず。よつて筆をとどめて記さず。坊に帰れば、阿闍梨のもとめによつて、三山順礼の句々短冊に書く。
涼しさやほの三日月の羽黒山
雲の峰幾つ崩れて月の山
語られぬ湯殿にぬらす袂かな
湯殿山銭ふむ道の涙かな 曾良 |

 |

すずしさや ほのみかづきの はぐろさん
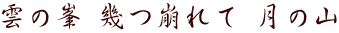
くものみね いくつはなれて つきのやま
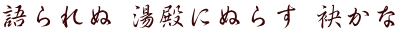
かたられぬ ゆどのにぬらす たもとかな
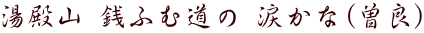
ゆどのさん ぜにふむみちの なみだかな (そら)
|
|
|
 |
|
八日、月山に登る。木綿しめを身に引っかけ、宝冠で頭を包み、強力という者に案内されて、雲や霧の立ち込める山の空気の中で、氷や雪を踏み締めて登ること、なんと八里、さらに日や月の通り道である雲の関所に入るのかと疑われてしまうくらいで、息が絶え身が凍りつきそうになって、やっとのことで頂上に到着すると、日が沈んで月が現れる。笹を敷いて、篠を枕として、横になって夜が明けるのを待つ。日が出て雲が消えるので湯殿に下る。
谷の側に鍛冶小屋というものがある。この国の鍛冶が、霊水を選んでここで身を清めて剣を打ち、とうとう月山と銘を刻んで世の中に評判となった。あの竜泉で剣を鍛えるとかいうことだ。中国の刀鍛冶の干将とその妻の莫耶が協力して名刀を作った故事を慕うものである。道に優れた者の執念が浅くないことが知られるのである。岩に腰をかけてしばらく休むうちに、三尺ほどの桜の蕾が半分開いているのがある。降り積もった雪の下に埋もれているのに、春を忘れない遅桜の花の心は素晴らしい。炎天下の梅花がここで薫っているようだ。行尊僧正の詠んだ歌の趣もここに思い出されて、さらにこの桜がより素晴らしく思われる。たいていは、この山中の細かいことは、修行者の決まりとして他言することを禁じている。そこで、これ以上は筆を置いて書かない。宿坊に帰ると、阿闍梨の願いによって、三山巡礼のときの句々を短冊に書いた。
涼しさやほの三日月の羽黒山
<涼しいことだなあ。かすかに浮かぶ三日月の光の下にある羽黒山よ。>
雲の峯幾つ崩れて月の山
<雲の峰がいくつ崩れてから、月に照らされた月の山になるのだろうか。>
語られぬ湯殿にぬらす袂かな
<語ることはできない湯殿の素晴らしさに、ついつい涙で袂が濡れてしまう。>
湯殿山銭ふむ道の涙かな 曾良
<湯殿山には賽銭がばらまかれているが、それを踏んでいると、ありがたさに涙が出てくることよ。曾良作。>
※ 現代語訳 土屋博映中継出版「『奥の細道が面白いほどわかる本 」中経出版の超訳より |
|
|
|
|