●平安後期成立の第5番目の勅撰集、10巻。初度本は三代集時代の歌が多く新鮮味に欠けたようで、内容、構成も白河院の意向にそわず却下されました。
●そこで、2度目の選集作業にかかりました。二奏本は、当代歌人を重視した構成で、革新的な内容を盛り込みましたが、これも白河院が納得されませんでした。
●三奏本は、初度本と二奏本の中間的な歌人構成とし古・新の調和を図りました。
●納得した白河院が、清書途中の下書きの本を納められたので、撰者の手もとに三奏本は残らず、成立直後からほとんど世に流布しませんでした。
●一般に「金葉集」という場合は、世に最も流布した二奏本を指します。
●10首以上の入集歌数がある歌人は、74番・源俊頼、71番・源経信、藤原公実(きんざね)、藤原顕季(あきすえ)などすべて当代の歌人たちで、出典別で重視されたのは「堀河百首」です。
●その構成は、勅撰集としてはじめて全体を10巻仕立て(春・夏・秋・冬・賀・別・恋上・恋下・雑上・雑下)とした点です。
●伝統尊重と同時に、雑下に連歌を配し、日常語や俗語まで含んでいます。
●貴族社会の狭い範囲から、より幅広い階層にまで広がりを見せています。 |
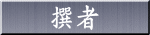

源俊頼
|