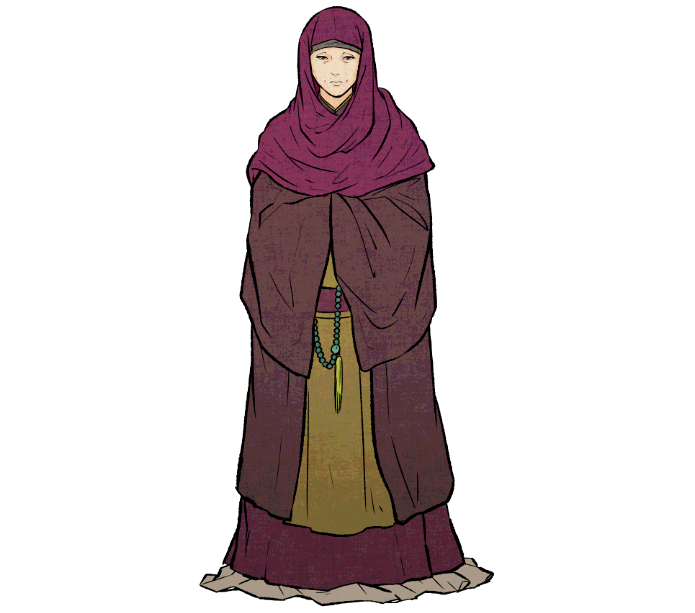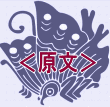
かかりしほどに、法皇は文治二年の春の比(ころ)、建礼門院の大原の閑居(かんきょ)の御住居(おんすまひ)御覧ぜまほしう思し召されけれども、如月弥生(きさらぎやよい)のほどは風烈(はげ)しく余寒(よかん)も未(いま)だ尽(つ)きず。峰の白雪消えやらで、谷の氷柱もうち解けず、春過ぎ夏来たつて北祭も過ぎしかば、法皇夜を籠(こ)めて大原の奥へ御幸成る。忍びの御幸なりけれども、供奉(ぐぶ)の人々には、徳大寺、花山院、土御門以下公卿六人、殿上人八人、北面少々候ひけり。鞍馬通りの御幸なれば、かの清原深養父が補陀洛寺、小野皇太后宮の旧跡叡覧(えいらん)あつて、それより御輿(おんこし)に召されけり。遠山に懸(か)かる白雲は散りにし花の形見なり。青葉に見ゆる梢(こずゑ)には春の名残ぞ惜しまるる。比(ころ)は卯月(うづき)二十日余りの事なれば、夏草の繁木(しげき)が末を分け入らせ給ふに、初めたる御幸なれば、御覧じ慣れたる方もなく、人跡絶えたるほども思し召しやられて哀れなり。 |
|

そうこうするうち、後白河法皇(ごしらかわほうおう)は、文治(ぶんじ)二年の春頃、建礼門院(けんれいもんいん)殿が住んでおられる大原の閑居(かんきょ)をご覧になろうとお思いになったが、二月・三月の頃は風も激(はげ)しく、余寒(よかん)もまだ残っていた。峰(みね)の白雪も消えやらず、谷の氷柱(つらら)もまだ解けず、春過ぎ夏が来て、賀茂(かも)の祭も過ぎたので、後白河法皇は夜明けを待たず大原の奥へ赴(おもむ)かれた。お忍(しの)びの御幸(ごこう)であったが、お供の人々には、徳大寺実定(とくだいじさねさだ)殿、花山院兼雅殿(かざんのいんかねまさ)、土御門通親(つちみかどのみちちか)殿以下、公卿(くぎょう)が六人、殿上人(てんじょうびと)が八人、北面武士(ほくめんのぶし)が少々付き従った。鞍馬(くらま)通りを経る御幸(ごごう)なので、清少納言(けいしょうなごん)の父・清原元輔(きよはらのもとすけ)の補陀洛寺(ふだらくじ)や後冷泉天皇中宮(ごれいぜいてんのうのちゅうぐう)の旧跡(きゅうせき)をご覧になり、それから御輿(おんこし)に乗られた。遠山にかかる白雲は、散った花を思わせる。青葉に見える梢(こずえ)には、春の名残があった。頃は四月二十日余りのこと、夏草の茂(しげ)みの先を分け入られると、初めての御幸なので、見慣れておられる景色もなく、人跡(じんせき)の途絶えた様子も察せられて哀れであった。 |
| 西の山の麓に一宇の御堂あり。即(すなわ)ち寂光院これなり。古(ふる)う作りなせる泉水、木立、由(よし)ある様(さま)の所なり。甍破(いらかやぶ)れては霧不断(きりふだん)の香を焚き、樞落(とぼそお)ちては月常住(じやうぢゆう)の燈(ともしび)を掲(かか)ぐとも、かやうの所をや申すべき。庭の夏草茂(しげ)り合ひ、青柳糸(あをやぎいと)を乱(みだ)りつつ、池の浮草波に漂(ただよ)ひ、錦(にしき)を曝(さら)すかと誤(あやま)たる。中島の松に懸(か)かれる藤波(ふぢなみ)の裏紫(うらむらさき)に咲ける色、青葉混(あおばま)じりの遅桜、初花(はつはな)よりも珍しく、岸の山吹咲き乱れ、八重立(やへた)つ雲の絶え間より山時鳥(やまほととぎす)の一声(ひとこゑ)も君の御幸(みゆき)を待ち顔なり。法皇これを叡覧(えいらん)あつて、かうぞ遊ばされける。 |
|
西の山の麓(ふもと)に一宇(いちう)の御堂(みどう)があった。これが寂光院(じゃっこういん)である。古びた作りの泉水(せんすい)や木立(こだち)を見れば、由緒(ゆうしょ)ありげな場所である。屋根瓦(やねがわら)は壊(こわ)れて、霧(きり)は絶え間ない香(こう)を焚(た)くかのごとく、落ちた扉(とびら)の隙間(すきま)からは月が常夜燈(じょうやとう)を掲(かか)げているごときであるというのはこういうところを言うのであろう。庭の夏草が生(お)い茂(しげ)り、青柳(あおやぎ)は糸が乱れるごとく、池の浮草は波に漂(ただよ)い、錦(にしき)を晒(さら)しているのかと見紛(みまが)う。池の中島の松に掛(か)かった藤(ふじ)が裏紫(うらむらさき)に咲いた色、青葉混(あおばま)じりの遅桜(おそざくら)、咲き始めの花よりも珍(めずら)しく、岸の山吹(やまぶき)は咲き乱れ、幾重(いくえ)にも湧(わ)き立つ雲の切れ間から聞こえるほととぎすの一声も、法皇のご到着(とうちゃく)を待っているようであった。法皇がこれをご覧になり、こう詠(よ)まれた。 |
| 池水に汀(みぎは)のさくらちりしきてなみの花こそさかりなりけれ |
|
池水に水際(みぎは)の桜が散り敷(し)いて、波の花が盛(さか)りになっている |
| 古(ふ)りにける岩の断間(たえま)より落ち来る水の音さへ故(ゆゑ)び由(よし)ある所なり。緑蘿(りよくら)の垣、翠黛(すいたい)の山、絵に書くとも筆も及び難し。女院の御庵室(ごあんじつ)を御覧ずれば、軒には蔦(つた)、牽牛(あさがほ)這(は)ひ懸(か)かり、忍交(しのぶま)じり忘れ草、 |
|
古びた岩の裂(さ)け目から落ちて来る水の音さえもわけありげな場所である。緑の蔦(つた)や葛(かずら)が絡(から)まる垣根(かきね)、緑黒色の山、絵にも描けそうにないほど見事である。建礼門院殿の庵(いおり)をご覧になると、軒(のき)には蔦(つた)や朝顔が這(は)い掛(か)かり、忍草(しのぶくさ)や忘れ草も茂(しげ)って、 |
| 「瓢箪屡空、草滋顔淵之巷、藜〔※注?〕深鎖、雨湿原憲之枢(瓢箪(へうたん)しばしば空(むな)し、草顔淵(くさがんゑん)の巷(ちまた)に滋(しげ)し、〔※注 藜? 〕深く鎖(さ)せり、雨原憲(あめげんけん)の枢(とぼそ)を湿(うる)ほす)」とも云つつべし。杉(すぎ)の葺目(ふきめ)も疎(まば)らにて、時雨(しぐれ)も霜(しも)も置く露(つゆ)も洩(も)る月影(つきかげ)に争ひて、堪(たま)るべしとも見えざりけり。後ろは山、前は野辺(のべ)、いささ小篠(をざさ)に風騒(かぜさわ)ぎ、世に堪(た)へぬ身の習(ならひ)ひとて、憂(う)き節繁(ふししげ)き竹柱(たけばしら)、都の方(かた)の言伝(ことづて)は間遠(まどほ)に結(ゆ)へる籬垣(ませがき)や、僅(わづ)かに事問ふ物とては、峰(みね)に木伝(こづた)ふ猿(さる)の声、賤(しづ)が爪木(つまぎ)の斧(おの)の音、これらが音信(おとづれ)ならでは、柾(まさき)の葛(かづら)、青葛(あおつづら)、来る人(ひと)稀(まれ)なる所なり。 |
|
「一瓢(いっぴょう)の飲み物も一箪(いったん)の食べ物もなく、草が孔子(こうし)の弟子(でし)・顔淵(がんえん)の家の近くに茂(しげ)り、また、あかざが深く茂って、雨はこれも孔子の弟子・原憲(げんけん)の家の戸を湿(しめ)らせる」とも言えそうである。杉の葺(ふ)き目もまばらで、時雨も霜も草に置く露もこぼれる月影に劣(おと)らず、防げるようには見えない。後ろは山、前は野辺、わずかな小笹(をざさ)に風が騒(さわ)ぎ、世捨(よす)て人の常として、節(ふし)の多い竹柱(たけばしら)の庵(いおり)、都からの便りも結った生垣(いけがき)のようにまばらで、わずかに訪れるものとしては、峰(みね)の木々を伝う猿の声や木こりの伐(き)る斧(おの)の音、これらが聞こえるばかりで、柾の葛や青葛が絡まり、来る人の稀(まれ)な場所であった。 |
| 法皇、 |
|
法皇は、 |
| 「人やある、人やある」 |
|
「どなたかおられるか、どなたか」 |
| と召(め)されけれども、御答へ申す者もなし。ややあつて、老い衰へたる尼一人参りたり。 |
|
と呼ばれたが、返事をする者もない。少しして、老(お)い衰(おと)えた尼(あま)が一人現れた。 |
| 「女院は何処(いづく)へ御幸(ごかう)成りぬるぞ」 |
|
「建礼門院はどこへ行かれたか」 |
| と仰せければ、 |
|
と仰(おお)せになると、 |
| 「この上の山へ花摘みに入らせ給ひて候ふ」 |
|
「この上の山へ花摘(はなつ)みに入られました」 |
| と申す。 |
|
と言う。 |
| 「さこそ世を厭(いと)ふ御習(おんなら)ひといひながら、さやうの事に仕へ奉るべき人も無きにや。御痛(おんいた)はしうこそ」 |
|
「いくら世捨(よす)て人の常とはいえ、こんな用事すら任せる者もいないのか。かわいそうなことだ」 |
| と仰せければ、この尼申しけるは、 |
|
と仰せになると、尼は、 |
| 「五戒十善の御果報尽(おんくわほうつ)きさせ給ふによつて、今かかる御目(おんめ)を御覧ぜられ候ふにこそ。捨身(しやしん)の行(ぎやう)になじかは御身(おんみ)を惜(お)しませ給ひ候ふべき。因果経には、『欲知過去因(よくちくわこいん)、見其現在果(けんごげんざいくわ)、欲知未来果(よくちみらいくわ)、見其現在因(けんごげんざいいん)』と説かれたり。過去未来の因果を予(かね)て悟らせ給ひなば、つやつや御嘆(おんなげ)きあるべからず。昔悉達太子(しつだたいし)は十九にて伽耶城を出で、檀特山の麓にて木の葉を連ねては膚(はだ)を隠し、峰に上つて薪を採り、谷に下りて水を結び、難行苦行の功(こう)によつて、つひに成等正覚(じやうとうしやうがく)し給ひき」 |
|
「五戒十善(ごかいじゅうぜん)の果報(かほう)がなくなられたので、今このような目に遭(あ)われているのです。捨て身の勤行(ごんぎょう)をしている者が、どうしてその身を惜しまれるでしょう。因果経(いんがきょう)には、『過去の因果を知りたければ、現在の果報を見よ、未来の果報を知りたければ、現在の因果を見よ』と説(と)かれております。過去・未来の因果をあらかじめ悟(さと)られていれば、なにも嘆(なげ)かれるものはありません。昔、釈尊(しゃくそん)は十九歳で伽耶城(がやじょう)を出、檀特山(だんどくせん)の麓(ふもと)で木の葉をまとって肌(はだ)を隠(か)し、峰(みね)に上って薪(たきぎ)を採(と)り、谷に下って水をすくい、難行苦行(なんぎょうくぎょう)の末に、ついに悟(さと)りを開かれたのです」 |
| とぞ申しける。この尼の有様(ありさま)を御覧ずれば、絹布(きぬぬの)の分きも見えぬ物を結び集めてぞ着たりける。あの有様にてもかやうの事申す不思議さよと思し召して、 |
|
と言われた。この尼のありさまをご覧になると、衣の生地(きじ)の区別もつかないような物を身にまとっている。こんななりで、こんなことを言うとはどうも妙(みょう)だと思われ、 |
| 「抑(そもそ)も汝(なんぢ)はいかなる者ぞ」 |
|
「いったいおまえは何者だ」 |
| と仰せければ、この尼さめざめと泣いて、暫(しば)しは御返事(おんぺんじ)にも及(およ)ばず。ややあつて、涙を押さへて、 |
|
と仰(おお)せられると、この尼はさめざめと泣いて、しばらくは返事もできなかった。少しして、涙をこらえて、 |
| 「申すにつけて憚(はばか)り覚え候へども、故少納言入道信西が娘、阿波内侍と申す者にて候ふなり。母は紀伊二位。さしも御(おん)いとほし深うこそ候ひしに、御覧じ忘れさせ給ふにつけても、身の衰(おとろ)へぬるほども思ひ知られて今更(いまさら)せん方なうこそ覚え候へ」 |
|
「申し上げるのもはばかられるのですが、今は亡(な)き少納言入道(しょうなごんにゅうどう)・藤原信西(ふじわらしんせい)の娘で阿波(あわ)の内侍(ないし)と申す者でございます。母は紀伊の二位・朝子でございます。あれほどご寵愛(ちょうあい)いただいておりましたのに、お気づきいただけないほど我が身が衰(おとろ)えたことを思い知らされるのは、仕方がないとはいえ、悲しいものでございます」 |
| とて袖を顔に押し当て忍び敢へぬ様、目も当てられず。 |
|
と袖(そで)を顔に押し当てて忍(しの)びなく様子は、正視(せいし)できないほどであった。 |
| 法皇、 |
|
法皇は、 |
| 「されば汝(なんぢ)は阿波内侍にこそあなれ。今更(いまさら)御覧じ忘れける。ただ夢とのみこそ思し召せ」 |
|
「そちは阿波の内侍なのか。見忘れていた。ただ夢とのみ思われよ」 |
| とて御涙塞(おんなみだせ)き敢(あ)へ給はず。 |
|
と涙をお止めになれなかった。 |
| 供奉(ぐぶ)の人々も、 |
|
お供の人々も、 |
| 「不思議の尼かなと思ひたれば、理(ことわ)りて申しけり」 |
|
「不思議な尼だと思っていたが、合点がいった」 |
| とぞ各(おのおの)感じ合はれける。 |
|
とおのおの感じ合われた。 |
| さて彼方此方を叡覧あれば、庭の千種露重く、籬に倒れ懸かりつつ、外面の小田も水越えて、鴫立つ隙も見え分かず。御庵室に入らせ給ひて障子を引き開けて御覧ずれば、一間には来迎の三尊おはします。中尊の御手には五色の糸を懸けられたり。左には普賢画像、右に善導和尚、並びに先帝の御影置きたり。八軸の妙文、九帖の御書も懸けられたり。蘭麝の匂ひに引き替へて香の煙ぞ立ち上る。かの浄名居士の方丈の室の内には三万二千の床を並べ、十方の諸仏を請じ奉り給ひけんもかくやとぞ覚えける。障子には諸経の要文共色紙に書いて所々に押されたり。その中に大江定基法師が清涼山にして詠じたりけん「笙歌遥聞孤雲上、聖衆来迎落日前」とも書かれたり。 |
|
そしてあちらこちらをご覧になると、庭の千草(ちくさ)は露(つゆ)がたくさん降り、生垣(いけがき)にもたれかかり、外面(そとも)の水田も水かさが増し、しぎの飛び立つのもわからない。庵(いおり)に入られ障子(しようじ)を開けてご覧になると、一間(ひとま)には来迎(らいこう)の阿弥陀(あみだ)・観音(かんのん)・勢至(せいし)の三尊(さんぞん)が安置されていた。中央の阿弥陀如来(あみだにょらい)の御手(みて)には五色(ごしき)の糸が掛(か)けられていた。左には普賢菩薩(ふげんぼさつ)の絵、右には唐・光明寺の善導和尚(ぜんどうおしょう)、並びに先の安徳天皇(あんとくてんのう)の肖像(しょうぞう)が置かれていた。法華経(ほけきょう)八巻、九帖(くじょう)の御書(ごしょ)も掛(か)けられていた。宮廷(きゅうてい)に薫(かお)っていた蘭(らん)の花と麝香(じゃこう)の匂(にお)いに替(か)わって香(こう)の煙が立っていた。かの天竺(てんじく)の浄名居士(じょうみょうこじ)の一丈四方の居室の内に三万二千の座を並べ、十方(じっぽう)の諸仏をお招(まね)きしたのもこうであったかと思われる。障子(しようじ)には諸経(しょきょう)の重要な文言などを色紙に書いてあちこちに貼(は)られてあった。その中に、大江定基法師(おおえのさだもとぼっし)が清涼山(しょうりょうぜん)で詠(よ)んたという「笙歌遥(しょうがはる)かに聞こえる孤雲(こうん)の上、聖衆来迎(しょうじゅらいごう)する落日の前」という句も書かれてあった。 |
| 少し引き退(の)けて、女院の御製(ぎょせい)と思しくて、 |
|
少し離(はな)れて、建礼門院殿の作と思(おぼ)しい歌があった。 |
| おもひきや深山の奥にすまひして雲井(くもゐ)の月をよそに見んとは |
|
思いがけない、深山(みやま)の奥に住みながら宮中の月をこんなところで見ることになるとは |
| さて傍らを御覧ずれば御寝所(ぎょしんじょ)と思しくて、竹の御竿(おんさを)に麻の御衣(おんころも)、紙の御衾(おんふすま)など懸(か)けられたり。さしも本朝漢土(ほんてうかんど)の妙(たへ)なる類数(たぐひかず)を尽(つ)くし、綾羅錦繍(りようらきんしう)の粧もさながら夢にぞなりにける。供奉の人々もまのあたり見参らせし事共なれば、今のやうに覚えて皆袖をぞ濡らされける。 |
|
そして傍(かたわ)らをご覧になると寝所(しんじょ)と思しく、竹の竿(さお)に麻(あさ)の衣、紙の布団などの夜具が掛(か)けられてあった。あれほど我が国や唐土(もろこし)の見事な衣類をことごとく集め、綾羅錦繍(りょうらきんしゅう)の装(よそお)いも、さながら夢になってしまった。お供の人々も当時を見て知っておられるので、それが今のように思えて皆、袖(そで)を濡(ぬ)らされた。 |
| さるほどに、上の山より濃墨染の衣着たる尼二人、岩の懸道(かけぢ)を伝ひつつ下り煩(わづら)はせ給ひけり。 |
|
さて、上の山から濃墨染(こきすみぞめ)の衣を着た尼(あま)が二人、険(けわ)しい岩道伝いを難儀(なんぎ)しながら下りてこようとされていた。 |
| 法皇御覧あつて、 |
|
法皇がご覧になり、 |
| 「あれは何者ぞ」 |
|
「あれは何者だ」 |
| と仰せければ、老尼涙を押さへて、申しけるは、 |
|
と仰せになると、老尼(ろうに)は涙をこらえ、 |
| 「花篋(はながたみ)肱(ひぢ)に懸(か)け、岩躑躅(いはつつじ)うち添(そ)へて持たせ給ひたるは、女院にて渡らせ給ひ候ふなり。爪木(つまぎ)に蕨(わらび)折り具して候ふは鳥飼中納言維実の娘、五条大納言国綱の養子、先帝(せんてい)の御乳母(おんめのと)大納言典侍局」 |
|
「花籠(はなかご)を肘(ひじ)に掛(か)け、岩つつじを添(そ)え持っておられるのが建礼門院でございます。薪(たきぎ)と蕨(わらび)をお持ちなのが鳥飼中納言(とりかいのちゅうなごん)・藤原伊実(ふじわらこれざね)殿の娘、五条大納言(ごじょうのだいなごん)・藤原邦綱(ふじわらのくにつな)殿の養子、先の安徳天皇の乳母(めのと)で大納言典侍局(だいなごんのすけのつぼね)」 |
| と申すも敢(あ)へず泣きけり。法皇も哀れげに思し召して御涙塞(おんなみだせ)き敢(あ)へさせ給はず。 |
|
と言うこともままならず泣かれた。法皇も哀(あは)れに思われて、涙をお止めになれなかった。 |
| 女院も、 |
|
建礼門院殿も、 |
| 「世を厭(いと)ふ御習(おんなら)ひといひながら、今かかる有様(ありさま)を見え参らせんずらん恥づかしさよ。消えも失(う)せばや」 |
|
「世捨(よす)て人の常とは言いながら、今このようなありさまをお見せする恥(は)づかしさ。消えてしまいたい」 |
| と思し召せどもかひぞなき。宵々毎(よひよひごと)の閼伽(あか)の水、結ぶ袂(たもと)も萎(しを)るるに、暁起(あかつきお)きの袖(そで)の上、山路の露(つゆ)も滋(しげ)しくて、絞(しぼ)りやかねさせ給ひけん、山へも帰らせ給はず、御庵室(おんあんじつ)へも入らせおはしまさず、あきれて立たせましましたる所に内侍の尼(あま)参りつつ、花篋(はながたみ)をば賜(たま)はりけり。 |
|
と思われたが仕方がなかった。毎夜の仏前に供える水で袂(たもと)は萎(しお)れているのに、早朝起きて山路(やまじ)を行くので、袖(そで)はたくさんの露(つゆ)に濡(ぬ)れ、露(つゆ)と涙で絞(しぼ)りかね、いまさら山へも帰られず、庵(いおり)へも入られず、途方(とほう)に暮(く)れて立っていたところ、内侍(ないし)の尼(あま)が参り、花籠(はなかご)を受け取られたのだった。 |