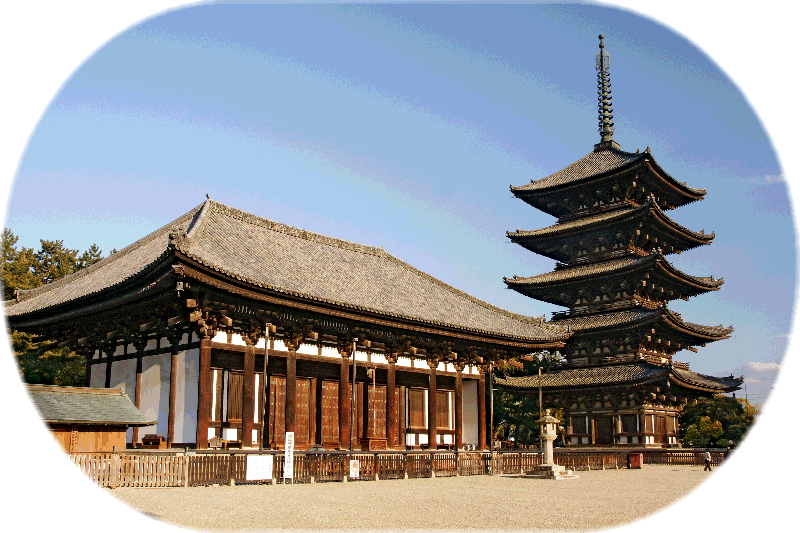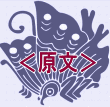
さるほどに、本三位中将重衡卿をば狩野介宗茂に預けられて、去年より伊豆国におはしけるが、南都の大衆頻(しき)りに申しければ、 |
|

さて、本三位中将重衡(ほんざんみのちゅうじょうしげひら)殿は狩野宗茂(かののすけむねもち)に預(あず)けられて、去年から伊豆国(いずのくに)におられたが、奈良・興福寺(こうふくじ)の大衆(だいしゆ)がしきりに要求してくるので、 |
| 「さらば渡さるべし」 |
|
「ならば引き渡そう」 |
| とて源三位入道(げんざんみにふだう)の孫(まご)、伊豆蔵人大夫頼兼に仰(おお)せて、つひに奈良へぞ遣(つか)はされける。今度は都の内へは入れず、大津より山科通りに醍醐路(だいごぢ)を経て行けば、日野は近かりけり。この北方と申すは鳥飼中納言惟実の娘、五条大納言国綱の養子、先帝御乳母(せんていのおんめのと)、大納言典侍局とぞ申しける。中将一谷(いちのたに)にて生捕(いけどり)にせられ給ひて後は先帝に付き参らせてましましけるが、壇浦にて海に沈(し)み給ひしかば、武士(もののふ)の荒気(あらけ)なきに捕(とら)はれて旧里(きうり)に帰り、姉の大夫三位に同宿(どうじゆく)して日野といふ所にぞましましける。三位中将の露の命、草葉の末に懸(か)かつて未だ消えやり給はずと聞き給ひて、いかにもして今一度変はらぬ姿を見もし見えばやと思ひて待たれけれども、それも叶(かな)はず、ただ泣くより外(ほか)の慰(なぐさ)みなくて明かし暮(く)らし給ひけり。 |
|
と、源頼政(みなもとのよりまさ)殿の孫・伊豆蔵人大夫頼兼(いずのくらんどのたいふよりかね)に命じて、ついに興福寺に引き渡した。今回は都の中へは入れず、大津から山科(やましな)を通り、醍醐(だいご)を経て行ったので、日野(ひの)は近かった。重衡殿の北の方・輔子(すけこ)殿というのは、鳥飼中納言(とりかいのちゅうなごん)・藤原伊実(ふじわらのこれざね)の娘、五条大納言(ごじょうのだいなごん)・藤原邦綱(ふじわらのくにつな)の養子、先の安徳天皇(あんとくてんのう)の乳母(めのと)で、大納言典侍局(だいなごんのすけのつぼね)と言う。重衡殿が一の谷で生(い)け捕(ど)りにされて後は先の安徳天皇に仕えておられたが、壇(だん)の浦(うら)で海に沈(しず)まれると、荒武者たちに捕らえられて京へ帰り、姉の大夫三位(だいぶざんみ)・成子(なりこ)殿と共に日野というところで過ごされていた。重衡殿の露(つゆ)の命は草葉(くさば)の先にひっかかり、まだ消えておられないと聞かれ、なんとかしてもう一度、変わらぬ姿を見たいと思って待っていたが、それも叶(かな)わず、ただ泣くよりほかに慰(なぐさ)みはなく、悲しみに明け暮(く)れておられた。 |
| 三位中将、守護の武士共に宣ひけるは、 |
|
重衡殿は守護(しゅご)の武士たちに、 |
| 「さてもこのほど各(おのおの)の情深(なさけふか)う芳志(ほうし)おはしつる事こそ何よりもまた嬉(うれ)しけれ。今一度最後に芳恩(ほうおん)蒙(かうぶ)りたき事あり。我は一人の子無ければ憂(う)き世に思ひ置く事なし。年来(としごろ)契(ちぎ)りたりし女房の日野といふ所に在りと聞く。今一度対面して後生(ごしやう)の事をも申し置かばやと思ふはいかに」 |
|
「このたび、おのおの方が情け深く世話を焼いてくれたことはなにより嬉(うれ)しかった。もう一度、最後にお願いしたいことがある。私は子が一人もいないので、この世に思い残すことはない。長年連れ添(そ)っていた女房が日野というところにいると聞いた。もう一度逢(あ)って、後世のことを話しておきたいと思うのだが、どうか」 |
| と宣へば、武士も岩木ならねば皆涙を流いて、 |
|
と言われると、武士も岩や木ではないので、皆涙を流して、 |
| 「まことに女房などの御事は何か苦しう候ふべき、疾(はよ)う疾(はよ)う」 |
|
「女房のことなど何の問題がありましょう、さあ、すぐにでも」 |
| とて許し奉る。三位中将斜めならず悦び、 |
|
と許(ゆる)した。重衡殿はとても喜び、 |
| 「大納言典侍局のこれに御渡(おんわた)り候ふやらん。只今(ただいま)三位中将殿の奈良へ御通り候ふが、立ちながら御見参(おんげんざん)に入らんと候ふ」 |
|
「大納言典侍殿はここにいるのでしょうか。たった今、重衡殿が奈良に向かう途中でお通りになりますが、立ったままでお目にかかりたいと言っておられます」 |
| と人を入れて云はせたりければ、北方、 |
|
と人を通じて言わせれば、大納言典侍殿が、 |
| 「何処(いづら)や、何処(いづら)や」 |
|
「どこですか、どこですか」 |
| とて走り出で見給へば、藍摺の直垂に折烏帽子着たる男の痩せ黒みたるが縁に寄り居たるぞ、そなりける。北方御簾の際近(きはちか)く出でて、 |
|
と走り出てご覧になると、藍摺(あいずり)の直垂(ひたたれ)に折烏帽子(おりえぼし)を着て、縁(へり)に寄りかかっている痩(や)せ黒ずんだ男がいた、重衡殿であった。大納言典侍殿は御簾(みす)のそばまで出られ、 |
| 「いかにやいかにや。夢かや現(うつつ)か。これへ入らせ給へ」 |
|
「どうしてどうして。夢かうつつか。こちらへお入りください」 |
| と宣ひける。御声(おんこゑ)を聞き給ふにつけてもただ先立つものは涙なり。 |
|
と言われた。声を聞かれるにつけても、ただ先立つものは涙(なみだ)ばかりであった。 |
| 三位中将御簾うち被(かづ)き、泣く泣く宣ひけるは、 |
|
重衡殿は御簾を上げ、泣きながら、 |
| 「西国にてもいかにも成るべかりし身の、生きながら囚はれて、京、鎌倉恥を曝(さら)すのみならず、果(は)ては南都の大衆の手へ渡されて斬(き)らるべしとて罷(まか)り候ふ。夢ならずして今一度逢(あ)ひ見奉る事もやと存じ候ひつるに、今は露ほども憂(う)き世に思ひ置く事なし。出家して形見に髪をも奉るべう候へども、かかる身に罷(まか)り成つて候へば力及(ちからおよ)ばず」 |
|
「西国で最期(さいご)を遂(と)げるはずだった身が、生きながら囚(とら)われて、京、鎌倉と恥(はじ)を晒(さら)すばかりでなく、挙(あ)げ句(く)の果てに奈良・興福寺(こうふくじ)の大衆(だいしゅ)に引き渡されて斬(き)られることになり、そこへ向かう途中なのです。なんとかしてもう一度逢(あ)って顔を見たいと思っていたので、もうこの世に露(つゆ)ほども未練(みれん)はありません。出家して髪(かみ)を形見(かたみ)に渡そうとも思いましたが、このような身になってしまったのでそれもできません」 |
| とて額の髪を引き分け、口の及(およ)ぶ所を少し食(く)ひ切つて、 |
|
と言うと、額(ひたい)の髪を引き分け、歯が届(とど)くところを少し噛(か)み切って、 |
| 「これを形見に御覧ぜよ」 |
|
「これを形見(かたみ)に見てやってください」 |
| とて置かれければ、北方日比(ひごろ)覚束(おぼつか)なう思しけるより、今一入(ひとしほ)思ひの色をぞ増さられける。ややあつて、北方涙を押さへて宣ひけるは、 |
|
と置かれると、大納言典侍殿は日頃の頼(たよ)りなさよりもなお憂(うれ)えの色を深められた。少しして、大納言典侍殿は涙をこらえて、 |
| 「まこと二位殿、越前三位(ゑちぜんのさんみ)の上(うへ)のやうに水の底にも沈むべかりしかども、正(まさ)しうこの世におはせぬ人とも聞かざりしかば、変はらぬ姿を今見もし見えばやと思ひてこそ憂(う)きながら今日までも長らへたれ。今まで長らへたりつるは、もしやと思ふ頼(たの)みもありつるものを、さては今日を限りにておはすらん事よ」 |
|
「本来なら、八条二位(はちじょうのにい)殿や通盛(みちもり)殿の北の方・小宰相(こざいしょう)殿のように、水の底へ沈(しず)むべきであったのでしょうが、たしかにこの世にはおられないとも聞いていなかったので、変わらぬ姿をもう一度見たいと思うがゆえに、つらいながらも今日まで生き長らえてきました。今まで生き長らえたのは、もしかしたらという願いがあったからこそでした。それももう今日が最後ですね」 |
| とて昔今(むかしいま)の事共(ことども)宣ひ交(か)はすにつけても、ただ尽(つ)きせぬものは涙なり。北方、 |
|
と、昔や今のことなどを語り合うにつけても、ただただ涙がこぼれてくる。大納言典侍殿は |
| 「あまりに御姿(おんすがた)の萎(しを)れ候ふに、奉(たてまつ)り替(か)へよ」 |
|
「あまりにお姿がやつれて見えますから、着替(きか)えをなさいませ」 |
| とて袷衣(あはせ)の小袖(こそで)に浄衣(じやうえ)を添(そ)へて出(い)だされたり。中将これを着替へつつ日比(ひごろ)着給ひたる装束をば、 |
|
と、裏地のついた衣の小袖(こそで)に僧用の白衣を添(そ)えて渡された。重衡殿はこれに着替(きか)えながら、日頃(ひごろ)着ておられた装束(しょうぞく)を、 |
| 「形見に御覧(ごらん)ぜよ」 |
|
「形見にしてください」 |
| とて置かれけれ。北方、 |
|
と言って置かれた。大納言典侍殿は、 |
| 「それもさる御事にて候へども、はかなき筆の跡こそ長き世の形見にて候へ」 |
|
「それもありがたいのですが、ちょっとした筆の跡(あと)こそ長い世の形見になります」 |
| とて御硯(おんすずり)を出(い)だされたり。中将泣く泣く一首の歌をぞ書き給ふ。 |
|
と硯(すずり)を出された。中将は泣きながら一首の歌を書かれた。 |
| せきかねてなみだのかかるから衣(ころも)後(のち)のかたみにぬぎぞかへぬる |
|
止めかねて涙のかかる唐衣(からごろも)、後(のち)の形見に脱(ぬ)ぎ替(か)えました |
| 北方の返事に、 |
|
大納言典侍殿の返事に、 |
| ぬぎかふる衣も今は何かせん今日(けふ)をかぎりのかたみとおもへば |
|
脱(ぬ)ぎ替(か)えた衣ももう役に立ちません、今日限りの形見と思います |
| 「後の世には生れ逢(あ)ひ奉らん。必ず一蓮(ひとつはちす)にと祈り給へ。日も闌(たけ)ぬ。奈良へも遠(とほ)う候ふ。武士の待つらんも心無し」 |
|
「後(のち)の世(よ)でもう一度巡(めぐ)り逢(あ)いましょう。どうか一蓮托生(いちれんたくしょう)を祈ってください。日も傾きました。奈良もまだ遠くです。武士を待たせるのも気になります」 |
| とて出でられければ、北方(きたのかた)中将(ちゆうじやう)の袂(そで)にすがり、 |
|
と出られると、大納言典侍殿は重衡殿の袖(そで)にすがりつき、 |
| 「いかにや、暫(しば)し」 |
|
「どうか、あと少しだけ」 |
| とて引き留(とど)め給へば、中将、 |
|
と引き止められると、重衡殿は、 |
| 「心の内をばただ推(お)し量(はか)り給ふべし。されどもつひには長らへ果(は)つべき身にもあらず」 |
|
「この気持ちをどうかわかってください。天寿(てんじゅ)を全(まっと)うできる身ではないのです」 |
| とて思ひ切つてぞ出(い)でられける。まことにこの世にて逢(あ)ひ見ん事もこれぞ限りと思はれければ、今一度立ち帰りたくは思はれけれども、心弱うては叶(かな)はじと思ひ切つてぞ出でられける。 |
|
と思い切って出発された。本当にこの世で顔を合わせるのもこれが最後と思われると、もう一度立ち帰りたくなったが、弱気ではいけないと思い切って出発されたのだった。 |
| 北方は御簾の外まで転び出で、喚(をめ)き叫(さ)び給ひける御声(おんこゑ)の門(かど)の外(ほか)まで遥(はる)かに聞えければ、中将涙に暮(く)れて行先(ゆくさき)も見えねば、駒(こま)をも更(さら)に早め給はず、中々(なかなか)なりける見参(げんざん)かなと、今は悔(くや)しうぞ思はれける。 |
|
大納言典侍殿が御簾(みす)の外まで転び出て、泣き叫ばれる声は門(かど)の外遥(ほかはる)かまで聞こえたので、重衡殿は涙があふれて前も見えず、馬を早めることもできず、やっぱり逢(あ)わなければよかったと、今は後悔(こうかい)されていた。 |
| 北方、やがて走り出でておはしぬべうは思はれけれども、それもさすがなればとて引き被(かづ)いてぞ臥(ふ)し給ふ。 |
|
大納言典侍殿は、すぐに走って追いかけたいとは思われたが、それもできないからと衣を被(かぶ)って臥(ふ)せられた。 |
| さるほどに、南都大衆、三位中将受け取り奉つて、いかがすべきと僉議(せんぎ)す。 |
|
さて、興福寺の大衆(だいしゅ)は重衡殿の身柄(みがら)を引き受けると、処分(しょぶん)について評議(ひょうぎ)した。 |
| 「抑(そもそ)もこの重衡卿は大犯(だいぼん)の悪人なる上、三千五刑(けい)の内にも洩(も)れ、修因感果(しゆいんかんくわ)の道理極定(どうりごくじやう)せり。仏敵法敵の逆臣なれば、頗(すこぶ)る東大寺、興福寺両寺の大垣を廻(めぐ)らして堀首(ほりくび)にやすべき、また鋸にてや斬(き)るべき」 |
|
「そもそもこの重衡殿は重大な犯罪(はんざい)を犯(おか)し、それは五刑(けい)の中の三千の刑にも見当たらないほどで、その因果(いんが)によって受ける道理は当然といえる。仏敵(ぶってき)・法敵(ほうてき)の逆臣(ぎゃくしん)だから、東大寺・興福寺両寺の外の大垣(おおがき)を引き回した上で、首まで地中に埋めるか、それとも首を鋸(のこぎり)で引くべきだ」 |
| と僉議(せんぎ)す。老僧共の僉議しけるは、 |
|
と言い合った。老僧たちは、 |
| 「それも僧徒(そうと)の法に穏便(をんびん)ならず。ただ武士に賜うで木津の辺にて斬らすべし」 |
|
「そのようなことは僧のすべきことではない。武士に任せて、木津(こつ)の辺で斬(き)らせよう」 |
| とてつひに武士の手へ返されける。武士これを受け取つて、木津川(こつがは)の端にて既(すで)に斬り奉らんとしけるに、数千人の大衆、守護の武士、見る人幾万(いくまん)といふ数を知らず。 |
|
と、ついに武士の手に返された。武士は重衡殿を預かって、木津川の端(はた)でまさに斬ろうとしたとき、数千人の大衆、守護の武士らが集まって、見る人は何万という数も知れない。 |
| ここに三位中将の侍(さぶらひ)に木工右馬允知時といふ者あり。八条女院(はつでうのにようゐん)に候ひけるが、最後を見奉らんとて鞭を打ちてぞ馳(は)せたりける。既(すで)に斬り奉らんとしける処(ところ)に馳せ着いて、急ぎ馬より飛んで下り、千万(せんばん)人の立ち囲(かこ)うだる中を押(お)し分け押し分け三位中将の御側(おんそば)近う参つて、 |
|
ここに重衡殿の侍で木工右馬允知時(むくうまのじょうともとき)という者がいた。八条二位殿に仕えていたが、最期(さいご)を一目見ようと鞭(むち)を打って駆(か)けつけてきた。まさに斬(き)ろうとしているところに到着(とうちゃく)して、急いで馬から飛び下り、千・万人が取り囲んでいるのを押(お)し分けながら重衡殿のそば近くに参り、 |
| 「知時こそ最後を見奉(みたてまつ)らんとて参つて候へ」 |
|
「私が最期を看取(みと)りに参りました」 |
| と申しければ、中将、 |
|
と言うと、重衡殿は、 |
| 「志のほどまことに神妙(しんべう)なり。あはれ同じうは最後に仏を拝み奉つて斬らればやと思ふはいかに。あまりに罪深う覚(おぼ)ゆるに」 |
|
「その志(こころざし)、実に殊勝(しゅしょう)だ。ところで、できるなら最後に仏を拝(おが)んで斬(き)られようと思うのだが、どうだ。あまりに罪深(つみぶか)く思えるから」 |
| と宣へば、知時、 |
|
と言われると、知時は、 |
| 「安いほどの御事(おんこと)候ふ」 |
|
「お安い御用(ごよう)です」 |
| とて守護の武士に申し合はせて、その辺より仏を一体迎へ奉つて出で来たり。幸(さいは)ひに阿弥陀(あみだ)にてぞましましける。河原の沙(いさご)の上に据(す)ゑ奉り、知時狩衣の袖の括りを解いて、仏の御手に懸(か)け、中将に控(ひか)へさせ奉る。中将これを控へつつ、仏に向かつて申されけるは、 |
|
と警護(けいご)の武士と相談して、その辺(へん)の里から仏を一体(いったい)迎(むか)えてやって来た。幸いに阿弥陀如来(あみだにょらい)であられた。河原(かわら)の砂の上に据(す)え、知時は狩衣(かりぎぬ)の袖(そで)の括(くく)りを解(と)くと仏の御手(みて)に掛(か)けると、重衡殿に紐(ひも)を持たせた。重盛殿はこれを持ちながら、仏に向かって、 |
| 「伝へ聞く、調達(でうだつ)が三逆を作り、八万蔵(ざう)の聖教(しやうげう)を焼き滅ぼししも、つひには天王如来の記別(きべつ)に預る。所作(しよさ)の罪業(ざいごふ)まことに深しといへども聖教に値遇(ちぐ)せし逆縁朽ちずして却(かえ)つて得道(とくだう)の因となる。まことに重衡が逆罪を犯す事全く愚意(ぐい)の発起(ほつき)にあらず。ただ世の理を存ずるばかりなり。生を受くる者誰か父の命を背かん。命を保つ者誰か王命を蔑如(べつじよ)する。かれといひこれといひ、辞(じ)するに処(ところ)なし。理非仏陀(りひぶつだ)の照覧(せうらん)にあり。抑(そもそ)も罪報立ち所に報(むく)い、運命既(すで)に只今(ただいま)を限りとす。後悔千万(こうくわいせんばん)悲しんでもなほ余りあり。但(ただ)し三宝(さんぼう)の境界(きやうがい)は慈悲(じひ)を以(もつ)て心とする故に済度(さいど)の良縁(りやうえん)区々(まちまち)なり。唯円教意(ゆいゑんげうい)、逆則是順(ぎやくそくぜじゆん)、この文肝(もんきも)に銘(めい)ず。一念弥陀仏(いちねんみだぶつ)、即滅無量罪(そくめつむりやうざい)、願はくは逆縁を以て順縁(じゆんえん)とし、只今最後の念仏によつて九品託生(くぼんたくしやう)を遂(と)ぐべし」 |
|
「伝え聞くところによれば、堤婆達多(だいばだった)が三逆(ぎゃく)の罪を犯し、八万蔵(ぞう)の教典を焼き滅(ほろ)ぼしても、ついには天王如来(てんおうにょらい)となることを認められました。その行動は実に罪深(つみぶか)いとはいえ、仏教に巡(めぐ)り逢(あ)った逆縁(ぎゃくえん)は朽(く)ちず、却(かえ)って今は仏道に入るきっかけとなりました。本当に、私は逆罪など少しも企(くわだ)ててはおりません。ただ世の中の理(ことわり)がここにあるばかりです。この世に生を受けた者の中で、誰が父の命令に背(そむ)くでしょうか。生き延(の)びる者で、誰が天皇の命令をないがしろにするでしょうか。あれといい、これといい、断ることはできません。事の理非(りひ)は釈尊(しゃくそん)がご存じです。我が罪(つみ)はたちどころに報(むく)い、運命がまさに尽(つ)きようとしております。どれほど後悔(こうかい)し、悲しんでもしきれません。ただし、仏法(ぶっぽう)の本意は慈悲(じひ)を第一とするがゆえに、衆生を救うきっかけはさまざまであるといいます。唯円教(ゆいえんきょう)に照らせば、逆縁(ぎゃくえん)は則(すなわ)ちこれ順縁(じゅんえん)である。この文(もん)を肝(きも)に銘(めい)じました。一度弥陀仏を念ずれば、即(すなわ)ちに無量の罪の滅する。願わくは逆縁を順縁とし、今の最後の念仏によって九品(くぼん)の浄土(じょうど)へ生まれ変われますように」 |
| とて首を延(の)べてぞ討(う)たせられける。日比(ひごろ)の悪行はさる事なれども、只今の有様を見奉るに、数千人の大衆、守護の武士共も皆鎧の袖をぞ濡らしける。首をば般若寺の門の前に釘付(くぎづ)けにこそ懸(か)けたりけれ。これは去んぬる治承の合戦の時、此処(ここ)に打つ立つて伽藍を滅ぼし給ひたりし故(ゆゑ)とぞ聞えし。 |
|
と、首を伸ばして討たれた。日頃の悪行(あくぎょう)はよくないのは当然だが、今の様子を見ていると、数千人の大衆(だいしゅ)や警護(けいご)の武士たちも皆鎧(よろい)の袖(そで)を濡(ぬ)らした。首を般若寺(はんにゃじ)の門前に釘(くぎ)で打って掛(か)けられた。これは去る治承(じしょう)の合戦の時、重衡殿がここに立って伽藍(がらん)を滅(ほろ)ぼされたからだと聞いている。 |
| 北方、大納言典侍殿、たとひ首をこそ刎(は)ねらるとも、骸(むくろ)は捨て置きたりければ、これを取つて輿に入れ、日野へ舁(か)いてぞ帰りける。昨日まではさしもゆゆしうおはせしかども、かやうに暑き比(ころ)なれば、いつしかあらぬ様(さま)に成り給ひぬ。これを待ち受けて見給ひける北方の心の内、推(お)し量(はか)られて哀れなり。さてしもあるべき事ならねば、その辺近(へんちか)き法界寺へ入れ奉り、貴き僧を語らひ、形の如(ごと)く御仏事営み給ふぞ哀れなる。首をば大仏の聖俊乗房にかうと宣へば、大衆に乞(こ)ひて日野へぞ遣はしける。首も骸も煙に成し、骨をば高野へ送り、墓をば日野にぞせられける。北方やがて様(さま)を変へ、濃墨染に窶(やつ)れ果(は)てて、かの後世菩提(ごせぼだい)を弔ひ給ふぞ哀れなる。 |
|
たとえ首を刎(は)ねられても、胴体(どうたい)は放置されていたので、大納言典侍殿はこれを拾って輿(こし)に入れ、日野へ担(かつ)いで帰られた。昨日までは、あれほど立派にしておられたが、このように暑い時期であったので、いつしか腐(くさ)ってひどいありさまになってしまった。これを待ち受けてご覧になる大納言典侍殿の心の内は、察するほどに哀(あわ)れであった。しかしそうしてばかりもいられないので、近くにある法界寺(ほうかいじ)へお入れし、貴(とうと)い僧に頼んで、形どおりに仏事を営まれたのが哀(かな)しい。首を大仏の聖(ひじり)・俊乗房(しゅんじょうぼう)にしかじかと伝えると、大衆(だいしゅ)を集めて日野へ遣(つか)わした。首も骸(むくろ)も煙ににして、骨(こつ)を高野山へ送り、日野に墓を築(きず)かれた。大納言典侍殿はすぐに出家し、濃墨染(こきすみぞめ)を着て、すっかりやつれ果て、重衡殿の後世(ごせ)・菩提(ぼだい)を弔(とむら)われたのが哀(あわ)れであった。 |