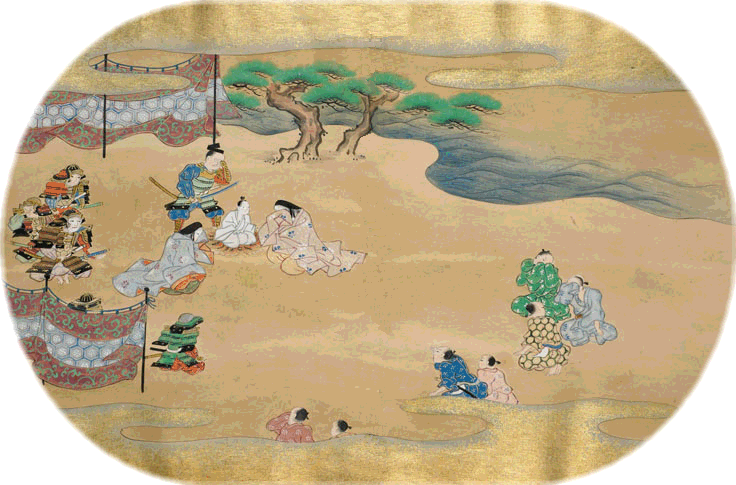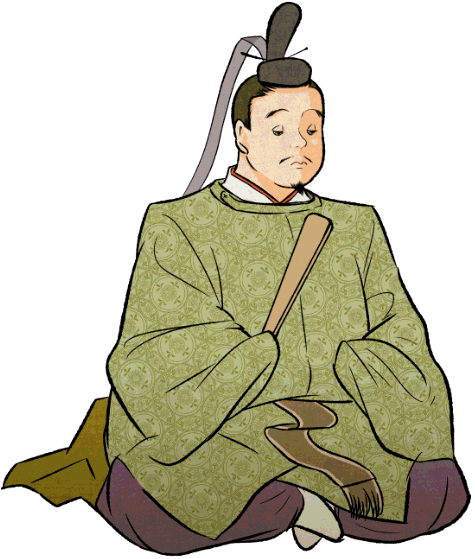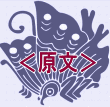
さるほどに、元暦二年五月七日、九郎大夫判官義経、大臣殿父子(おほいとのふし)具足(ぐそく)し奉つて関東へ下らるべき由(よし)聞えしかば、大臣殿判官の許(もと)へ使者を立てて、 |
|

さて、元暦二年五月七日、九郎大夫判官義経(くろうだいふのほうがんよしつね)殿が、平宗盛(たいらのむねもり)殿・清宗(きよむね)殿父子を連れて関東へ下ることになると、宗盛殿は義経殿のもとへ使者を送り、 |
| 「明日関東へ下向(げこう)の由(よし)その聞え候ふ。それにつきては生捕(いけどり)の中に八歳の童(わらは)とつけられ参らせて候ふは、未(いま)だ憂(う)き世に候ふやらん。給はつて今一度見候はばや」 |
|
「明日関東へ下ると伺(うかが)いました。ところで、捕虜(ほりょ)の中にいるという八歳の童子(どうじ)はまだこの世におりますか。生きていたら、もう一度逢いたいのですが」 |
| と申されたりければ、判官の返事に、 |
|
と言われると、義経殿は |
| 「誰(たれ)とても恩愛の道は思ひ切られぬ事にて候へば、まことにさこそ思し召され候ふらめ」 |
|
「誰も恩愛(おんあい)の道というのは思いを断(た)てないものですから、本当にそう思われているのでしょう」 |
| とて河越小太郎重房が許(もと)に預け置き奉つたりける若君を急ぎ大臣殿の許へ具足(ぐそく)し奉るべき由(よし)宣ひ遣はされたりければ、河越、人に車借りて乗せ奉る。二人の女房共も共に乗りてぞ出でにける。 |
|
と、河越小太郎重房(かわごえのこたろうしげふさ)のところに預(あず)け置かれていた若君(わかぎみ)を急いで宗盛大臣殿のもとへお連れするよう使者に命じられたので、重房は人に車を借りてお乗せした。二人の女房たちも共に乗って出た。 |
| 若君は父を遥(はる)かに見参らせ給はねば、世に懐(なつ)かしげにてぞましましける。大臣殿、若君を見給ひて、 |
|
若君は父を遠くにご覧になり、とても嬉(うれ)しそうにされていた。宗盛殿も若君をご覧になり、 |
| 「いかにや副将軍御前(ふくしょうぐんごぜん)、これへ」 |
|
「さあ副将軍(ふくしょうぐん)殿、こちらへ」 |
| と宣へば、急ぎ父の御膝(おんひざ)の上へぞ参られける。大臣殿、若君の髪掻(か)き撫(な)で、涙をはらはらと流いて、 |
|
と言われると、急いで父の膝(ひざ)の上に乗られた。宗盛殿は若君の髪(かみ)をかき撫(な)で、涙をほろほろ流して、 |
| 「これ聞き給へ各、この子は母もなき者にてあるぞよ。この子が母はこれを生むとて産(さん)をば平(たひ)らかにしたりしかども、やがて臥(ふ)し悩(なや)みしが、七日といふにはかなくなりてあるぞとよ。『この後いかなる人の腹に君達(きんだち)を設(もう)け給ふとも、これをば思し召し捨てずして、わらはが形見に御覧ぜよ。差し放つて乳母(めのと)などの許(もと)へも遣(つか)はすな』と云ひし事が不便(ふびん)さに、朝敵を平らげん時、あの右衛門督(うゑもんのかみ)には大将軍せさせ、これには副将軍をせさせんずればとて、名を副将と付けたりしかば、斜(なの)めならず嬉(うれ)しげにて、今を限りの時までも名を云ひなどして愛せしが、七日といふにつひにはかなくなるとぞよ。この子を見る度毎(たびごと)にはその事が忘れ難く覚ゆるぞや」 |
|
「おのおの方聞いてください、この子には母がいないのです。この子の母は、この子を産むときには安産でしたが、そのまま起きることができず、七日目に世を去ったのです。『この後、どんな人との間に若君が生まれても、この子を決してお捨てにならず、私の形見(かたみ)と思ってください。決してお放しにならず、乳母などにも預けないでください』と言っていたのがかわいそうで、朝敵(ちょうてき)を征伐(せいばつ)するとき、そこにいる清宗(きよむね)に大将軍をさせ、これには副将軍をさせよう、そう思って、名を副将(ふくしょう)とつけると、彼女はとても喜んで、死ぬまでその名を呼んでかわいがっていましたが、七日目についに世を去ったのです。この子を見るたびにそのこと思い出されるのです」 |
| とて泣かれければ、守護の武士共も皆鎧の袖をぞ絞りける。ややあつて大臣殿、 |
|
と言って泣かれると、守護(しゅご)の武士たちも皆鎧(よろい)の袖(そで)を絞(しぼ)った。少しして、宗盛殿は、 |
| 「いかに副将よ、早う帰れ」 |
|
「さあ副将よ、早く帰れ」 |
| と宣へども、若君帰り給はず。右衛門督これを見給ひて、 |
|
と言われたが、若君は帰ろうとなさらない。清宗殿がこれをご覧になり、 |
| 「あはれいかにや副将御前、今夜は疾(はや)う帰れ。只今(ただいま)客人(まらうと)の来うずるに、朝は急ぎ参れ」 |
|
「なにをしている、副将よ、今夜は早く帰れ。もうすぐお客さんがやって来る、また明日の朝急いで参れ」 |
| と宣へども、父の御浄衣(おんじやうえ)の袖にひしと取り付いて、 |
|
と言われたが、父の浄衣(じょうえ)の袖(そで)にしがみつき、 |
| 「否(いな)や帰らじ」 |
|
「いやだ、帰らない」 |
| とこそ泣かれけれ。 |
|
と泣かれた。 |
| かくて遥(はる)かにほど経れば、日も漸(やうや)う暮(く)れかかりぬ。さてしもあるべき事ならねば、乳母の女房抱き取つて、つひに車に乗せ奉る。二人の女房共も袖を顔に押し当て、泣く泣く暇(いとま)申しつつ、共に乗つてぞ出でにける。大臣殿は若君の後ろを遥かに御覧じ送つて、 |
|
こうしてずいぶんと時間が経って、日も傾いてきた。しかしそうしてばかりもいられないので、乳母の女房が抱え、ついに車にお乗せした。二人の女房たちも袖を顔に押し当て、泣きながらあいさつをして、共に乗って出て行った。宗盛殿は遠ざかる若君のずっと見送られ、 |
| 「日比(ひごろ)の恋しさは事の数ならず」 |
|
「日頃の寂(さび)しさなど今に較べたら物の数ではない」 |
| とぞ悲しみ給ひける。この子は母の遺言の無慙(むざん)さに、差し放つて乳母(めのと)などの許(もと)へも遣(つわ)はさず、朝夕御前(おんまえ)にて育て給ふ。三歳で初冠(うひかぶり)させて、義宗とぞ名乗らせける。漸(やうや)う生(お)ひ立ち給ふほどに眉目形(みめかたち)世に勝(まさ)れ、心様優(こころざまいう)におはしければ、大臣殿も斜(なな)めならず嬉(うれ)しき事に思して、されば西海の旅の空、舟の内のまでも引き具(ぐ)して片時も離(はな)れ給はず。然(しか)るを軍(いくさ)敗れて後は今日ぞ互ひに見給ひける。 |
|
と悲しまれた。この子は母の遺言(ゆいごん)のあるがゆえに、乳母などに預けることもなく、朝夕父の御前で育てられた。三歳で元服(げんぷく)させ、義宗(よしむね)と名乗らせた。成長するにしたがって容貌(ようぼう)も美しくなり、心も優(やさ)しかったので、宗盛殿もとても嬉(うれ)しく思われて、西海の旅の空、舟の内のまでも連れてゆき、片時(かたとき)もお離(はな)しにならなかった。それが、合戦に敗れて後は、今日初めて互いの顔を合わせたのだった。 |
| 重房、判官に申しけるは、 |
|
重房(しげふさ)は、義経殿に、 |
| 「抑(そもそ)も若君をば何と御計(おんばか)らひ候ふべき」 |
|
「ところで、なぜ若君をお取り計らいになったのですか」 |
| と申しければ、 |
|
と言うと、 |
| 「鎌倉まで具足(ぐそく)し奉るに及(およ)ばず。汝(なんぢ)これにてともかくも相計(あひはか)らへ」 |
|
「鎌倉まで連れてゆくまでもないからだ。おまえ、ここで好きにせよ」 |
| と宣ひければ、重房宿所に帰りて、二人の女房共に申しけるは、 |
|
と言われたので、重房は屋敷(やしき)に帰って、二人の女房たちに、 |
| 「大臣殿は明日鎌倉へ下向候ふ。重房も御供(おんとも)に罷(まか)り下り候ふ間、緒方三郎惟義が手へ渡し参らせ候ふべし。さらば疾(と)う疾(と)う召され候へ」 |
|
「宗盛殿は明日、鎌倉へ下向(げこう)される。私も供として下るから、緒方三郎惟義(おかたのさぶろうただよし)に預けてほしい。すぐにでもお願いしたい」 |
| とて御車寄(おんくるまよ)せたりければ、若君は、 |
|
と車を寄せると、若君は、 |
| 「また昨日のやうに父の御許(おんもと)へか」 |
|
「また昨日のように父上のところへ行くんだね」 |
| とて斜(なな)めならず嬉しげに思したるこそいとほしけれ。二人の女房も一つ車に乗りてぞ出でにける。六条を東へ遣つて行く。 |
|
と、かわいそうに、とても嬉(うれ)しそうに思っておられた。二人の女房も同じ車に乗って出て行った。車は六条を東へ向かう。 |
| 「あはれこれは怪(あや)しきものかな」 |
|
「これはどうも様子がおかしい」 |
| と肝魂(きもたま)を消して見るところに、ややあつて、兵共(つはものども)五六十騎がほど喚(をめ)いて河原の中へうち出でたり。やがて車を遣(や)り留(とど)め、 |
|
と不安になっているところに、少しして、兵たち五・六十騎が叫びながら河原の中へ現れた。すぐに車を止め、 |
| 「若君下りさせ給へ」 |
|
「若君(わかぎみ)、お降りください」 |
| とて敷皮敷いて据(す)え奉(たてまつ)る。若君世にも心細げに思して |
|
と、敷皮(しきがわ)を敷(し)いた。若君は世にも心細げに思われ、 |
| 「我をば何方(いづち)へ具(ぐ)して行かんとはするぞ」 |
|
「私をどこへ連れていくつもりだ」 |
| と宣へば、二人の女房共、とかうの御返事にも及ばず、声をばかりにぞ喚(をめ)き叫(さけ)ぶ。重房が郎等(ろうどう)太刀(たち)を引き側(そば)めて、左の方より若君の御後(おんうしろ)に立ち廻(まわ)り、既(すで)に斬(き)り奉らんとしけるを、若君見付け給ひて、幾(いく)ほど遁(のが)るべき事のやうに急ぎ乳母(めのと)の懐(ふところ)の内へぞ逃げ入らせ給ひける。二人の女房共、若君を抱え参らせて、 |
|
と言われると、二人の女房たちは、なんの返事もできず、声を限りに叫んだ。重房の郎等(ろうどう)が太刀(たち)を構え、左の方から若君の背後に立ち回り、まさに斬(き)ろうとしたとき、若君はそれをご覧になって、少しでも逃(のが)れようと、慌(あわ)てて乳母(めのと)の懐(ふところ)の内へ逃(に)げ込(こ)まれた。二人の女房たちは若君を抱(かか)えて、 |
| 「ただ我々を失ひ給へ」 |
|
「私たちを殺してください」 |
| とて天に仰ぎ地に伏して泣き悲しめどもかひぞなき。ややあつて、重房涙を押(お)さへて申しけるは、 |
|
と天を仰(あお)ぎ地に伏(ふ)して泣き悲しんだがどうにもならない。少しして、重房が涙をこらえて、 |
| 「今はいかにも叶(かな)はせ給ふべからず」 |
|
「もはやどうにもならないのです」 |
| とて急ぎ乳母の懐の内より若君引き出だし参らせ、腰の刀にて押し伏(ふ)せてつひに首をぞ馘(か)いてける。 |
|
と急いで乳母の懐(ふところ)の内より若君を引きずり出し、押さえつけると、腰の刀でついに首を刎(は)ねた。 |
| 「首をば判官(ほうがん)に見せん」 |
|
「首を義経殿に見せよう」 |
| とて取つて行く。二人の女房共、徒跣(かちはだし)にて追つ付き、 |
|
と持っていった。二人の女房たちは裸足(はだし)で追いつき、 |
| 「何か苦しう候ふべき。御首をば賜(たまわ)って御孝養(おんけうやう)をし参らせ候はん」 |
|
「どうかお願いです。御首(おんくび)をいただいて、供養(くよう)をさせてください」 |
| と申しければ、判官情ある人にて、 |
|
と言われると、義経殿は情(なさ)けある人なので、 |
| 「尤(もっと)もさるべし。疾(と)う疾(と)う」 |
|
「そうだろうとも。さあ早く」 |
| とて賜(た)びにけり。二人の女房共斜(なな)めならずに悦(よろこ)び、これを取つて懐(ふところ)に引き入れて、京の方へ帰るとぞ見えし。その後五六日して、桂川に女房二人身を投げたりといふ事ありけり。一人(いちにん)幼き人の首を懐に入れて沈みたりしはこの若君の乳母の女房にてぞありける。今一人骸(むくろ)を抱いて沈みたりしは介錯(かいしやく)の女房なり。乳母が思ひ切るはせめていかがせん、介錯の女房さへ身を投げけるこそ有難(ありがた)けれ。 |
|
と与えられた。二人の女房たちはとても喜び、首を受け取って懐(ふところ)に引き入れ、京の方へ帰るように見えた。その後五・六日して、女房が二人、桂川(かつらがわ)に身を投げたという事件があった。幼い人の首を懐に入れて沈(しず)んでいた一人は、この若君の乳母(めのと)の女房であった。もう一人、骸(むくろ)を抱いて沈んでいたのは付き添(そ)いの女房であった。乳母が殉(じゅん)ずるのはともかく、付き添いの女房まで身を投げたというのは珍(めずら)しい。 |