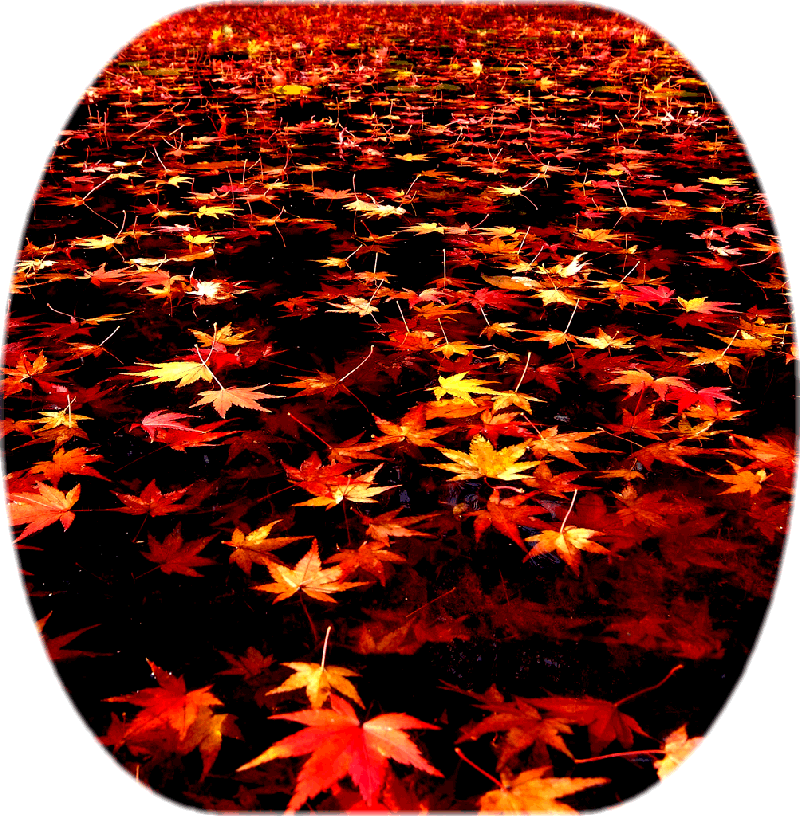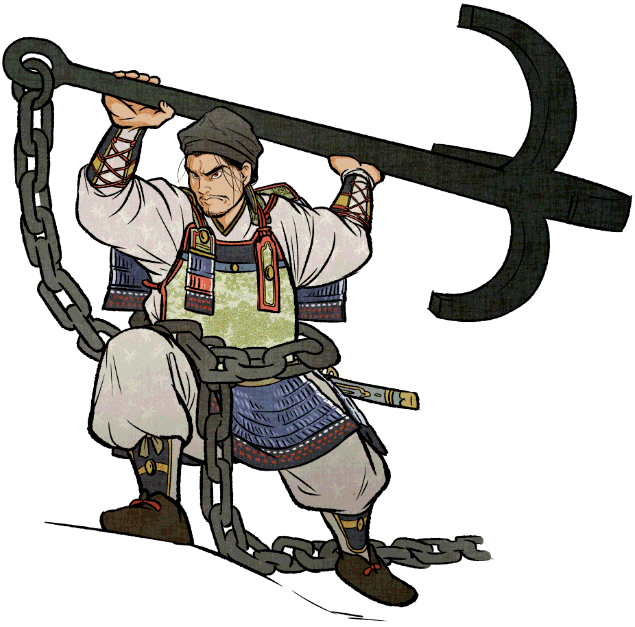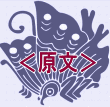
新中納言知盛卿は |
|

新中納言知盛(しんちゅうなごんとももり)殿は |
| 「見るべきほどの事は見つ。今は何をか期すべき」 |
|
「見届(みとど)けるべきことはすべて見た。もう何も思い残すことはない」 |
| とて乳母子の伊賀平内左衛門家長を召(め)して、 |
|
と、乳母子(めのとご)の伊賀平内左衛門家長(いがのへいないざえもんいえなが)を呼び、 |
| 「日比(ひごろ)の契約(けいやく)をば違へまじきか」 |
|
「日頃(ひごろ)の約束は破(やぶ)らないつもりか」 |
| と宣へば、 |
|
と言われると、 |
| 「さる事候ふ」 |
|
「もちろんです」 |
| とて中納言にも鎧二領着せ奉り、我が身も鎧二領着て、手に手を取り組み、一所(いつしよ)に海にぞ入り給ふ。これを見て二十余人の侍共、後続いて海にぞ沈みける。されどもその中に、越中次郎兵衛、上総五郎兵衛、悪七兵衛、飛騨四郎兵衛は何としてかは遁(のが)れたりけん、其処(そこ)をもつひに落ちにけり。 |
|
と、知盛殿にも鎧(よろい)を二領(にりょう)着せ、自分も鎧を二領着て、手に手を取って一緒(いっしょ)に入水(じゅすい)した。これを見て二十余人の侍たちも続いて海に沈んでいった。しかしそんな中、越中次郎兵衛盛嗣(えっちゅうのじろうびょうえもりつぎ)殿、上総五郎兵衛(かずさのごろえびょうえ)・伊藤忠光(いとうのただみつ)、悪七兵衛(あくしちびょうえ)・伊藤景清(いとうのかげきよ)、飛騨四郎兵衛(ひだのしろうびょうえ)・伊藤景高(いとうのかげたか)は、なんとかして逃れようと、そこもついに逃(に)げ延(の)びた。 |
| 海上には赤旗赤標(あかはたあかじるし)切り捨て、かなぐり捨てたりければ、龍田川の紅葉葉を嵐の吹き散らしたるに異(こと)ならず。汀(みぎは)に寄する白波は薄紅にぞ成りにける。主もなき空(むな)しき舟は潮に引かれ風に任せて、何方(いづく)を指すともなく揺られ行くこそ悲しけれ。 |
|
海上(かいじょう)に赤旗・赤印(あかじるし)を切り捨て、かなぐり捨てると、龍田川(たったがわ)の紅葉葉(もみじば)を嵐(あらし)の吹き散らしたがごとくであった。水際(みぎわ)に寄せる白波は薄紅(うすぐれない)に染(そ)まった。主(ぬし)のいないうつろ舟は、潮(しお)に引かれ風に任せて、もの悲しくどこを目指すともなく揺(ゆ)れて行く。 |
| 生捕には前内大臣宗盛公、平大納言時忠、右衛門督清宗、内蔵頭信基、讃岐中将時実、大臣殿の八歳の若君、兵部少輔雅明、僧には二位僧都専親、法勝寺執行能円、中納言律師仲快、経誦坊阿闍梨融円、侍には源大夫判官季貞、摂津判官盛澄、橘内左衛門季康、藤内左衛門信康、阿波民部父子、以上三十八人なり。菊池次郎高直、原田大夫種直は、軍以前より年来の郎等引き具して、甲を脱ぎ、弓の弦を外いて降人に参る。 |
|
生(い)け捕(ど)りには、前内大臣宗盛(さきのないだいじんむねもり)殿、平大納言時忠(へいだいなごんときただ)殿、右衛門督清宗(うえもんのかみきよむね)殿、内蔵頭信基(くらのかみののぶもと)殿、讃岐中将時実(さぬきのちゅうじょうときざね)殿、宗盛殿の八歳の若君、兵部少輔(ひょうぶのしょう)・藤原尹明(ふじわらのまさあきら)、僧には、二位僧都(にいのそうず)・専親(せんしん)、法勝寺執行(ほっしようじのしゅぎょう)・能円(のうえん)、中納言律師(ちゅうなごんのりっし)・仲快(ちゅうかい)、経誦坊阿闍梨(きょうじゅぼうのあじゃり)・融円(ゆうえん)、侍には、源大夫判官季貞(げんだいふのほうがんすえさだ)、摂津判官盛澄(つのほうがんもりずみ)、橘内左衛門季康(きちないざえもんすえやす)、藤内左衛門信康(とうないざえもんのぶやす)、阿波民部(あわのみんぶ)・田口成良(たぐちのなりよし)・教能(のりよし)父子、以上三十八人であった。菊池次郎高直(きくちのじろうたかなお)と原田大夫種直(はらだのたいふたねなお)は合戦以前から長年の郎等(ろうどう)を連れて、兜(かぶと)を脱ぎ、弓の弦(つる)を外して降人(こうにん)となった。 |
| 女房達には、女院、北政所、臈御方、帥典侍殿、大納言典侍殿、治部卿局、以下四十三人とぞ聞えし。元暦二年の春の暮れ、いかなる年月にや、一人海底に沈み、百官波上に浮かぶらん。国母官女(こくもくわんぢよ)は東夷西戎(とういせいじゆう)の手に随(したが)ひ、臣下卿相(しんかけいしやう)は数万の軍旅(ぐんりよ)に捕はれて旧里(きうり)へ帰り、或(ある)いは朱買臣が錦を着ざる事を嘆き、或いは王昭君が胡国に赴く恨みもかくやとぞ悲しび合はれける。 |
|
女房たちには、建礼門院(けんれいもんいん)殿、北政所(きたのまんどころ)・完子(さだこ)殿、義経(よしつね)殿の異父妹・廊の御方(ろうのおんかた)、帥典侍(そつのすけ)・領子(りょうこ)殿、重盛(しげもり)殿の北の方・大納言典侍(だいなごんのすけ)殿、知盛(とももり)殿の北の方・治部卿局(しじぶきょうのつぼね)をはじめ四十三人であったという。元暦(げんりゃく)二年の春の暮れ、どういう年月で、一人が海底に沈み、百官が波上(はじょう)に浮かぶことになったのであろうか。帝の母・建礼門院と官女は東方西方の野蛮人(やばんじん)に従い、家臣や公卿(くぎょう)は数万の軍勢に囚(とら)われて故郷の都へ帰ったときは、漢の朱買臣(しゅばいしん)が故郷に錦(にしき)を飾(かざ)れなかったことを嘆(なげ)いたり、漢の王昭君(おうしょうくん)が胡国(ここく)に赴(おもむ)いたことを恨(うら)んだときもこんなふうかと思われるほど悲しみ合われた。 |
| 四月三日、九郎大夫判官義経、源八広綱を以(もつ)て院御所(ゐんのごしよ)へ奏聞(そうもん)せられけれるは、 |
|
四月三日、義経殿は、源八広綱(げんぱちひろつな)を使者に院の御所へ向かわせ |
| 「去んぬる三月二十四日の卯の刻に、豊前国田浦門司関、長門国壇浦赤間関にて平家を攻め滅ぼし、内侍所(ないしどころ)、璽(しるし)の御箱(おんばこ)、事故(ことゆゑ)なう都へ還(かへ)し入れ奉るべき」 |
|
「去る三月二十四日の卯(う)の刻(こく)に、豊前国田浦門司関(ぶぜんのくにたのうらもじがせき)、長門国壇浦赤間関(ながとのくにだんのうらあかまがせき)で平家を攻め滅ぼしましたので、八咫鏡(やたのかがみ)と八尺瓊曲玉(やさかにのまがたま)を無事都へ返還(へんかん)します」 |
| 由(よし)奏聞(そうもん)せられたりければ、法皇大きに御感(ぎよかん)ありけり。公卿も殿上人も笑壺(ゑつぼ)に入らせおはします。広綱を御前の御坪(おつぼ)へ召して、合戦の次第(しだい)を委(くわ)しう御尋(おんたづ)ねあつて、御感(ぎよかん)のあまりに当座(とうざ)に広綱を左兵衛尉にぞ成されける。 |
|
と奏聞(そうもん)すると、法皇は感動された。公卿(くぎょう)も殿上人(てんじょうびと)もおおいに喜ばれた。広綱を御前の庭へ召して、合戦の様子を詳(くわ)しく尋ねられ、感心のあまりにその場で広綱を左兵衛尉(さひょうえのじょう)に任じられた。 |
| 同じき五日、北面に候ひける藤判官信盛を召して、 |
|
同・五日、北面武士の藤判官信盛(とうほうがんのぶもり)を召して、 |
| 「内侍所、璽の御箱一定(いちぢやう)還(か)り入らせ給ふか見て参れ」 |
|
「八咫鏡と八尺瓊曲玉がたしかに返還(へんかん)されたか確かめてまいれ」 |
| とて西国へ遣(つか)はさる。院の御馬賜はつて、宿所へも帰らず、鞭を挙げて西を指してぞ馳せ下る。 |
|
と西国へ遣わされた。院の御馬を賜(たまわ)って、家へも帰らず、鞭(むち)を上げて西を目指して馳(は)せ下った。 |
| さるほどに九郎大夫判官義経、平氏男女(へいじなんによ)の生捕共(いけどりども)相具(あいぐ)して上られけるが、同じき十四日播磨国明石浦にぞ着かれける。名を得たる浦なれば、更けゆくままに月冴え上り、秋の空にも劣らず。 |
|
さて、義経殿は、平家の男女の捕虜(ほりょ)たちを引き連れて京へ向かわれたが、同・十四日、播磨国明石(はりまのくにあかし)の浦に到着した。名の知られた浦で、更(ふ)けゆくままに月は冴(さ)えわたり、秋の空にも劣(おと)らない。 |
| 女房達は差し集(つど)ひて、 |
|
女房たちは集まって、 |
| 「一年(ひととせ)これを通りしに、さすがかくは無かりしものを」 |
|
「先年、ここを通ったときには、まさかこんなことになるとは思ってもみなかったのに」 |
| と忍音(しのびね)に泣きぞ合はれける。帥典侍殿はいと心に思ひ残せる事もおはせざりけるが、涙に床も浮くばかりなり。つくづくと月を眺め給ひて、 |
|
と皆忍(しの)び泣かれた。大納言典侍殿は深く心に思い出されることもあって、涙で床(とこ)が浮くほどであった。しみじみと月を眺(なが)められてこう詠(よ)まれた。 |
| ながむればぬるる袂に宿(やど)りけり月よ雲井(くもゐ)のものがたりせよ |
|
眺めれば、涙に濡(ぬ)れる袂(たもと)に映る月よ、宮中の物語をしておくれ |
| 治部卿局 |
|
治部卿局殿 |
| 雲の上に見しにかはらぬ月影のすむにつけても物ぞかなしき |
|
宮中で見たのと変わらぬ月影(つきかげ)が、すむにつけてももの悲しい |
| 大納言典侍局 |
|
重衡殿の北の方・大納言典侍・輔子(すけこ)殿 |
| 我身(わがみ)こそあかしの浦に旅ねせめおなじ波にもやどる月かな |
|
私の身も、あかしの浦の旅寝(たびね)だろうけれど、同じ浦の波に月も宿ることでしょう |
| 判官も武士なれども、 |
|
義経殿も武人であったが、 |
| 「さこそ各(おのおの)の昔恋しう物悲しうもやおはすらん」 |
|
「みんなさぞかし昔のことを恋しく物悲しく思っておられるのだろう」 |
| と身に染みて哀れにぞ思はれける。 |
|
としみじみ感じられ、哀(あは)れに思われた。 |
| 同じき二十五日、内侍所(ないしどころ)、璽(しるし)の御箱(おんばこ)、鳥羽に着かせ給ふと聞えしかば、御迎(おんむかへ)に参らせ給ふ。公卿には勘解由小路中納言経房卿、検非違使別当左衛門督実家、高倉宰相中将泰通、権右中弁兼忠、左衛門権佐親雅、榎並中将公時、但馬少将教能、武士には伊豆蔵人大夫頼兼、石川判官代能兼、左衛門尉有綱とぞ聞えし。その夜の子の刻に、内侍所、璽の御箱、太政官庁に入らせおはします。宝剣(ほうけん)は失せにけり。神璽(しんし)は海上に浮かみたるを片岡太郎経春が取り上げ奉りたりけるとかや。 |
|
同・二十五日、八咫鏡(やたのかがみ)と八尺瓊曲玉(やさかにのまがたま)が鳥羽(とば)に到着したというので、お迎えに参上した。公卿には、勘解由小路中納言経房(かでのこうじのちゅうなごんつねふさ)殿、検非違使別当(けびいしべっとう)・左衛門督実家(さえもんのかみさねいえ)殿、高倉宰相中将泰通(たかくらのさいしょうのちゅうじょうやすみち)殿、権右中弁兼忠(ごんのうちゅうべんかねただ)殿、左衛門権佐親雅(さえもんのごんのすけちかまさ)殿、榎並中将公時(えなみのちゅうじょうきんとき)殿、但馬少将教能(たじまのしょうしょうのりよし)殿、武士に、は伊豆蔵人大夫(いずのくらんどのたいふ)・源頼兼(みなもとのよりかね)、石川判官代能兼(いしかわのほうがんだいよしかね)、左衛門尉(さえもんのじょう)・源有綱(みなもとのありつな)であったという。その夜の子(ね)の刻(こく)に、八咫鏡と八尺瓊曲玉が太政官庁(だじょうかんのちょう)にお入りになった。天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)はなくなってしまった。八咫鏡は海上に浮かんでいたのを片岡太郎経春(かたおかのたろうつねはる)が取り上げ奉ったという。 |