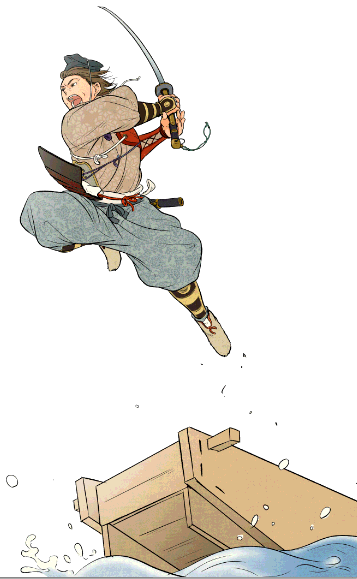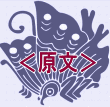
女院はこの有様(ありさま)を見参らせ給ひて、今はかうとや思し召されけん、御硯、御焼石、左右の御懐(おんふところ)に入れて海へ入らせ給ひける。渡辺党源五馬允眤小舟をつつと漕ぎ寄せて、御髪を熊手に懸(か)けて引き上げ奉る。女房達、 |
|

建礼門院(けんれいもんいん)殿はこの様子をご覧になり、もはやこれまでと思われたか、御硯(おんすずり)と御焼石(おんやきいし)を左右の懐(ふところ)に入れて海に入られた。渡辺党(わたなべとう)の源五馬允眤(げんごうまのじょうむつる)は小舟をつっと漕(こ)ぎ寄せて、御髪(おんぐし)を熊手(くまで)に掛(か)けて引き上げた。女房たちは、 |
| 「それは女院にて渡(わた)らせ給ふぞ。過ち仕るな」 |
|
「それは建礼門院殿です。過(あやま)ちなさいますな」 |
| と申されたりければ、判官に申して、急ぎ御所の御舟(おんふね)へ遷(うつ)し奉(たてまつ)る。大納言典侍局は、内侍所(ないしどころ)の御唐櫃(おんからうと)を脇(わき)に挟(はさ)んで海へ入らんとし給ひけるが、袴の裾を舷(ふなばた)に射付けられて、蹴纏(けまと)ひ倒れ給ひけるを武者共取り留め奉る。その御唐櫃の鎖を捩(ね)ぢ切り、御蓋(おんふた)を既(すで)に開かんとす。忽(たちま)ちに目眩(めく)れ鼻血垂(た)る。 |
|
と言われたので、義経殿に願い出て、急いで御所の舟にお移しした。大納言典侍殿(だいなごんのすけどの)は、八咫鏡(やたのかがみ)が安置された唐櫃(からびつ)を脇(わき)に抱えて海へ入ろうとされたが、袴(はかま)の裾(すそ)を船縁(ふなべり)に射付けられて、足が絡(から)まって倒れたところを武者たちが抱(だ)き留(とど)めた。その唐櫃の鎖(じょう)をねじ切り、蓋(ふた)を開こうとする。たちまち目がくらみ鼻血が垂(た)れた。 |
| 平大納言時忠卿は生捕(いけどり)にせられておはしけるが、この由(よし)を見奉つて、 |
|
平大納言時忠(へいだいなごんときただ)殿は生(い)け捕(ど)りされていたが、その様子を見て、 |
| 「それは内侍所の渡らせ給へば、凡夫は見奉(みたてまつ)らぬものぞ」 |
|
「それは八咫鏡(やたのかがみ)だ、凡夫(ぼんぷ)が見てはならぬ物だ」 |
| と宣へば、兵共皆逃げ去りぬ。その後、時忠卿、判官に申し合はせて、元の如く絡げ納め奉る。 |
|
と言われると、兵たちは皆逃げ去った。その後、時忠殿は義経殿と相談して、元のように唐櫃に紐(ひも)をかけて納めた。 |
| さるほどに、門脇平中納言教盛、修理大夫経盛兄弟手に手取り組み、鎧の上に碇を負うて海に沈(しず)み給ひける。小松新三位中将資盛、同少将有盛、従弟左馬頭行盛も手に手を取り組み一所で海にぞ入り給ふ。人々はかやうにし給へども、大臣殿父子はさもし給はず。舷(ふなばた)に立ち出でて、四方(しほう)きつと見廻(みまわ)しておはしければ、平家の侍共(さぶらひども)あまりの心憂(こころう)さに傍(わき)をつつと走り通るやうにて、まづ大臣殿を海へかはと突(つ)き入れ奉る。これを見て、右衛門督(うえもんのかみ)やがて続いて飛び給ひぬ。人々は重き鎧の上へまた重き物を負うたり抱いたりして入ればこそ沈め、この人親子はさもし給はず、憖(なまじい)に水練(すいれん)の上手にておはしければ、大臣殿は、 |
|
さて、門脇平中納言教盛(かどわきのへいちゅうなごんのりもり)殿と修理大夫経盛殿(しゅうりのだいぶつねもり)兄弟は手に手を取って、鎧(よろい)の上から碇(いかり)を背負い、海に沈まれた。小松新三位中将資盛(こまつのしんざんみのちゅうじょうすけもり)殿、同・少将有盛(しょうしょうありもり)殿、従弟(いとこ)・左馬頭行盛(さまのかみゆきもり)殿も手に手を取って共に海に入られた。人々はこのように入水(じゅすい)されたが、宗盛(むねもり)殿・清宗(きよむね)殿父子にそのような様子はなかった。船端に出て、四方を見回しておられたので、平家の侍たちはあまりの情(なさ)けなさに、そばをさっと駆(か)け抜けるようにして、まず宗盛殿を海へざぶっと突(つ)き落とした。これを見て、清宗殿すぐに続いて飛び込まれた。人々は重い鎧の上にまた重い物を背負ったり抱いたりして入水したが、この親子はそのようなこともなさらず、なまじ泳ぎが上手だったので、宗盛殿は、 |
| 「右衛門督沈まば我も沈まん。助からば我も共に助らん」 |
|
「清宗が沈んだらおれも沈もう。助かったらおれも共に助かろう」 |
| と思ひ、目と目をきつと見交はして、彼方此方(かなたこなた)へ泳ぎ歩き給ひけるを、伊勢三郎義盛小舟をつと漕ぎ寄せ、まづ右衛門督を熊手に懸(か)けて引き上げ奉る。大臣殿、いとど沈(しず)みもやり給はざつしを一所(いっしょ)で取り奉つてけり。御乳母子飛騨三郎左衛門景経この由(よし)を見奉つて、 |
|
と思い、互いを見交わしながら、あちらこちらへ泳ぎ歩かれているところを、伊勢三郎義盛(いせのさぶろうよしもり)が小舟をさっと漕(こ)ぎ寄せ、まず清宗殿を熊手に掛(か)けて引き上げた。宗盛殿が、少しも沈(しず)みもせずにいたのを、一緒(いっしょ)に引き上げた。乳母子(めのとご)の飛騨三郎左衛門(ひだのさぶろうざえもん)・伊藤景経(いとうかげつね)がこの様子を見て、 |
| 「我が君(きみ)取り奉るは何者ぞや」 |
|
「我が殿を引き上げたのは何者だ」 |
| とて義盛が舟に押し並べて乗り移り、太刀を抜いて打つてかかる。義盛が童(わらは)、主(しゆう)を討たせじと中に隔(へだ)たり、三郎左衛門に打つてかかる。三郎左衛門が打つ太刀に義盛が童、甲(かぶと)の真向(まっかう)打ち割られ、二の刀に首打ち落さる。義盛なほ危なう見えけるを、隣の舟より堀弥太郎親経、よつ引いてひやうと放つ。三郎左衛門内甲を射させて怯(ひる)む処(ところ)に、義盛が舟に押し並べて乗り移り、三郎左衛門に組んで伏(ふ)す。堀が郎等(ろうどう)主(しゆう)に続いて乗り移り、三郎左衛門が鎧(よろひ)の草摺引き上げて、柄も拳も通れ通れと三刀刺(さ)いて首を取る。大臣殿は生捕(いけどり)にせられておはしけるが、乳母子(めのとご)の前にてかやうになるを見給ひていかばかりの事をか思はれけん。 |
|
と、義盛の舟に押(お)し並べて乗り移り、太刀(たち)を抜(ぬ)いて斬(き)りかかった。義盛の童子(どうじ)が、主(しゅう)を討(う)たすまいと間に割って入り、景経に斬(き)りかかった。景経の振(ふ)る太刀(たち)に義盛の童子は兜(かぶと)を真っ正面から打ち割られ、二の太刀で首を打ち落された。義盛はなおも危(あや)うく見えたので、隣(となり)の舟から堀弥太郎親経(ほりのやたろうちかつね)が、弓を引き絞(しぼ)ってひゅっと射た。景経が内兜を射られて怯(ひる)んだところに、義盛が舟を添(そ)わせて乗り移り、景経を組み伏(ふ)せた。堀親経の郎等(ろうどう)が主に続いて乗り移り、景経の鎧の草摺(くさずり)を引き上げて、柄(つか)も拳(こぶし)も突(つ)き抜(ぬ)けんばかりに三太刀(みたち)刺(さ)し込(こ)んで首を取った。宗盛殿は生け捕りになっておられたが、景経が目の前でこのようになるのをご覧になり、どれほどのことを思われたであろうか。 |
| 凡(およ)そ能登殿の矢先(やさき)に廻(まわ)る者こそなかりけれ。今日を最後とや思はれけん、赤地の錦の直垂に唐綾威の鎧着て、鍬形打つたる甲の緒を締め、厳物作(いかものづく)りの大太刀を帯び、二十四差いたる切斑の矢負ひ、重籐の弓持つて、差し詰(つ)め引き詰め散々に射ければ、者共(ものども)多く手負ひ射殺さる。矢種(やだね)皆尽(みなつ)きければ、大太刀、大長刀左右に持つて、散々に薙(な)いで廻(まわ)り給ふ。 |
|
教経殿の矢面(やおもて)に立つ者はいなかった。今日が最後と思われたか、赤地の錦(にしき)の直垂(ひたたれ)に唐綾威(からあやおどし)の鎧(よろい)を着、鍬形(くわがた)の飾(かざ)りをつけた兜(かぶと)の緒(お)を締(し)め、厳(いか)めしい作りの大太刀(おおだち)を佩(は)き、二十四筋差した切斑(きりふ)の矢を背負い、重籐(しげどう)の弓を持って、次々に矢をつがえてさんざんに射ると、者どもは深手(ふかで)を負わされ射殺された。矢が尽(つ)きてしまったので、大太刀や大長刀(おおなぎなた)を左右に持って激(はげ)しく薙(な)ぎ回られた。 |
| 新中納言知盛卿、能登殿の許へ使者を立て、 |
|
新中納言知盛殿は、教経殿のところへ使者を送り、 |
| 「いたう罪(つみ)な作り給ひそ。さりとてはよき敵かは」 |
|
「あまり罪作(つみつく)りなことはなさるな。それとも、よい敵(かたき)を見つけられたか」 |
| と宣へば、 |
|
と言われると、 |
| 「さては大将軍に組めごさんなれ」 |
|
「さては大将軍(たいしょうぐん)と組めということか」 |
| とて打物(うちもの)茎短(くきみじ)かに取り持つて、艫舳(ともへさき)に散々に薙(な)いで廻(まわ)り給ふ。されども判官を見知(みしり)給はねば、物具(もののぐ)のよき武者をば判官かと目を懸(か)けて飛んで懸(か)かる。いかがはし給ひたりけん、判官の舟に乗り当たり、あはやと目を懸けて飛んで懸かる。判官叶(かな)はじとや思はれけん、長刀をば脇に掻(か)い挟(はさ)み、御方(みかた)の舟の二丈ばかり退(しりぞ)いたりけるに、ゆらりと飛び乗り給ひぬ。能登殿早業や劣られたりけん、やがて続いても飛び給はず。 |
|
と、太刀を短く持って、舟の上を激(はげ)しく薙(な)ぎ回られた。しかし義経殿の顔を知らないので、よい甲冑(かっちゅう)をまとっている武者を義経殿かと目がけて飛びかかる。うまい具合に義経殿の舟に乗り当たり、こいつかと目がけてとびかかった。義経殿はまずいと思ってか、長刀(なぎなた)を脇(わき)に挟(はさ)んで、二丈(にじょう)ほど離(はな)れた味方の舟に、ぴょんと飛び移られた。教経殿は早業(はやわざ)では劣(おと)るので、続いて飛び移ったりはされなかった。 |
| 能登殿今はかうとや思はれけん、大太刀(おほたち)大長刀(おほなぎなた)をも海へ投げ入れ、甲(かぶと)も脱いで捨てられけり。鎧の袖、草摺をもかなぐり捨て、胴ばかり着て、大童になつて、大手を広げて立たれたる。凡(およ)そ辺(あたり)を払つてぞ見えし。能登殿大音声(だいおんじやう)を揚(あ)げて、 |
|
教経殿はもはやこれまでと思われたか、大太刀や大長刀も海へ投げ入れ、兜(かぶと)も脱(ぬ)いで捨てられた。鎧(よろい)の袖(そで)や草摺(くさずり)もかなぐり捨て、胴(どう)だけを着けて、大童(おおわらわ)になり、大きく両手を広げて立たれた。辺(あた)りの者を寄せつけない雰囲気(ふんいき)があった。教経殿は大声を張り上げて、 |
| 「我と思はん者共(ものども)は寄つて教経組んで生捕(いけどり)にせよ。鎌倉へ下り、兵衛佐(ひょうえのすけ)にもの一詞(ひとことば)云はんと思ふなり。寄れや寄れ」 |
|
「我こそはと思う者はここに来て、おれと組み合って生(い)け捕(どり)にしろ。鎌倉へ下り、頼朝に一言言いたいことがあるさあ。かかってこい」 |
| と宣へども、寄る者一人もなかりけり。ここに土佐国の住人安芸郷を知行しける安芸大領実康が子に安芸太郎実光とて、凡(およ)そ二十人が力現(ちからあらわ)したる大力(だいぢから)の剛(かう)の者、我に劣(おと)らぬ郎等(ろうどう)一人(いちにん)具(ぐ)したりけり。弟の次郎も普通には勝れたる兵なり。 |
|
と言われたが、迫(せま)る者は一人もいなかった。ここに、土佐国(とさのくに)の住人で安芸国(あきのくに)を知行(ちこう)する安芸大領実康(あきのだいりょうさねやす)の子の、二十人力ほどの勇猛(ゆうもう)な者・安芸太郎実光(あきのたろうさねみつ)が、自分に劣(おと)らぬ郎等(ろうどう)を一人連れてきた。弟の次郎実俊(じろうさねとし)も人並み以上に勝(すぐ)れた兵であった。 |
| 安芸太郎能登殿を見奉(みたてま)つて、 |
|
安芸実光は教経殿を見て、 |
| 「心猛(こころたけ)うましますとも、何ほどの事をかおはすべき。たとひ長十丈の鬼なりとも、我等三人が掴(かこ)み付いたらんに、などか従(したが)へ奉らさではあるるべき。いざや組み奉らん」 |
|
「勇猛(ゆうもう)なようですが、たいしたことはありますまい。たとえ背丈(せたけ)が十丈(じゅうじょう)の鬼であろうと、我ら三人がつかみかかれば、必ず屈伏(くっぷく)させてやる。勝負だ」 |
| とて能登殿の舟に押(お)し並べて乗り移り、太刀の鋒(きつさき)を調(ととの)へて一面(いちめん)に打つて懸(か)かる。能登殿まづ真先(まつさき)に進んだる安芸太郎が郎等(ろうどう)をば裾(すそ)を合はせて海へどうと蹴入(けい)れ給ふ。続いて懸(か)かる安芸太郎をば弓手(ゆんで)の脇に掻(か)い挟(はさ)み、弟の次郎をば馬手(めて)の脇に取つて挟み、一締め締めて、 |
|
と、教経殿の舟を添(そ)わせて乗り移り、太刀の切っ先を揃(そろ)えて一気に斬(き)りかかった。教経殿はまず真っ先に突(つ)っ込(こ)んできた実光の郎等(ろうどう)と裾(すそ)を合わせて海へどうと蹴(け)り入れた。続いてかかってきた実光を左の脇(わき)に抱(かか)え、弟の実俊を右の脇に抱えて、一締(ひとし)め締め上げ、 |
| 「いざうれ己等(おのれら)、さらば死出の山の供せよ」 |
|
「さあおまえら、死出(しで)の旅路の供(とも)をしろ」 |
| とて生年二十六にて海へつつとぞ入り給ふ。 |
|
と言うと、生年二十六歳で、海へざぶんと飛び込んだ。 |