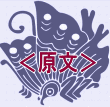
さるほどに、源氏の兵共(つはものども)平家の舟に乗り移り乗り移り、水主、梶取共、或(ある)いは射殺され、或いは斬り殺されて、舟を直すに及ばず、舟底に皆倒れ臥(ふ)しにけり。新中納言知盛卿小舟に乗り、急ぎ御所の御舟へ参らせ給ひて、 |
|

さて、源氏の兵たちが平家の舟に乗り移ってきて、水主(すいしゅ)、梶取(かんどり)たちは射殺され斬(き)り殺されて、舟を立て直すことができず、舟底に皆倒れてしまった。新中納言知盛(しんちゅうなごんとももり)殿は小舟に乗り、急いで御座舟(ござぶね)に移られ、 |
| 「世の中は今はかうと覚え候へ。見苦しき物をば海へ入れて、舟の掃除(そうじ)召(め)され候へ」 |
|
「もはやこのような状況です。見苦しい物は海へ捨てて、舟をきれいにしてください」 |
| とて掃いたり拭(ぬぐ)うたり、塵拾ひ、艫舳(ともへ)に走り廻(まわ)つて、手づから掃除(さうぢ)し給ひけり。女房達、 |
|
と、掃(は)いたり拭(ふ)いたり、塵(ちり)を拾ったり、甲板(かんぱん)を走り回って、自ら掃除をなさった。女房たちは、 |
| 「中納言殿、さて軍(いくさ)のやうはいかにや、いかに」 |
|
「知盛殿、今、合戦はどうなっているのですか」 |
| と問ひ給へば、 |
|
と尋ねられると、 |
| 「珍しき東男をこそ御覧ぜられ候はんずらめ」 |
|
「珍(めずら)しい東男(あずまおとこ)がご覧(らん)になれますよ」 |
| とてからからと笑はれければ、女房達、 |
|
と、からからと笑われたので、女房たちは、 |
| 「何条(なんでう)の只今(ただいま)の戯(たわぶ)れぞや」 |
|
「まったくなんのお戯(たわむ)れですか」 |
| とて声々に喚(をめ)き叫(さけ)び給ひけり。 |
|
と声々に大声で叱(しか)られた。 |
| 二位殿は日比(ひごろ)より思ひ設(もう)け給へる事なれば、鈍色の二衣うち被き、練袴の稜高(かどたか)く取り、神璽を脇に挟み、宝剣を腰に差いて、主上(しゅじょう)を抱き参らせて、 |
|
八条二位(はちじょうにい)殿は日頃からお考えになっていたことなので、鈍色(にぶいろ)の二衣(ふたつぎぬ)を被(かぶ)り、練袴(ねりばかま)の股立(ももだ)ちを高くつかみ、神璽(しんし)を脇(わき)に挟(はさ)み、宝剣(ほうけん)を腰(こし)に差し、安徳天皇(あんとくてんのう)をお抱(だ)きになり、 |
| 「我が身は女なりとも、敵の手にはかかるまじ。主上(しゆしやう)の御供(おんとも)に参るなり。御志(おんこころざし)思ひ給はん人々は急ぎ続き給へや」 |
|
「私は女であっても、敵(かたき)の手にはかかりません。帝(みかど)のお供に参ります。同じ思いの人々は急いで私について来なさい」 |
| とて静々と舷(ふなばた)へぞ歩み出でられける。主上は今年八歳にぞ成らせおはしませども、御年(おんとし)のほどよりは遥(はる)かにねびさせ給ひて、御容(おんかたち)美しう、辺も照り輝くばかりなり。御髪(おんぐし)黒う優々(ゆうゆう)として御背中(おんせなか)過ぎさせ給ひけり。あきれたる御有様(おんありさま)にて、 |
|
と静々と舳先(へさき)へ歩み出られた。安徳天皇は今年八歳におなりだが、お歳(とし)よりはるかに大人びておられ、お姿も美しく、辺(あた)りが照り輝くほどであった。背中あたりまで伸(の)びた黒髪(くろかみ)が美しく揺(ゆ)れておられる。驚(おどろ)かれた様子で、 |
| 「抑(そもそ)も我をば何方(いづち)へ具(ぐ)して行かんとはするぞ」 |
|
「朕(ちん)をどこへ連れていくつもりだ」 |
| と仰せければ、二位殿、稚(いとけな)き君に向かひ参らせ涙をはらはらと流いて、 |
|
と仰(おお)せになると、八条二位殿は、幼い帝に顔を向け、涙をほろほろと流して、 |
| 「君は未だ知ろし召(め)され候はずや。前世の十善戒行の御力(おんちから)によつて、今万乗(ばんじよう)の主(あるじ)とは生れさせ給へども、悪縁に引かれて御運既(すで)に尽(つ)きさせ候ひぬ。まづ東(ひんがし)に向かはせ給ひて伊勢大神宮に御暇申させおはしまし、その後西に向かはせ給ひて西方浄土の来迎(らいかう)に預(あづ)からんと誓(ちか)はせおはしまし、御念仏候ふべし。この国は粟散辺土(そくさんへんぢ)とて心憂(こころう)き境(さかひ)なれば、極楽浄土とてめでたき所へ具(ぐ)し参らせ候ふぞ」 |
|
「まだご存じないのですね。前世(ぜんせ)で行った十善(じゅうぜん)・戒行(かいぎょう)の力によって、今天皇としてお生まれになりましたが、悪縁(あくえん)に引かれて、その御運はすっかり消えてしまったのです。まず東をお向きになり、伊勢大神宮にお暇(いとま)を申し上げ、その後西をお向きになり、西方浄土(さいほうじょうど)のお迎(むか)えをお願いし、お念仏を唱(とな)えなさいませ。この国は小さな辺境(へんきょう)の地で、憩(いこ)えるところではありませんから、極楽浄土(ごくらくじょうど)という幸せなところへお連れするのです」 |
| と泣く泣く掻(か)き口説(くど)き申されければ、山鳩色の御衣に鬢結はせ給ひて、御涙(おんなみだ)に溺(おぼ)れ、小さう美しき御手(おんて)を合はせてまづ東に向かはせ給ひて、伊勢大神宮に御暇申させ給ひ、その後西に向かはせ給ひて御念仏ありしかば、二位殿やがて抱き参らせて、 |
|
と泣く泣く説得されると、山鳩色(やまばといろ)の御衣(ぎょい)に鬢(びんずら)を結われ、涙ながらに小さく美しい手をお合わせになり、まず東を向かれ、伊勢大神宮にお暇申し上げ、その後西を向かれて念仏を唱えられると、八条二位殿はすぐにお抱えになって、 |
| 「波の底にも都の候ふぞ」 |
|
「波の底にも都がございます」 |
| と慰め参らせて千尋(ちいろ)の底にぞ沈み給ふ。悲しきかな、無常の春の風忽(たちま)ちに花の御姿を散らし、情無(なさけな)きかな、分段(ぶんだん)の荒き波(なみ)玉体(ぎよくたい)を沈(しず)め奉る。殿(てん)をば長生(ちやうせい)と名付けて、長き栖(すみか)と定め、門をば不老(ふらう)と号して老いせぬ扉鎖(とざし)とは書きたれども、未だ十歳の内にして底の水屑(みくづ)と成らせおはします。十善帝位(じふぜんていゐ)の御果報(おんくわほう)申すも中々(なかなか)おろかなり。雲上の龍降(くだ)つて、海底の魚と成り給ふ。大梵高台(だいぼんかうだい)の閣(かく)の上(うへ)、釈提喜見(しやくだいきけん)の宮の内(うち)、古(いにしへ)は槐門棘路(くわいもんきよくろ)の間に九族(きうぞく)を靡(なび)かし、今は舟の内、波の下(した)にて御命を一時(いつし)に滅ぼし給ふこそ悲しけれ。 |
|
と慰(なぐ)められて、遥(はる)かな海の底に沈まれた。悲しいことに、無常(むじょう)の春の風はたちまち花の御姿(おんすがた)を散らし、痛ましくも、生死を分ける荒い波が帝のお体を沈めた。御殿(ごてん)を長生殿(ちょうせいでん)と名づけ、長く暮(く)らせる住まいと決めて、門を不老門(ふろうもん)と名づけ老(お)いぬ門戸(もんこ)と書いたが、まだ十歳に満たないうちに海の藻屑(もくず)となられたのだった。天子の位に即(つ)かれながら、ごのようなご運であるとは、言葉が見つからない。雲上(うんじょう)の龍(りゅう)が下(くだ)ってきて、海底の魚になられた。梵天(ぼんてん)がお住まいの高い楼閣(ろうかく)の上か、帝釈天(たいしゃくてん)がお住まいの喜見城(きけんじょう)にお住まいになり、昔は大臣や公卿(くぎょう)に囲まれて平家一門を従えておられた方が、今は舟の内、波の下で御命(おんいのち)を一瞬(いっしゅん)で滅(ほろ)ぼされたのは悲しいことである。 |

