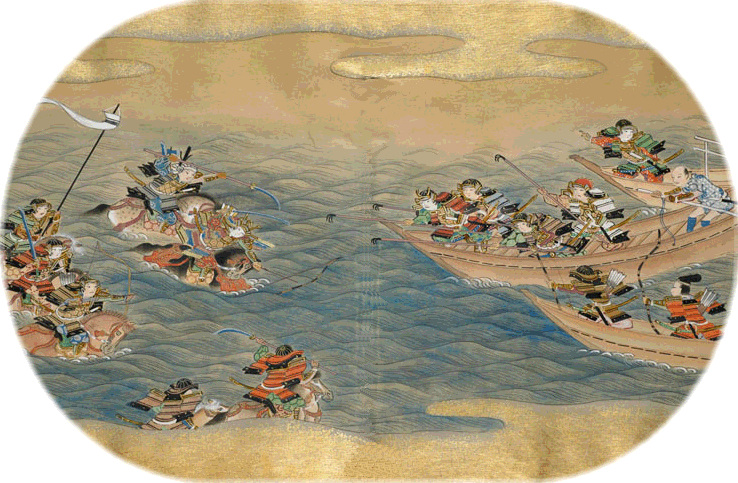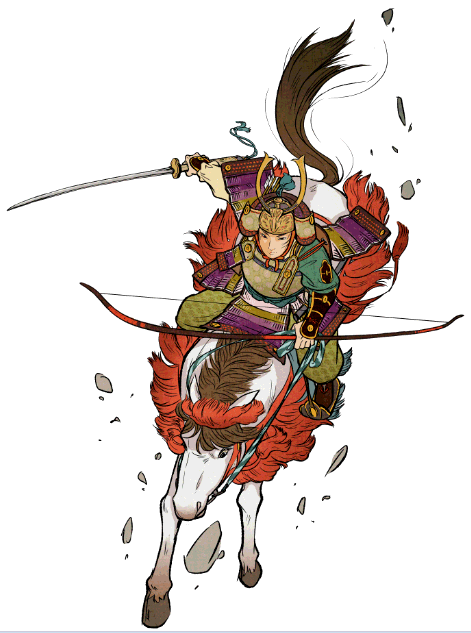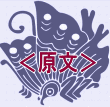
あまり感に堪へずと思しくて、平家の方より、年の齢五十ばかりなる男の黒革威の鎧着たるが、白柄の長刀杖につき、扇立てたる所に立ちて舞ひ締(し)めたり。伊勢三郎義盛、与一が後ろに歩ませ寄せて、 |
|

あまりの素晴らしさに感極(かんきわ)まってか、平家方から、黒革威(くろかわおどし)の鎧(よろい)を着た五十歳ほどの男が、白柄(しらえ)の長刀(なぎなた)を杖(つえ)にし、扇を立てたところに立って舞を始めた。伊勢三郎義盛(いせのさぶろうよしもり)は、宗隆(むねたか)の後ろに馬を歩ませ、 |
| 「御諚(ごぢやう)であるぞ、これをもまた仕れ」 |
|
「ご命令だ、あの男も殺せ」 |
| と云ひければ、与一今度は中差(なかざし)取つて番(つが)ひ、よつ引いて、舞ひ澄(す)ましたる男の真只中(まっただなか)をひやうつばと射て、舟底へ真倒(さかさま)に射倒す。 |
|
と言ったので、宗隆は、今度は鋭い矢尻(やじり)の矢を取ってつがえると、引き絞(しぼ)り、舞っている男の心臓めがけて、ひゅうばっと射て、舟底へ真っさかさまに射倒した。 |
| 「ああ射たり」 |
|
「射抜いた」 |
| と云ふ人もあり、嫌々(いやいや) |
|
と言う人もあり、逆に |
| 「情なし」 |
|
「非情(ひじょう)だ」 |
| と云ふ者も多かりけり。平家の方には音もせず。源氏の方にはまた箙を叩いて響(どよ)めきけり。平家これを本意(ほい)なしとや思ひけん、弓持つて一人、楯突いて一人、長刀持つて一人、武者三人渚(なぎさ)に上がり、 |
|
と言う人も多かった。平家方では音もしない。源氏方では、また箙(えびら)を叩(たた)いて歓声(かんせい)を上げた。平家はこれを残念に思い、弓を持って一人、楯(たて)を突(つ)いて一人、長刀(なぎなた)を持って一人、武者三人が上陸し、 |
| 「源氏、此処(ここ)を寄せよや」 |
|
「源氏、来い」 |
| とぞ招きける。判官、 |
|
と招いた。義経殿が、 |
| 「安(やす)からぬ事なり。馬強(うまづよ)ならん若党共(わかとうども)、馳(は)せ寄つて蹴散らせ」 |
|
「生意気(なまいき)な。騎馬上手の若者ども、駆(か)け込んで蹴散(けち)らせ」 |
| と宣へば、武蔵国の住人美尾屋四郎、同藤七、同十郎、上野国の住人丹生四郎、信濃国の住人木曾中次、五騎連れて喚(をめ)いて駆(か)く。まづ楯の陰より塗箆(ぬりの)に黒保呂矧(くろぼろは)いだる大の矢を持つて、真先に進んだる美尾屋十郎が馬の左の鞅尽(むながいづ)くしに弭ゆはず)の隠(かく)るるほどにぞ射籠(いこ)うだる。屏風を返すやうに馬はどうと倒るれば、主(ぬし)は弓手(ゆんで)の脚(あし)を越え、馬手(めて)の方(かた)へ下(お)り立ちて、やがて太刀をぞ抜いたりける。 |
|
と命じられると、武蔵国(むさしのくに)の住人・美尾屋四郎(みおのやしろう)、同(おなじき)・藤七(とうじち)、同・十郎、上野国(こうづけのくに)の住人・丹生四郎(にうのしろう)、信濃国(しななのくに)の住人・木曽中次(きそのちゅうじ)の五騎が連れ立ち、雄叫(おたけ)びを上げて向かった。まず盾(たて)の陰(かげ)から、褐色(かっしょく)に塗(ぬ)った漆(うるし)の矢柄(やがら)に黒保呂(くろぼろ)の羽根をつけた大きな矢を持って、真っ先に進んだ美尾屋十郎の馬の左の胸に筈(はず)が埋(う)まるほど射こめた。屏風(びょうぶ)を返すように馬がどうっと倒れると、十郎は馬の左脚(ひだりあし)を飛び越(こ)え、右側へ下り立って、すぐに太刀(たち)を抜いた。 |
| また楯(たて)の陰(かげ)より長刀持つたる男一人うち振つて懸(か)かりければ、美尾屋十郎小太刀、大長刀に叶(かな)はじとや思ひけん、掻(か)き伏(ふ)いて逃げければ、やがて続いて追つ駆(しころ)を掴(つか)まうとす。掴まれじと逃ぐる。三度掴み外いて四度の度にむずと掴む。暫(しば)しぞ堪(たま)つて見えし。鉢付(はちつ)けの板よりふつと引き切つてぞ逃げたりける。残り四騎は馬を惜(お)しうで駆(か)けず、見物してぞ居たりける。美尾屋十郎は御方(みかた)の馬の陰へ逃げ入つて息継(いきつ)ぎ居たり。敵(かたき)は追うて来ず、白柄(しらえ)の長刀杖(なぎなたつゑ)につき、甲(かぶと)の錣(しころ)を高く差し上げ、大音声(だいおんじやう)を揚(あ)げて、 |
|
また盾(たて)の陰(かげ)から長刀(なぎなた)を持った男が一人振(ふ)りかかってくると、十郎は小太刀(こだち)、大長刀(おおなぎなた)には敵(かな)わないと思ってか、地に伏(ふ)すようにして逃げると、すぐに続いて追いかけてきた。長刀で薙(な)ごうとするのかと見れば、そうではなく、長刀を左の脇に挟(は)み、右手を差し延べて、十郎の兜(かぶと)の錣(しころ)をつかもうとする。つかまるまいと逃げる。三度つかみ損(そこ)ねて四度目にむんずとつかんだ。しばらくは揉(も)み合っているようであった。すると鉢付(はちつ)けの板からぶっつり切って逃げてしまった。残り四騎は馬を惜(お)しんで駆(か)けつけず、見物していた。美尾屋十郎は味方の馬の陰(かげ)へ逃げ込んで呼吸を整えていた。敵(かたき)は追ってこず、白柄(しらえ)の長刀を杖(つえ)にして、兜(かぶと)の錣(しころ)を高く差し上げ、大声を張り上げて、 |
| 「遠からん者は音にも聞け。近からん人は目にも見給へ。これこそ京童部(きょうわらんべ)の喚(よ)ぶなる上総悪七兵衛景清よ」 |
|
「遠くにいる者よく聞け。近くにいる者はとくと見よ。我こそ京童部(きょうわらべ)が噂(うわさ)する上総悪七兵衛(かずさのあくしちびょうえ)・伊藤景清(かげきよ)だ」 |
| と名乗り捨ててぞ退(しりぞ)きにける。 |
|
と名乗り捨てて退却(たいきゃく)した。 |
| 平家これに少し心地(ここち)を直(なほ)いて、 |
|
平家はこれに少し気を取り直して、 |
| 「悪七兵衛討たすな、者共(ものども)、景清討たすな、続けや」 |
|
「悪七兵衛を討(う)たすな、者ども、景清を討たすな、続け」 |
| とて二百余人渚に上がり、楯を雌鳥羽に築(つ)き並べて、 |
|
と二百余人が渚(なぎさ)に上がり、盾(たて)を雌鳥羽(めんどりば)に並べ、 |
| 「源氏此処(ここ)を寄せや」 |
|
「源氏、来い」 |
| とぞ招いたる。判官、 |
|
と招いた。義経殿は、 |
| 「安からぬ事なり」 |
|
「生意気な」 |
| とて伊勢三郎義盛、奥州佐藤四郎兵衛忠信を前に立て、後藤兵衛父子、金子兄弟、弓手馬手(ゆんでめて)に立て、田代冠者を後ろになして、判官八十余騎喚いて先を駆(か)け給へば、平家の方には馬に乗つたる勢は少なし、大略(たいりやく)徒武者なりければ、馬に当てられじとや思ひけん、引き退き、皆舟にぞ乗りにける。楯(たて)は算(さん)を散らしたるやうに散々(さむざむ)に懸(か)けなされぬ。 |
|
と、伊勢三郎義盛、奥州(おうしゅう)の佐藤四郎兵衛忠信(さとうしろうびょうえただのぶ)を前に立て、後藤兵衛実基(ごとうびょうえさねもと)・基清(もときよ)父子、金子十郎家忠(かねこじゅうろういえただ)・与一親範(よいちちかのり)兄弟を左右に立て、田代冠者信綱(たしろのかんじゃのぶつな)を後ろにして、義経殿は八十余騎で雄叫(おたけ)びを上げながら先駆(さきが)けられると、平家方では馬に乗った勢は少なく、ほとんどが徒武者(かちむしゃ)だったので、馬に蹴(け)られまいと思ってか、退却(たいきゃく)しながら、皆舟に乗った。盾(たて)は数え棒(ぼう)を散らしたようにちりぢりに蹴散(けち)らされた。 |
| 源氏勝ちに乗つて、馬の太腹浸かるほどにうち入れうち入れ攻め戦ふ。舟の内より熊手を持つて判官の甲の錣にからりからりと二三度しけれども、御方(みかた)の兵共(つはものども)、太刀長刀の鋒(きつさき)にて打ち払い打ち払い攻め戦ひけるが、判官いかがはし給ひたりけん、弓を懸(か)け落されぬ。俯(ふ)して鞭を持つて掻(か)き寄せ、取らん取らんとし給へば、御方の兵共、 |
|
源氏は勝ちに乗じて、馬の太腹(ふとはら)が浸(つ)かるほど海に入って攻め戦った。舟の内から熊手(くまで)を持ってきて、義経殿の兜(かぶと)の錣(しころ)にからりからりと二・三度ひっかけようとしたとき、味方の兵たちが、太刀や長刀の切っ先で払いのけながら攻め戦うと、義経殿はどうしたことか、弓を落とされた。うつ伏(ぶ)して鞭(むち)でかき寄せながら、拾おうとしてなさるので、味方の兵たちは、 |
| 「ただ捨てさせ給へ、捨てさせ給へ」 |
|
「お捨てなされ、お捨てなされ」 |
| と云ひけれども、つひに取つて笑(わら)うてぞ帰られける。大人共(おとなども)は皆爪弾(みなつまはじ)きをして、 |
|
と言ったが、ついに拾い上げると、笑って帰られた。大人たちは皆あきれて、 |
| 「たとひ千疋万疋(せんびきまんびき)に代へさせ給ふべき御(おん)たらしなりと申すとも、いかでか御命(おんいのち)には替へさせ給ふべきか」 |
|
「たとえ千頭万頭の価値がある弓であろうと、命には代えられません」 |
| と申しければ、判官、 |
|
と言うと、義経殿は、 |
| 「弓の惜しさに取らばこそ。義経が弓といはば、二人しても張り、もしは三人しても張り、伯父為朝が弓のやうならば態(わざと)も落して取らすべし。わう弱(じやく)たる弓を敵(かたき)の取り持つて、『これこそ源氏の大将軍九郎義経が弓よ』など嘲哢(てうろう)せられんが口惜(くちお)しさに、命に替へて取つたるぞかし」 |
|
「弓が惜(お)しくて拾ったのではない。義経の弓といえば二・三人張り、伯父(おじ)・為朝(ためとも)の弓のだというのならば、わざと落として拾わせもするだろう。弱々しい弓を敵が拾って、『これが源氏の大将軍・九郎義経の弓だ』などとあざ笑われるのが悔(くや)しいから、命に代えても拾ったのだ」 |
| と宣へば、皆またこれをぞ感じける。 |
|
と言われると、皆またこれに感動した。 |
| 一日戦ひ暮らし、夜に入りければ、平家の舟は沖に浮かび、源氏は陸(くが)にうち上がつて、牟礼高松の中なる野山に陣をぞ取つたりける。源氏の兵共(つはものども)はこの三日が間は寝ざりけり。一昨日渡辺福島を出で、大波に揺られて微睡(まどろ)まず、昨日阿波国勝浦に着いて軍(いくさ)し、終夜(よもすがら)中山越え、今日また一日戦ひ暮らしたりければ、人も馬も皆疲れ果てて、或(ある)いは甲(かぶと)を枕(まくら)にし、或いは鎧の袖、箙など枕として、前後も知らずぞ臥(ふ)しにける。されどもその中に判官と伊勢三郎は寝ざりけり。判官は高き所にうち上がつて、敵(かたき)や寄すると遠見(とほみ)し給へば、伊勢三郎は窪(くぼ)き所に隠(かく)れ居て、敵寄せばまづ馬の太腹射んとて待ちかけたり。 |
|
一日戦い暮らし、夜に入ると、平家の舟は沖(おき)に浮かび、源氏は陸に上がって、牟礼(むれ)・高松の奥にある野山に陣を構えた。源氏の兵たちはこの三日間一睡(いっすい)もしなかった。一昨日は渡辺・福島を出て、大波に揺(ゆ)られてまどろむこともなく、昨日は阿波国(あわのくに)勝浦(かつうら)に着いて合戦し、夜を徹(てっ)して中山を越え、今日また一日戦い暮(く)らしたので、人も馬も皆疲れ果て、兜(かぶと)を枕(まくら)にしたり、鎧(よろい)の袖(そで)や箙(えびら)など枕にして、前後不覚(ぜんごふかく)になって眠(ねむ)った。しかし、そんな中でも義経殿と伊勢三郎義盛は眠らなかった。義経殿は高いところに上がって、敵の来襲(らいしゅう)を見張られ、伊勢三郎義盛はくぼんだところに隠(かく)れて、敵が攻めてきたら馬の太腹(ふとはら)を射てやろうと待ち構えていた。 |
| 平家の方には能登(のと)殿を大将軍としてその夜夜討(ようち)に寄すべかりしを、越中次郎兵衛盛嗣と海老次郎が先陣を争ふほどに、その夜も空しく明けにけり。寄せたれば源氏なじかはあらまし。寄せざりけるこそせめての運の極(きわ)めなれ。 |
|
平家方では教経(のりつね)殿を大将軍として、その晩夜襲(やしゅう)をかけようと、越中次郎兵衛盛嗣(えっちゅうのじろうびょうえもりつぎ)と海老次郎盛方(えみのじろうもりかた)が先陣(せんじん)を争ったので、その夜も空しく明けてしまった。攻めていたら源氏はひとたまりもなかったであろう。攻めなかったとはよくよく運に見放されたものである。 |