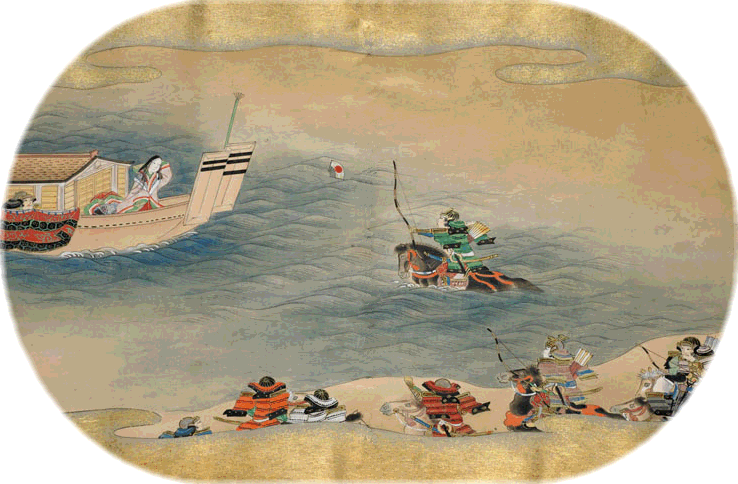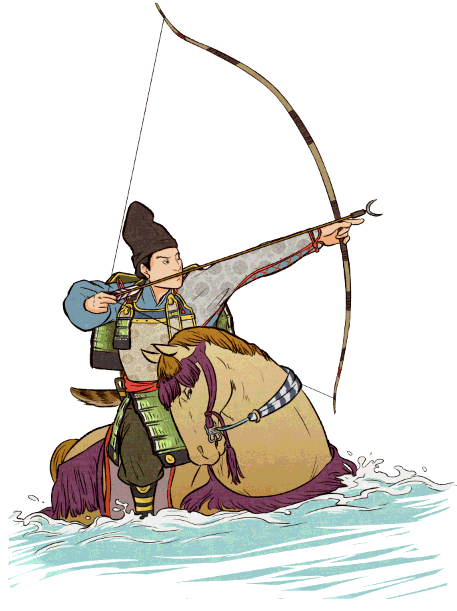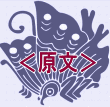
さるほどに、阿波、讃岐に平家を背いて源氏を待ちける者共、彼処(あそこ)の峰此処(ここ)の洞(ほら)より十四五騎二十騎、うち連れうち連れ馳せ来たるほどに、判官(ほうがん)ほどなく三百余騎になり給ひぬ。 |
|

さて、阿波(あわ)・讃岐(さぬき)で平家に背(そむ)いて源氏を待っていた者たちは、あちこちの峰(みね)や洞穴(ほらあな)から十四・五騎、二十騎と連れ立って馳(は)せ集まったので、義経殿はほどなく三百余騎になった。 |
| 「今日は日暮れぬ、勝負を決すべからず」 |
|
「今日は日が暮れた、勝負を決するのはやめだ」 |
| とて引き退(しりぞ)く処(ところ)に、ここに沖の方より尋常(じんじやう)に飾(かざ)つたる小舟一艘、汀(みぎわ)へ向かひて漕(こ)ぎ寄せさせ、渚(なぎさ)より七八段ばかりにもなりしかば、舟を横様(よこさま)に成す。あれはいかにと見るほどに、舟の内より年齢(としよはひ)十八九ばかりなる女房の柳の五衣に紅の袴着たるが皆紅(みなぐれなゐ)の扇の日出(ひい)だいたるを舟の船枻(せがい)に挟(はさ)み立て、陸(くが)へ向かつてぞ招(まね)きける。 |
|
と退却(たいきゃく)するところへ、沖(おき)の方から立派(りっぱ)に飾(かざ)った小舟が一艘(そう)、波打ち際(ぎわ)へ向かって近づき、渚(なぎさ)から七・八段(たん)ほどの距離になると、舟を横に向けた。あれはなんだと見ていると、柳(やなぎ)の五衣(いつつぎぬ)に紅(くれない)の袴(はかま)を着た十八・九歳ほどの女房が舟の中から出てきて、すべてに日の出が描かれた紅の扇(おうぎ)を舟の横板に挟(はさ)んで立て、陸に向かって手招(てまね)きをした。 |
| 判官、後藤兵衛実基を召して、 |
|
義経殿は、後藤兵衛実基(ごとうびょうえさねもと)を呼び、 |
| 「あれはいかに」 |
|
「なんだあれは」 |
| と宣へば、 |
|
と尋ねられると、 |
| 「射よとにこそ候ふめれ。但(ただ)し大将軍の矢面に進んで傾城(けいせい)を御覧(ごらん)ぜられん処(ところ)を手練(てた)れに狙(ねろ)うて射落せとの謀(はかりごと)と存じ候へ。さりながらも、扇をば射させらるべうもや候ふらん」 |
|
「射てみろという意味でしょう。おそらく、大将軍が矢面(やおもて)に進んで美女をご覧になっているところを、手練(てた)れに狙撃(そげき)させるための罠(わな)と思われます。しかし、扇は射るべきかと」 |
| と申しければ、判官 |
|
と答えたので、義経殿が |
| 「御方(みかた)に射つべき仁(じん)は誰(たれ)かある」 |
|
「味方にあれを射ることができる者はいるか」 |
| と宣へば、 |
|
と尋ねられると、 |
| 「上手共(じやうずども)多う候ふ中に下野国の住人那須太郎資高が子に与一宗高こそ小兵(こひやう)では候へども手は利(き)いて候ふ」 |
|
「大勢の名手の中でも、下野国(しもつけのくに)の住人・那須太郎資高(なすのたろうすけたか)の子・与一宗隆(よいちむねたか)は、小柄(こがら)ですが、腕は確かです」 |
| と申す。判官、 |
|
と言った。義経殿が、 |
| 「証拠いかに」 |
|
「証拠(しょうこ)はあるか」 |
| と宣へば、 |
|
と言われると、 |
| 「さん候ふ、翔鳥などを争うて三つに二つは必ず射落し候ふ」 |
|
「はい、飛ぶ鳥を狙(ねら)えば、三つに二つは必ず射落します」 |
| と申しければ、判官、 |
|
と言われると、義経殿は、 |
| 「さらば与一召(め)せ」 |
|
「では与一を呼べ」 |
| とて召されけり。 |
|
と呼ばれた。 |
| 与一その比(ころ)は未だ二十ばかりの男なり。褐に赤地の錦を以(もっ)て壬衽彩(おほくびはたそでいろ)へたる直垂に萌黄威の鎧着て、足白の太刀を帯き、二十四差いたる切斑の矢負ひ、薄切斑に鷹の羽割り合はせて矧(は)いだりける〔※ぬた〕目の鏑(かぶら)をぞ差し添(そ)へたる。滋籐の弓脇に挟み、甲(かぶと)をば脱ぎ高紐に懸(か)け、判官の御前(おんまへ)に畏(かしこま)る。 |
|
与一宗隆は当時、まだ二十歳ほどの男であった。褐(かち)に赤地の錦(にしき)で、襟(えり)や袖(そで)を彩(いろど)った直垂(ひたたれ)に萌黄威(もえぎおどし)の鎧(よろい)を着、足白(あしじろ)の太刀(たち)を帯(は)き、二十四筋差した切斑(きりふ)の矢を背負い、薄切斑(うすぎりふ)に鷹(たか)の羽根を割り合わせて作った〔※注 ぬた〕目の鏑矢(かぶらや)を差していた。滋籐(しげどう)の弓を脇(わき)に挟(はさ)み、兜(かぶと)を脱いで高紐(たかひも)に掛(か)け、義経殿の前にかしこまった。 |
| 判官、 |
|
義経殿が、 |
| 「いかに宗高、あの扇の真中射て敵に見物せさせよかし」 |
|
「さて宗隆、あの扇の真ん中を射て、敵に見せてやれ」 |
| と宣へば、与一、 |
|
と命じられると、宗隆は、 |
| 「仕(つかま)つとも存じ候はず。これを射損(いそん)ずるほどならば長き御方(みかた)の御弓箭(おんゆみや)の瑕(きず)にて候ふべし。一定(いちぢやう)仕らうずる仁(じん)に仰(おほ)せ付けらるべうもや候ふらん」 |
|
「自信はありません。射損(いそこ)ねましたら、長く味方の弓矢取りの恥(はじ)になりましょう。確実に射止められる方に仰せつけられた方がよろしいかと存じます」 |
| と申しければ、判官大きに怒つて、 |
|
と答えたので、義経殿はひどく怒(いか)って、 |
| 「今度鎌倉を立つて西国へ赴かんずる者共(ものども)は、皆義経が命を背くべからず。それに少しも子細(しさい)を存ぜん殿原(とのばら)は、これより疾(と)う疾(と)う鎌倉へ帰らるべし」 |
|
「このたび鎌倉を発って西国へ赴く者たちは、皆おれの命に背(そむ)いてはならない。それを少しも理解しない者たちは、ここからすぐに鎌倉へ帰れ」 |
| とぞ宣ひける。与一、重ねて辞せば悪(あ)しかりなんとや思ひけん、 |
|
と言われた。宗隆は、ここは重ねて断ってはまずいと思ってか、 |
| 「さ候はば、外(はづ)れんをば知り候ふまじ、御諚(ごぢやう)で候へば仕(つかま)つてこそ見候はめ」 |
|
「それでは、射止められるかどうか自信はありませんが、ご命令ですので、やるだけやってみます」 |
| とて御前を罷(まか)り立ち、黒き馬の太(ふと)う逞(たくま)しきに丸海鞘摺(まろぼやす)つたる金覆輪の鞍置いてぞ乗つたりける。弓取り直し、手綱掻(か)い繰(く)つて、汀(みぎは)へ向いてぞ歩ませける。御方(みかた)の兵共(つはものども)与一が後ろを遥(はる)かに見送りて、 |
|
と御前(おんまえ)を退(しりぞ)くと、太くたくましい黒馬に丸海鞘(まろぼや)の紋(もん)が描かれた金覆輪(きんぶくりん)の鞍(くら)を置いて乗った。弓を取り直し、手綱(たづな)をさばいて、波打(なみう)ち際(ぎわ)へと歩ませた。味方の兵たちは宗隆の背中を遥(はる)かに見送り、 |
| 「一定(いちぢやう)この若者仕つつべう存じ候ふ」 |
|
「この若者は必ず射止めるに違いない」 |
| と申しければ、判官世にも頼もしげにぞ見給ひける。 |
|
と言うと、義経殿は世にも頼(たの)もしげに見ておられた。 |
| 矢比(やごろ)少し遠かりければ、海の面一段(おもていつたん)ばかりうち入れたりけれども、なほ扇のあはひは七段ばかりもあるらんとぞ見えし。比(ころ)は二月十八日酉の刻ばかりの事なるに、折節(をりふし)北風烈(はげ)しくて、磯打(いそう)つ波も高かりけり。舟は揺り上げ揺り据(す)ゑて漂へば、扇も串(くし)に定まらず閃(ひらめ)いたり。沖には平家舟を一面に並べて見物す。陸(くが)には源氏轡(くつばみ)を並べてこれを見る。いづれもいづれも晴れならずといふ事なし。与一目を塞(ふさ)いで、 |
|
射程距離(しゃていきょり)が少し遠かったので、海の中に一段(たん)ほど入ったが、それでも扇までの間合いは七段ほどはあるように見えた。頃は二月十八日酉(とり)の刻(こく)ごろなので、折しも北風は激しくて、磯(いそ)を打つ波も高かった。舟は揺(ゆ)れに揺れて漂(ただよ)えば、扇も竿(さお)に固定されず、ひらひらと動いている。沖には平家が舟を一面に並べて見物している。陸には源氏が馬を並べてこれを見る。どちらも晴れがましい光景であった。宗隆は目を閉じると、 |
| 「南無八幡大菩薩、別しては我国の神明、日光権現、宇都宮、那須湯泉大明神、願はくはあの扇の真中射させて賜(た)ばせ給へ。射損(いそん)ずるほどならば、弓切り折り自害して人に二度(ふたたび)面(おもて)を向くべからず。今一度本国(ほんごく)へ迎へんと思(おぼ)し召(め)さば、この矢(や)外(はづ)させ給ふな」 |
|
「南無八幡大菩薩(なむはちまんだいぼさつ)、特に我が国の神明(しんめい)、日光権現(にっこうのごんげん)、宇都宮大明神(うつのみやだいみょうじん)、那須湯泉大明神(なすのゆぜんだいみょうじん)、願わくは、あの扇の真ん中射させてください。失敗したときには、弓を折って自害(じがい)し、人の前に二度と現れないつもりです。もう一度、那須へお迎(むか)えくださるならば、どうかこの矢を外(はず)させないでください」 |
| と心の内に祈念(きねん)して、目を見開いたれば、風少し吹き弱つて、扇も射よげにぞなりにけれ。与一鏑(かぶら)を取つて番(つが)ひ、よつ引いてひやうと放つ。小兵(こひやう)といふ条(じやう)、十二束三伏、弓は強し、鏑は浦響くほどに長鳴りして、過(あやま)たず扇の要際(かなめぎは)一寸ばかり置いてひいふつとぞ射切つたる。鏑は海に入りければ、扇は空へぞ揚(あ)がりける。春風に一揉み二揉み揉まれて海へさつとぞ散つたりける。皆紅(みなぐれなゐ)の扇の日出(ひい)だいたるが夕日に輝いて、白波の上に浮きぬ沈みぬ揺られけるを、沖には平家舷(ふなばた)を叩いて感じたり。陸には源氏箙(えびら)を叩いて響めきけり。 |
|
と、心の中で祈り、目を見開くと、風が少し弱まって、扇も射やすくなっていた。宗隆は鏑矢(かぶらや)を取ってつがえ、引き絞(しぼ)ってひゅっと放った。小柄(こがら)といえども、十二束(そく)三つ伏(ぶ)せ、弓の張りは強く、鏑矢は海辺に響(ひび)き渡るほどに長鳴(ながな)りして、扇の要(かなめ)のそば一寸ほどずれて確かに射切った。鏑矢は海に入り、扇は空へ舞い上がった。春風に一揉(も)み二揉み揉まれて、海にさっと散った。全面に日の出が描かれた紅の扇は夕日に輝き、白波の上に浮き沈み揺られているのを、沖の平家は舟のわきを叩(たた)いて感動していた。陸では源氏が箙(えびら)を叩いて歓声(かんせい)を上げた。 |