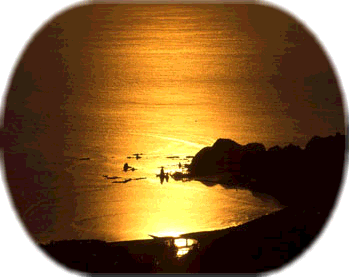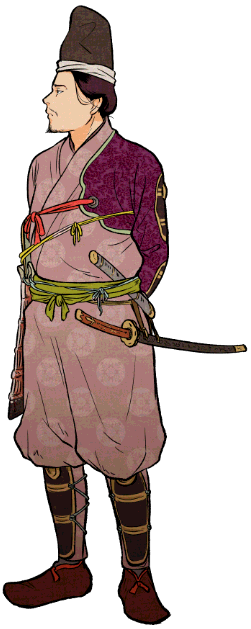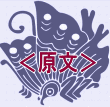
三御山の参詣、事故(ことゆゑ)なう遂げ給ひしかば、浜宮と申し奉る王子の御前(おんまへ)より一葉(いちえふ)の舟に棹(さを)ささせ、万里の蒼海に浮かび給ふ。遥かの沖に山成島といふ所あり。中将それに舟を漕ぎ寄せさせ、岸に上り、大きなる松の木を削りて名跡を書き付けらる。 |
|

熊野三山の参詣(さんけい)を無事に遂(と)げられると、浜の宮という王子社の御前から一艘(そう)の舟を出させ、広々とした青い海に万里(ばんり)の蒼海(そうかい)に漕(こ)ぎ出された。遥(はる)か沖に山成(やまなり)の島というところがあった。維盛殿はそこへ舟を漕ぎ寄せさせ、岸に上り、大きな松の木を削(けず)って名跡(めいせき)を書き付けられた。 |
| 「祖父太政大臣平朝臣清盛公、法名浄海。親父内大臣左大将重盛公、法名浄蓮。三位中将維盛、法名浄円、年二十七歳、寿永三年三月二十八日、那智の沖にて入水す」 |
|
「祖父(そぶ)・太政大臣平朝臣清盛公、法名浄海(ほうみょうじょうかい)。親父(しんぶ)・内大臣左大将重盛公、法名浄蓮(じょうれん)。三位中将維盛、法名浄円(じょうえん)、年二十七歳、寿永三年三月二十八日、那智(なち)の沖にて入水(じゅすい)する」 |
| と書き付けて、また舟に乗り、奥へぞ漕ぎ出で給ひける。思ひ切りぬる道なれども、今はの時にもなりぬれば、さすが心細う悲しからずといふ事なし。 |
|
と記し終えるとまた舟に乗り、奥へと漕ぎ出された。覚悟を決めてはいるものの、最期(さいご)の時にもなれば、やはり心細く悲しい。 |
| 比(ころ)は三月二十八日の事なれば、海路遥かに霞み渡り、哀(あは)れを催(もよほ)す類(たぐひ)かな。ただ大方(おほかた)の春だにも暮れゆく空は物憂きに、況(いはん)やこれは今を最後、只今(ただいま)限りの事なれば、さこそは心細かりけめ。沖の釣舟の波に消え入るやうに覚ゆるが、さすが沈みも果てぬを見給ふにつけても御身の上とや思はれけん。己(おの)が一行(ひとつら)引き連れて、今はと帰る雁金(かりがね)の越路(こしぢ)を指して鳴き行くも、故郷(ふるさと)へ言伝(ことづ)てせまほしく、蘇武が胡国の恨みまで、思ひ残せる隈(くま)もなし。 |
|
頃は三月二十八日のことなので、海路は遥かに霞(かす)み渡り、どことなく物悲しい。ただ例年の春でさえ暮(く)れゆく空は物憂(ものう)いのに、ましてやこれが最後、これで終わりというときなので、実に心細かったであろう。沖の釣舟(つりぶね)が波に消え入るやうに見えながら、それでも沈(しず)まないのを見られて、我が身のように思われた。自分の仲間を引き連れて、今帰ろうとして雁(かり)が北国を目指して鳴き渡るのを見て、故郷に伝言を頼めたらと、漢の蘇武(そぶ)の胡国(ここく)への恨(うら)みなどを我が身に重ね、あれこれと思うのだった。 |
| 「こはされば何事ぞや」 |
|
「これはいったいどうしたことだ」 |
| と来(こ)し方(かた)行(ゆく)く末(すゑ)の事共(ことども)を思ひ続けて給ふにも、 |
|
と、過去や未来のことを思うにつけて、 |
| 「なほ妄執(まうじふ)の尽きぬにこそ」 |
|
「まだ妄執(もうしゅう)が尽(つ)きていないのだ」 |
| と思ひ返して、西に向かつて手を合はせ、念仏し給ふ心の内にも、 |
|
と思い返しては、西に向かって手を合わせ、念仏される心の中でも、 |
| 「都には、今日を最後只今(ただいま)限りとはいかで知るべきなれば、風の便りの音信も今や今とこそ待たんずらめ」 |
|
「都では、私がこれで命を終えようとしていることなど知る由(よし)もないし、風の便りさえ今か今かと待っているだろう」 |
| と思ひければ、合掌(がつしやう)を乱(みだ)り、聖(ひじり)に向かつて宣ひけるは、 |
|
と思われると、合掌(がっしょう)が乱れてしまい、時頼入道(ときよりにゅうどう)に向かって、 |
| 「哀れ人の身に妻子といふものを持つまじかりけるものかな。今生(こんじやう)にて物を思はするのみならず、後世菩提の妨げとなりぬる事こそ口惜しけれ。かやうの事を心中(しんぢゆう)に残し置けば、あまりに罪深かかんなる間、懺悔するなり」 |
|
「ああ、人として妻子(さいし)など持つものではない。現世で心を悩(なや)ますだけでなく、後世菩提(ごせぼだい)の妨(さまた)げにもなってしまうことが口惜(くちお)しい。こんなことを心の中に残していては、あまりに罪深(つみぶか)いから、懺悔(ざんげ)する」 |
| とぞ宣ひける。 |
|
と言われた。 |
| 聖も哀れに思ひけれども、我さへ心弱くては叶(かな)はじとや思ひけん、涙を押し拭(はら)ひ、さらぬ体(てい)にもてなして、 |
|
時頼入道も哀れに思ったが、自分まで弱気ではいけないと思い、涙をぬぐい、平常心(へいじょうしん)を装(よそお)って、 |
| 「高きも賤(いや)しきも恩愛の道は思ひ切られぬ事にて候へば、まことにさこそは思し召され候ふらめ。一夜の枕を並ぶるも五百生(ごひやくしやう)の宿縁(しゆくえん)。生者必滅(しやうじやひつめつ)、会者定離(ゑしやぢやうり)は、憂(う)き世(よ)の習(なら)ひにて候ふなり。末(すゑ)の露(つゆ)、本(もと)の雫(しづく)の例(ため)しあれば、たとひ遅速(ちそく)の不同ありといふとも、後れ先立つ御別(おんわか)れ、つひに無くしてもや候ふべき。かの驪山宮の秋の夕べの契(ちぎ)りもつひには心を砕(くだ)く端(はし)となり、甘泉殿の生前(しやうぜん)の恩も終りなきにしもあらず。松子、梅生、生涯(しやうがい)の恨みあり、等覚、十地、なほ生死の掟に従ふ。たとひ君長生(ちゃうせい)の楽しみに誇り給ふとも、この恨みはつひに無くしてもや候ふべき。たとひまた百年の齢(よはひ)を持たせ給ふとも、この御別れはただ同じ事と思し召(め)さるべし。 |
|
「身分の上下にかかわらず、恩愛(おんあい)の道というのは思い切れないものですから、そう思われるのはもっともです。一夜(いちや)の枕(まくら)を共にしただけでも五百度生まれ変わる前からの縁(えん)で結ばれている。生きる者は必ず滅(ほろ)び、会う者は必ず離(はな)れるのが現世の定めです。木の葉の端の露(つゆ)が木の元の雫(しづく)となるという譬(たと)えもあるように、仮(かり)に遅い早いの差はあっても、後(おく)れるか、先立(さきだ)つか、別れは必ずやって来ます。秋の夜の驪山宮(りさんきゅう)で玄宗皇帝(げんそうこうてい)と楊貴妃(ようきひ)が交わした誓(ちか)いも心を砕(くだ)く端緒(たんしょ)となり、武帝(ぶてい)が李夫人(りふじん)の肖像(しょうぞう)を甘泉殿(かんせんでん)に据(す)えても、永遠ではありませんでした。漢の仙人(せんにん)・松子(しょうし)や梅生(ばいせい)でさえ命が尽(つ)きることを恨(うら)み、菩薩(ぼさつ)に次ぐ位の等覚(とうがく)や十地(じゅうじ)でさえ生死の掟(おきて)に従うのです。たとえ殿が長生きをして栄え誇(ほこ)られようとも、この悲しみをなくすことはできません。たとえまた百年の寿命(じゅみょう)を保たれても、この別れは、同じことだとお思いください。 |
| 第六天魔王といふ外道は欲界の六天を皆我が物と領(りやう)じて、中にもこの界の衆生の生死に離るる事を惜しみ、或いは妻となり、或いは夫となつてこれを妨げんとするに、三世の諸仏は一切衆生(いつさいしゆじやう)を一子(いつし)の如(ごと)く思し召して、かの極楽浄土の不退(ふたい)の土(ど)に勧(すす)め入れんとし給ふに、妻子といふ者が無始昿劫(むしくわうごふ)より以来、生死に輪廻(りんね)する絆(きづな)によつて仏は重う戒(いまし)め給ふ。さればとて心弱う思し召すべからず。 |
|
第六天の魔王(まおう)という外道(げどう)は、欲界(よくかい)の六天をことごとく奪(うば)い、中でも現世の衆生(しゅじょう)が仏道に入って生死のこだわりをなくすことを惜(お)しんで、あるときは妻となり、あるときは夫となってこれを妨(さまた)げようとするため、過去・現在・未来の諸仏は、すべての衆生を我が子のごとく思われ、戻ることのない極楽浄土(ごくらくじょうど)へ導こうとされているのですが、妻子というのは、いつから始まったのかわからないほど遠い昔から生死の世界を巡(めぐ)らせる絆(きずな)なので、仏は厳(きび)しく戒(いまし)めておられるのです。だからといって心細く思われることはありません。 |
| 源氏の先祖伊予入道頼義は、勅命によつて奥州の夷貞任宗任を攻め給ひし時、十二年が間に人の首を斬(き)る事一万六千、その外山野の獣、江河(こうが)の鱗(うろくづ)、その命を絶つ事幾千万といふ数を知らず。されども終焉(しゆうえん)の時、一念の菩提心を発(おこ)ししによつて往生の素懐を遂げたりとこそ承れ。 |
|
源氏の先祖・伊予入道頼義(いよのにゅうどうらいぎ)は、勅命(ちょくめい)によって奥州の夷(えびす)である安倍貞任(あべのさだとう)・宗任(むねとう)兄弟を攻められたとき、十二年の間に人の首を斬ること一万六千、そのほか山野の獣(けだもの)や、河川の魚、その命を絶つこと幾(いく)千万という数を知りません。それでも臨終(りんじゅう)において、一念の菩提心(ぼだいしん)を発したて、往生(おうじょう)の素懐(そかい)を遂(と)げたと言われています。 |
| 就中(なかんづく)御出家の功徳莫大(くどくばくたい)なれば、前世の罪障(ざいしやう)は皆滅(ほろ)び給ひぬらん。たとひ人あつて七宝塔(しつぽうたふ)を建つる事高さ三十三天に至るといふとも、一日の出家の功徳には及(およ)ぶべからず。たとひ百千歳(ひやくせんざい)の間百羅漢(ひやくらかん)を供養したる功徳も一日の出家の功徳には及ばず、とこそ説かれたり。 |
|
とりわけ御出家の功徳(くどく)はとても大きいものですから、前世の罪業(ざいごう)はすっかり消えてしまうでしょう。もし、ここにある人がいて、須弥山(しゅみせん)の頂上に届くほどの高い七宝(しっぽう)の塔(とう)建てることになっても、一日の出家の功徳には及びません。たとえ百年千年の間、百の羅漢(らかん)を供養(くよう)した功徳でも、一日の出家の功徳には及ばない、と説かれています。 |
| 罪深かりし頼義(らいぎ)も心猛(こころたけ)きが故(ゆゑ)に往生を遂(と)ぐ。御罪業(ございごふ)もましまさざらんに、などか浄土へ参り給はで候ふべき。 |
|
罪深かった源頼義(みなもとのよしより)も心をしっかり持っていたがゆえに往生の素懐を遂げました。殿は罪業もお持ちでないのですから、極楽浄土へ参らないはずがありません。 |
| その上当山権現(とうざんごんげん)は本地(ほんぢ)阿弥陀如来にてましませば、始め無三悪趣(むさんあくしゆ)の願より終り得三法忍(とくさんぽふにん)の願に至るまで、一々の誓願(せいぐわん)、衆生化度(しゆじやうけど)の願ならずといふ事なし。中にも第十八の願には、『説我得仏(せつがとくぶつ)、十方衆生(じつぱうしゆじやう)、至心信楽(ししんしんげう)、欲生我国(よくしやうがこく)、乃至十念(ないしじふねん)、若不生者(にやくふしやうじや)、不取正覚(ふしゆしやうがく)』と説かれたれば一念十念の頼みあり。 |
|
しかもこの熊野権現(くまのごんげん)は、本体は阿弥陀如来(あみだにょらい)ですから、初めの三悪道(さんあくどう)を無くす願(がん)から終わりの三種の法忍(ほうにん)を得る願に至るまで、ひとつひとつの願に、衆生(しゅじょう)を救う願でないものはありません。中でも第十八の願は、『もし自分が仏の身を得たとき、十方(じっぽう)の衆生が、心を尽(つ)くして、自分を信じ極楽に生まれようと願い、念仏を十遍(じっぺん)唱え、それでも極楽に生まれ変われない者は、正しく悟れないのである』と説かれていますから、一度でも十度でも念ずれば望みがあります。 |
| ただこの教へを深く信じて、努々(ゆめゆめ)疑ひをなすべからず。無二(むに)の懇念(こんねん)を致(いた)して、もしは一遍ももしは十遍も唱へ給ふものならば、弥陀如来、六十万億那由多恒河沙の御身を縮(つづ)め、丈六八尺の御形(おんかたち)にて観音、勢至、無数の聖衆、化仏菩薩、百重千重に囲繞(ゐねう)し、伎楽(ぎがく)詠して、只今極楽の東門を出でて来迎(らいかう)し給はんずれば、御身(おんみ)こそ蒼海(さうかい)の底に沈むと思し召さるとも、紫雲の上に登り給ふべし。成仏得脱(じやうぶつとくだつ)して悟りを開き給ひなば、娑婆(しやば)の故郷に立ち帰つて妻子を導き給はん事、還来穢国度(げんらいゑこくど)、人天(にんでん)少しも過ち給ふべからず」 |
|
ひたすらこの教えを深く信じて、ゆめゆめ疑いを持ってはなりません。二つとないほど心を込めて、もし一遍でも十遍でも唱えられたら、阿弥陀如来は、六十万億那由多恒河沙(まんおくなゆたごうがしゃ)の御身(おんみ)を縮め、丈六八尺(じょうろくはっしゃく)の御姿で、観音菩薩(かんのんぼさつ)、勢至菩薩(せいしぼさつ)、無数の聖衆(しょうじゅ)、化身した仏・菩薩らが、百重千重と取り囲み、音楽を奏(かま)で歌を詠(えい)じ、すぐにも極楽の東門を出てお出迎えされますから、たとえその身が青い海の底に沈むと思われても、紫雲(しうん)たなびく天上に登られることでしょう。成仏(じょうぶつ)し、煩悩(ぼんのう)を断ち切って解脱(げだつ)し、悟りを開かれれば、現世の故郷に帰って妻子を導かれることについては、現世に還(かえ)り来て人を救う、とありますから、疑いを持ってはなりません」 |
| 鐘打ち鳴らし念仏を勧め奉れば、中将、然(しか)るべき善知識(ぜんちしき)と思し召し、忽(たちま)ちに妄念を翻し、西に向かつて手を合はせ、高声(かうしやう)に念仏百返ばかり唱へ給ひて、 |
|
と、鐘(かね)を打ち鳴らし、念仏を勧(すす)められると、中将維盛殿は、今が真の道に赴(おもむ)く時だと思われ、すぐに妄念(もうねん)を翻(ひるがえ)し、西に向かって手を合わせ、高声に念仏百遍(ひゃっぺん)ほど唱えられ、 |
| 「南無」 |
|
「南無(なむ)」 |
| と唱ふる声と共に海へぞ飛び入り給ひける。与三兵衛、石童丸も同じう御名(みな)を唱へつつ、続いて海にぞ沈みける。 |
|
と唱える声と共に、海へ飛び込まれた。与三兵衛重景(よそうびょうえしげかげ)と石童丸(いしどうまる)も、同じように阿弥陀(あみだ)の名を唱えながら、続いて海に沈んでいった。 |