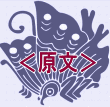
さるほどに、一谷の軍敗れにしかば、武蔵国の住人熊谷次郎直実、 |
|

(平家が)一の谷の合戦に敗れると、武蔵国(むさしのくに)の住人・熊谷次郎直実(くまがえのじろうなおざね)は |
| 「平家の君達助け舟に乗らんとて、汀(みぎは)の方へや落ち行き給ふらん。あつぱれよき大将軍に組まばや」 |
|
「平家の公達(きんだち)は助け舟に乗るために波打(なみう)ち際(ぎわ)へ落ちて行かれただろう。立派(りっぱ)な大将軍と組み合いたいものだ」 |
| と思ひ、渚(なぎさ)を指して歩まする処(ところ)に、ここに鶴縫(つるぬ)うたる直垂に萌黄匂の鎧着て、鍬形打つたる甲の緒を締め、金作の太刀を帯き、二十四差いたる切斑の矢負ひ、滋籐の弓持ち、連銭葦毛なる馬に金覆輪の鞍置いて乗つたる武者一騎、沖なる舟を目にかけ、海へさつとうち入れ、五六段ばかり泳がせける。 |
|
と思い、波打ち際を目指して馬を歩ませると、鶴(つる)を刺繍(ししゅう)した直垂(ひたたれ)に萌黄匂(もよぎにおい)の鎧を着、鍬形(くわがた)の飾(かざ)りをつけた兜(かぶと)の緒(お)を締(し)め、黄金作(こがねづくり)の太刀(たち)を佩(は)き、二十四筋差した切斑(きりふ)の矢を背負い、滋籐(しげどう)の弓を持ち、連銭葦毛(れんぜんあしげ)の馬に金覆輪(きんぶくりん)の鞍(くら)を置いて乗る武者が一騎、沖(おき)の舟を目にかけ、海へざっと乗り入れると、五六段(たん)ほど泳がせた。 |
| 熊谷、 |
|
直実は、 |
| 「あれはいかに、よき大将軍とこそ見参らせ候へ。正(まさ)なうも敵(かたき)に後ろを見せ給ふものかな。返させ給へ、返させ給へ」 |
|
「そなたは名のある大将軍とお見受けした。卑怯(ひきょう)にも敵に後ろをお見せになるのか。戻(もど)られよ、戻られよ」 |
| と扇を挙げて招きければ、招かれて取つて返し、渚に打ち上がらんとし給ふ処(ところ)に、波打際にて押し並び、むずと組んでどうと落ち、取つて押さへて首を馘(か)かんとて、内甲(うちかぶと)を押し仰けて見たりければ、年の齢十六七ばかりなるが、薄仮粧して鉄漿黒(かねぐろ)なり。我が子の小次郎が齢(よはひ)ほどにて、容顔(ようがん)まことに美麗(びれい)なりければ、何処(いづく)に刀を立つべしとも覚えず。 |
|
と扇(おうぎ)を上げて招(まね)くと、招かれて引き返し、渚(なぎさ)に上がろうとしたところに、波打ち際で馬を並べ、むんずと組んでどうと落ち、取り押さえて首を刎(は)ねようと、内兜(うちかぶと)を押し上げて見ると、薄仮粧(うすげしょう)にお歯黒(おはぐろ)を塗(ぬ)った十六・七歳ほどの少年であった。我が子の直家(なおいえ)と同じくらいの年で、実に美しい容貌(ようぼう)であったので、どこに刀を突(つ)き立ててよいかもわからない。 |
| 熊谷、 |
|
直実は、 |
| 「いかなる人にて渡らせ給ひやらん。名乗らせ給へ。助け参らせん」 |
|
「そなたはどのような御仁(ごじん)なのか。名乗られよ。お助けいたす」 |
| と申せば、 |
|
と言うと、 |
| 「汝(なんぢ)は誰(たれ)そ。名乗れ、聞かう」 |
|
「貴殿は誰か。名乗れ、聞こう」 |
| 「物その者では候はねども、武蔵国の住人熊谷次郎直実」 |
|
「物の数に入らないような者ですが、武蔵国の住人・熊谷次郎直実」 |
| と名乗り申す。 |
|
と名乗った。 |
| 「汝が為(ため)にはよい敵(かたき)ぞ。名乗らずとも首を取つて人に問へ。見知らうずるぞ」 |
|
「ならば貴殿にとって私はよい敵だ。名乗らなくても首を取って誰かに問え。知っている人がいるだろう」 |
| とぞ宣ひける。 |
|
と言われた。 |
| 熊谷、 |
|
直実は |
| 「あつぱれ大将軍や。この人一人(いちにん)討ち奉りたりとも負(ま)くべき軍(いくさ)に勝つ事はよもあらじ。また助け奉るとも勝つ軍に負くる事もよもあらじ。我が子の小次郎が薄手(うすで)負うたるをだに直実は心苦しう思ふぞかし。この殿の父、討たれ給ひぬと聞き給ひて、さこそは嘆き悲しび給はんずらめ。助け参らせん」 |
|
「見事な大将軍だ。この人ひとり討(う)ち取ったところで、負ける戦に勝つことはないだろう。また助けたところで、勝つ戦に負けることもあるまい。我が子・直家が浅手を負っただけでもおれはつらかった。この殿の父上は、我が子が討たれたと聞いたらどれほど嘆(なげ)き悲しむことだろう。助けてさしあげよう」 |
| とて後ろを顧みたりければ、土肥(とひ)、梶原(かぢはら)五十騎ばかりで出で来たり。熊谷涙をはらはらと流いて、 |
|
と後ろを振(ふ)り向くと、土肥実平(どいさねひら)と梶原景時(かじはらのかげとき)が五十騎ほどでやって来た。直実は涙をほろほろ流して、 |
| 「あれ御覧候へ。いかにもして助け参らせんとは存じ候へども、御方(みかた)の軍兵雲霞(ぐんびやううんか)の如(ごと)くに満ち満ちてよも遁(のが)れ参らせ候はじ。あはれ同じうは直実が手に懸(か)け奉つてこそ後の御孝養(おんけうやう)をも仕り候はめ」 |
|
「これをご覧(らん)なされ。なんとかしてお助けしたいのだが、味方の軍兵(ぐんびょう)が雲霞(うんか)のごとく充ち満ちて、とても逃がしてさしあげることができません。同じことなら、我が手でお討ちし、後の供養(くよう)をいたします」 |
| と申しければ、 |
|
と言うと、 |
| 「ただいかやうにも疾(はよ)う疾う首を取れ」 |
|
「なんでもいいから、すぐ首を取れ」 |
| とぞ宣ひける。 |
|
と言われた。 |
| 熊谷あまりにいとほしくて、何処(いづく)に刀を立つべしとも覚えず。目も眩(く)れ心も消え果てて、前後不覚(ぜんごふかく)に覚えけれども、さてしもあるべき事ならねば、泣く泣く首をぞ馘(か)いてける。 |
|
直実は、あまりにかわいそうで、どこに刀を突(つ)き立ててよいかもわからない。目も眩(くら)み、分別(ふんべつ)もすっかり失って、前後もわからなくなってしまったが、それどころではないので、泣く泣く首を刎(は)ねた。 |
| 「あはれ弓矢取る身ほど口惜(くちお)しかりける事はなし。武芸の家に生れずば何しに只今(ただいま)かかる憂(う)き目をば見るべき。情(なさけ)なうも討(う)ち奉つたるものかな」 |
|
「ああ、武者ほどつらいことはない。武人の家系に生まれなければ、今頃こんなつらい目に遭(あ)うことはなかったはずだ。非情(ひじょう)にも殺してしまった」 |
| と袖を顔に押し当て、さめざめとぞ泣き居たる。首を包まんとて鎧直垂を解いて見ければ、錦の袋に入れられたりける笛をぞ腰に差されたる。 |
|
と袖(そで)を顔に押し当て、さめざめと泣いていた。首を包もうと鎧直垂(よろいびたたれ)を解いて見ると、錦(にしき)の袋に入れられた笛(ふえ)が腰(こし)に差してあった。 |
| 「あないとほし。この暁(あかつき)城の内にて管絃し給ひつるは、この人々にておはしけり。当時御方(みかた)に東国の勢何万騎かあるらめども、軍(いくさ)の陣へ笛持つ人はよもあらじ。上臈(じやうらふ)はなほも優(やさ)しかりけるものを」 |
|
「なんとかわいそうな。今朝方、城郭(じょうかく)の内で管弦(かんげん)を奏(かな)でおられていたのはこの方々だったのか。そのとき我らが東国の勢(せい)は何万騎(なんまんぎ)もあっただろうが、戦陣(せんじん)に笛を持ってくる者などいないだろう。貴人(きじん)とはなんとも優雅(ゆうが)なものだ」 |
| とてこれを取つて大将軍の御見参(ごけんざん)に入れたりければ、見る人涙を流しけり。 |
|
と、これを取って大将軍義経殿にお見せすると、見る人は涙を流した。 |
| 後に聞けば、修理大夫経盛の子息大夫敦盛とて、生年(しやうねん)十七にぞ成られける。それよりしてこそ熊谷が発心の心は出来にけれ。件(くだん)の笛は、祖父忠盛、笛の上手にて鳥羽院より下し賜はられたりしを、敦盛の器量(きりやう)たるによつてこの笛をぞ持たれたりける。名をば小枝とぞ申しける。狂言綺語(きやうげんきぎよ)の理(ことわり)と云ひながら、つひに讃仏乗(さんぶつじよう)の因(いん)となるこそ哀(あは)れなれ。 |
|
後で聞くところによると、十七歳になる修理大夫経盛(しゅりのだいふつねもり)の子息・大夫敦盛(だいふあつもり)ということであった。それから直実には発心(ほっしん)の心が芽生えた。その笛は、彼の祖父・忠盛(ただもり)が笛の上手であったため鳥羽院(とばのいん)から賜(たまわ)られたのを、敦盛の腕前により、持っておられたという。笛の名は小枝(さえだ)という。狂言(きょうげん)は道理に合わないといって仏教では歌舞管弦(かぶかんげん)などは迷(まよ)いの元(もと)とするが、その笛が仏門(ぶつもん)への道となったのは考えさせられるものがある。 |

