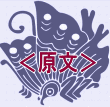
本三位中将重衡卿は生田森の副将軍にておはしけるが、その日の装束には褐(かつ)に白う黄なる糸を以(もつ)て岩に群千鳥繍(ぬ)うる直垂に紫裾濃の鎧着て、童子鹿毛といふ聞ゆる名馬に乗り給へり。乳母子の後藤兵衛盛長は滋目結の直垂に緋威の鎧着て、三位中将のさしも秘蔵(ひさう)せられたる夜目無月毛にぞ乗せられたる。主従二騎助け舟に乗らんとて、細道にかかつて落ち給ふ処(ところ)に、庄四郎高家、梶原源太景季、よい敵(かたき)と目をかけ、鞭鐙(むちあぶみ)を合はせて追ひ駆(か)け奉る。渚には助け舟共幾らもありけれども、後ろより敵は追つ駆けたり、乗るべき隙(ひま)もなかりければ、湊川、苅藻川をもうち渡り、蓮池を馬手(めて)に見て駒林を弓手(ゆんで)に成し、板宿、須磨をもうち過ぎて、西を指(さ)してぞ落ち給ふ。 |
|

本三位中将重衡(ほんざんみのちゅうしょうしげひら)殿は生田森(いくたのもり)の副将軍で、その日の装束(しょうぞく)には、深藍(ふかあい)に鮮やかな黄色の糸で岩と群千鳥(むらちどり)を刺繍(ししゅう)した直垂(ひたたれ)に紫裾濃(むらさきすそご)の鎧を着、童子鹿毛(どじかげ)という評判の名馬に乗られていた。乳母子(めのとご)の後藤兵衛盛長(ごとうびょうえもりなが)は、滋目結(しげめゆい)の直垂に緋威(ひおどし)の鎧を着、三位中将重衡殿の大切にされていた夜目無月毛(よめなしつきげ)に乗られていた。主従二騎が助け舟に乗るべく細道をたどって落ちようとされるところへ、庄四郎高家(しょうのしろうたかいえ)と梶原源太景季(かじはらげんたかげすう)が、いい敵を見つけたと、鞭(むち)を振(ふ)るい鐙(あぶみ)を蹴(け)って追いかけた。渚(なぎさ)には助け舟が何艘(なんそう)もあったが、後ろから敵が追いかけてくるので、乗っている暇(ひま)もなかったため、湊川(みなとがわ)、苅藻川(かるもがわ)をも越え、蓮池(はすのいけ)を右に見て駒林(こまのはやし)を左に見て、板宿(いたやど)、須磨(すま)も通り過ぎ、西を目指して落ち延びられた。 |
| 三位中将は童子鹿毛といふ聞ゆる名馬に乗り給ひたりければ、揉(も)み伏(ふ)せたる馬の容易(たわや)う追つ付くべしとも見えざりければ、梶原、もしやと遠矢によつ引いてひやうと放つ。三位中将の馬の三頭(さうづ)を箆深(のぶか)に射させて弱る処(ところ)に、乳母子後藤兵衛盛長は、我が馬召(め)されなん、とや思ひけん、鞭を打つてぞ逃げたりける。 |
|
三位中将重衡殿は童子鹿毛という評判の名馬に乗られていたので、疲れ果てた馬ではたやすく追いつけるとも思えず、梶原は、もしかしたらと弓を引き絞(しぼ)って遠矢(とおや)をひゅっと放った。三位中将重衡殿の馬が尻骨(しりぼね)あたりを深々と射られて弱ったところに、乳母子・後藤兵衛盛長が、自分の馬を取られてしまうかもしれないと思ってか、鞭を打って逃げてしまった。 |
| 三位中将、 |
|
三位中将重衡殿は、 |
| 「いかに盛長、我をば捨てて何処(いづく)に行くぞ。年比日比(としごろひごろ)さは契(ちぎ)らざりしものを」 |
|
「なんと盛長、おれを捨ててどこへ行くのか。長い間そのようなことをする約束はしていなかったはずだ」 |
| と宣へども、空(そら)聞かずして、鎧に付けたりける赤標共(あかじるしども)かなぐり捨てて、ただ逃げにこそ逃げたりけれ。三位中将、馬は弱る、海へさつとうち入れられけれども、其処(そこ)しも遠浅にて沈むべきやうもなかりければ、急ぎ馬より飛んで下り、上帯切り、高紐外し、既に腹を切らんとし給ふ所に庄四郎高家鞭鐙を合はせて馳(は)せ来たり、急ぎ馬より飛んで下り、 |
|
と言われたが、聞こえないふりで、鎧につけた赤い印をかなぐり捨てて、一目散(いちもくさん)に逃げてしまった。三位中将重衡殿は、馬が弱ってしまったので、海へざっと乗り込んだが、そこは遠浅で沈みようがないので、急いで馬から飛び下り、上帯(うわおび)を切り、高紐(たかひも)を外(はず)し、まさに腹を切ろうというところへ、庄四郎高家が鞭を振るい鐙を蹴って駆けつけ、急いで馬から飛び下り、 |
| 「正(まさ)なう候ふ。何処(いづく)までも御供(おんとも)仕り候はんものを」 |
|
「それはなりません。どこまでも私がお供します」 |
| とて我が乗つたりける馬に掻(か)き乗せ奉り、鞍の前輪に締(し)め付け奉つて、我が身は乗替(のりがへ)に乗つてぞ帰りける。 |
|
と自分の乗った馬に担ぎ乗せ、鞍(くら)の前輪(まえわ)に縛(しば)りつけ、自分は乗り替え馬に乗って帰った。 |
| 乳母子の盛長は其処(そこ)をばなつく逃げ延びて、後には熊野法師(くまのぼふし)に尾中法橋を頼うで居たりけるが、法橋死んで後、後家の尼公訴訟(にこうそしよう)の為(ため)に京へ上るに供して上りたりければ、三位中将の乳母子にて上下多くは見知れたり。 |
|
乳母子の盛長は、その場をやすやすと逃げ延びると、後は熊野(くまの)の法師である尾中法橋(おなかのほうきょう)を頼ってそこにおり、法橋が死んで後、後家(ごけ)の尼公(にこう)が訴訟(そしょう)のために上洛(じょうらく)するとき、お供をして上ったが、三位中将重衡殿の乳母子(めのとご)だったので、京では多くの人に知られていた。 |
| 「あな憎や、後藤兵衛盛長が三位中将のさしも不便(ふびん)にし給ひつるに、一所(いつしよ)でいかにも成らずして思ひも寄らぬ後家尼公の供して上りたるよ」 |
|
「ああ憎(にく)い、後藤兵衛盛長は重衡殿にあんなにかわいがってもらっていたのに、運命を共にするでもなく、自分ひとり逃げてしまい、どこの馬の骨とも知れない後家尼(ごけあま)の供をして都に来た」 |
| とて皆爪弾(つまはじき)をぞしける。盛長もさすが恥づかしうや思ひけん、扇を顔にかざしけるとぞ聞えし。 |
|
と、皆軽蔑(けいべつ)をした。盛長もさすがに恥(は)ずかしく思ったか、扇(おうぎ)を顔にかざしていたと聞いた。 |

