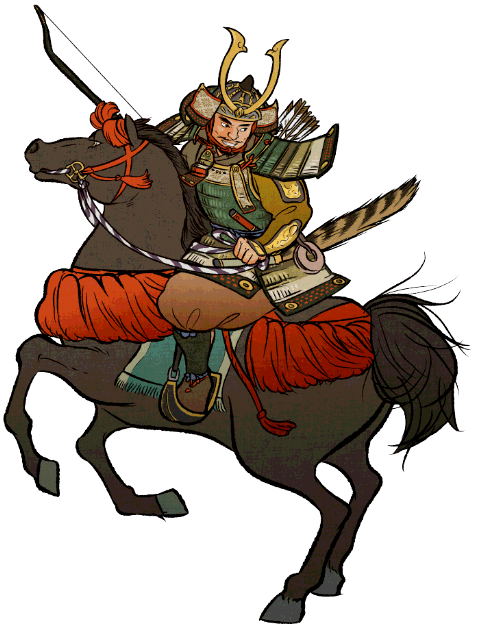木曾殿は信濃より巴、山吹とて二人の美女を具(ぐ)せられたり。山吹は労(いたは)りありて都に留まりぬ。中にも巴は色白う髪長く、容顔(ようがん)まことに美麗(びれい)なり。究竟(くつきやう)の荒馬乗りの悪所(あくしよ)落とし、弓矢、打物(うちもの)取つてはいかなる鬼にも神にも逢(あ)はうといふ一人当千(いちにんたうぜん)の兵(つはもの)なり。されば軍(いくさ)といふ時は、実(さね)よき鎧(よろひ)着せ、強弓、大太刀持たせて一方の大将には向けられけるに、度々(どど)の高名肩を並ぶる者なし。されば今度も多くの者共落ち失せ討たれける中に、七騎が中までも巴は討たれざりけり。 |
|

木曽殿(きそどの)は信濃(しなの)から巴(ともえ)、山吹(やまぶき)という二人の美女を連れて来ておられた。山吹は病のために都に留(とど)まった。巴は肌(はだ)の色白く、髪長く、容貌(ようぼう)は実に美しかった。屈強(くっきょう)な駻馬(あらうま)を乗りこなし、難所もものともせず、弓矢や刀剣(とうけん)を取ればいかなる鬼神(きしん)とも対峙(たいじ)しようという一騎当千(いっきとうせん)の武者であった。ゆえに戦となれば、よい拵(こしら)えの鎧(よろい)を着せ、強弓(つよゆみ)・大太刀(おおだち)を持たせて軍の大将として差し向けられれば、たびたびの高名(こうみょう)で肩を並べる者はいなかった。今度も多くの者たちが落ち延(の)び討(う)たれる中、残り七騎となってもまだ巴は討たれていなかった。 |
| 木曾は長坂を経て丹波路へとも聞ゆ。龍花越にかかつて北国へとも聞えけり。かかりしかども、今井が行末の覚束(おぼつか)なさに、取つて返して勢田の方へぞ落ち行き給ふ。今井四郎兼平も八百余騎で勢田を固めたりけるが、五十騎ばかりに討ち成され、旗をば巻かせて持たせつつ、主(しゆう)の覚束なさに、都の方へ上るつもりに大津の打出浜にてぞ木曾殿に行き合ひ奉る。中一町ばかりより違(たが)ひにそれと見知つて主従駒(こま)を早めて寄り合ひたり。木曾殿今井が手を取つて宣ひけるは、 |
|
義仲殿は長坂(ながさか)を経て丹波路(たんばじ)へ入ったという。龍華越(りゅうげご)えに差しかかり北国へ行ったとも言われている。しかし、兼平(かねひら)の消息がわからないので、引き返して勢田(せた)の方へ落ちていった。今井四郎兼平も八百余騎で勢田を守っていたが、五十騎ほどまでに討ち取られ、旗を巻かせて持たせながら、主君を心配して都へ上る途中、大津の打出浜(うちでのはま)で義仲殿と行き合った。一町(いっちょう)ばかり近づいて、互いを確認すると、主従(しゅじゅう)は馬を速めて近寄った。義仲殿が兼平の手を取って、 |
| 「義仲六条河原にていかにも成るべかりしかども、其処(そこ)で討たれんより汝(なんぢ)と一所でいかにも成らんと思ふ為にこそ多くの敵(かたき)に後ろを見せてこれまで遁(のが)れたるはいかに」 |
|
「おれは六条河原で死を覚悟していたが、そこで討たれることよりも、そちと一緒に死にたいと、多くの敵に背を見せて、ここまで逃げてきたんだ」 |
| と宣へば、今井四郎、 |
|
と言うと、兼平は、 |
| 「御諚(ごぢやう)まことに忝(かたじけな)う候ふ。兼平も勢田にて討死仕るべう候ひしかども、御行方(おんゆくゑ)の覚束(おぼつか)なさにこれまで遁(のが)れ参つて候ふ」 |
|
「ありがたいお言葉です。私も勢田で討ち死にするつもりでおりましたが、殿のことが心配でここまで逃げて参りました」 |
| と申しければ、木曾殿、 |
|
と言ったので、義仲殿が、 |
| 「さては契(ちぎ)り未だ朽(く)ちせざりけり。義仲が勢(せい)、山林に馳(は)せ散つてこの辺にも控(ひか)へたるらんぞ。汝(なんぢ)旗揚(はたあ)げさせよ」く |
|
「あのときの約束はまだ朽(く)ちてはいなかったな。我らが軍勢は、山林に馳(は)せ散ってこの周辺にもいるかもしれない。そちの旗を揚げさせてみよ」 |
| と宣へば、巻いて持たせたる今井が旗を差し上げたり。これを見付けて京より落ち来る勢ともなく、また勢田より落つる者ともなく、ほどなく三百余騎ばかりぞ馳せ集まる。木曾殿斜めならずに悦(よろこ)びて、 |
|
と命じると、巻いて持たせていた兼平の旗を差し上げた。これを見つけて、京から落ち延びた勢ともなく、勢田から落ちた者ともなく、ほどなく三百余騎ほどが馳(は)せ集まった。義仲殿はとても喜び、 |
| 「この勢(せい)にては最後の軍(いくさ)、一軍(ひといくさ)などかせざるべき。あれにしぐろうて見ゆるは誰が手やらん」 |
|
「この勢でなら最後の戦(いくさ)、一戦交えぬわけにはいかない。あそこに集結しているのは誰の軍だろう」 |
| 「甲斐(かひ)の一条次郎殿の御手とこそ承つて候へ」 |
|
「甲斐(かい)の一条次郎殿の手の者と聞いております」 |
| 「勢(せい)いかほどあるらん」 |
|
「軍勢の数は」 |
| 「六千余騎と聞え候ふ」 |
|
「六千余騎とのことです」 |
| 「さては互いによい敵(かたき)。同じう死ぬるとも大勢の中へ駆(か)け入り、よい敵に逢(あ)うてこそ討死をもせめ」 |
|
「ならばお互い好い敵だ。どうせ死ぬなら大勢の中に突(つ)っ込(こ)んで、好敵と交えて討ち死にしよう」 |
| とて真先(まっさき)にぞ進み給ふ。 |
|
と言って先頭に立って進軍した。 |
| 木曾その日の装束には、赤地錦の直垂に唐綾威の鎧着て、厳物作(いかものづく)りの大太刀を帯(は)き、鍬形打つたる甲の緒を締め、二十四差いたる石打の矢のその日の軍(いくさ)に射て少々残りたるを頭高(かしらだか)に負ひ成し、滋籐の弓の真中取つて、聞ゆる木曾の鬼葦毛といふ馬に金覆輪の鞍を置いて乗つたりけるが、鐙(あぶみ)踏ん張り立ち上がり、大音声(だいおんじやう)を揚(あ)げて、 |
|
義仲のその日の装束(しょうぞく)は、赤地錦(あかじにしき)の直垂(ひたたれ)に唐綾威(からあやおどし)の鎧(よろい)を着、厳(いか)めしい作りの大太刀(おおだち)を佩(は)き、鍬形(くわがた)の飾(かざ)りをつけた兜(かぶと)の緒(お)を締(し)め、二十四筋差しの石打矢(いしうちのや)の当日の戦の射残しを高く背負い、滋籐(しげどう)の弓の真ん中を持ち、名高い木曽の鬼葦毛(おにあしげ)という馬に金覆輪(きんぶくりん)の鞍(くら)を置いて乗っていたが、鐙(あぶみ)を踏(ふ)ん張(ば)って立ち上がり、大声を張り上げて、 |
| 「日比(ひごろ)は聞けんものを木曾冠者今は見るらん、左馬頭兼伊予守朝日将軍源義仲ぞや。甲斐一条次郎とこそ聞け。義仲討つて兵衛佐(ひやうゑのすけ)に見せよや」 |
|
「日頃噂(うわさ)に名高い木曽冠者(きそのかんじゃ)を見られるぞ、左馬頭兼伊予守(さまのかみけんいよのかみ)・朝日将軍源義仲(あさひのしょうぐんみなもとのよしなか)だ。甲斐一条次郎と聞いている。この義仲を討って頼朝に見せてやれ」 |
| とて喚(をめ)いて駆(か)く。一条次郎これを聞いて、 |
|
と叫んで突撃(とつげき)した。一条次郎はこれを聞き、 |
| 「只今(ただいま)名乗るは、大将軍ぞや。余(あま)すな者共(ものども)、漏(も)らすな若党(わかたう)、討(う)てや」 |
|
「今名乗ったのは大将軍だ。ぬかるな者ども、漏(も)らすな若者ども、討て」 |
| とて大勢の中に取り籠(こ)め、我討(われう)ち取らんとぞ進みける。 |
|
と大勢の中に取り囲み、我こそ討ち取ってやると攻めていった。 |
| 木曾三百余騎、六千余騎が中へ駆(か)け入り、縦様(たてさま)、横様(よこさま)、蜘蛛手(くもで)、十文字(じふもんじ)に駆け破つて、後ろへつと出でたれば、五十騎ばかりになりにけり。其処(そこ)を破つて行くほどに、土肥次郎実平二千余騎で支へたり。其処(そこ)をも破つて行くほどに、彼処(あそこ)にては四五百騎、此処(ここ)にては二三百騎、百四五十騎、百騎ばかりが中を、駆け破り駆け破り行くほどに、主従五騎にぞなりにける。五騎が中までも巴は討たれざりけり。 |
|
木曽勢三百余騎は、六千余騎の中に突入(とつにゅう)し、縦、横、八方、縦横(じゅうおう)に駆(か)け破(やぶ)り、後方へ抜けると、五十騎ほどになっていた。そこを突破(とっぱ)すると、土肥次郎実平(といのじろうさねひら)が二千余騎で待ち構えていた。そこも突破し、あそこでは四五百騎、ここでは二三百騎、百四五十騎、百騎ほどの敵中(てきちゅう)を撃破(げきは)しつつ進むうち、主従五騎になってしまった。その五騎の中までも巴(ともえ)は討たれず残っていた。 |
| 木曾殿、巴を召して、 |
|
木曽殿が巴を呼び、 |
| 「己(おのれ)は女なれば、これより疾(はよ)う疾(はよ)う何方(いづち)へも落ち行け。義仲は討死をせんずるなり。人手(ひとで)にかからずは自害をせんずれば、義仲が最後の軍(いくさ)に女を具(ぐ)したりけり、など云(い)はれん事も口惜(くちお)しかるべし」 |
|
「そなたは女だから、これより急いでどこへでも落ち延びろ。おれは討ち死にするつもりだ。人の手にかからないときは自害(じがい)するつもりだが、義仲は最後の戦にまで女を連れていた、などと言われるのも悔(くや)しい」 |
| と宣へども、なほ落ちも行かざりけるが、あまりに強う云はれ奉りて、 |
|
と言っても巴は立ち去らずにいたので、あまり厳(きび)しく言われ、 |
| 「あはれ、よからう敵(かたき)がな。木曾殿に最後の軍(いくさ)して見せ奉らん」 |
|
「ああ、好い敵はいないかなぁ。義仲殿に最後の戦をお見せしたいのに」 |
| とて控へて敵を待つ処(ところ)に、ここに武蔵国に聞えたる大力(だいぢから)、御田八郎師重、三十騎ばかりで出で来たる。巴その中へ破つて入り、まづ御田の腹に押し並べ、むずと組んで引き落し、我が乗つたりける鞍の前輪に押し付けて、ちとも働かさず、首捩(くびね)ぢ切つて捨ててけり。その後(のち)巴は物具(もののぐ)脱(ぬ)ぎ捨て、東国の方へ落ち行きける。手塚太郎討死す。手塚別当落ちにけり。 |
|
と控(ひか)えて敵を待っていると、そこに、武蔵国(むさしのくに)で知られた怪力(かいりき)の御田八郎師重(おんだのはちろうもろしげ)が三十騎ほどで現れた。巴はその中へ突入(とつにゅう)し、まず御田のわきに馬を並べ、むんずと掴(つか)んで引き落し、自分が乗った鞍(くら)の前輪(まえわ)に押しつけ、動けないようにして、首をねじ切って捨てた。そして、巴は甲冑(かっちゅう)を脱ぎ捨てると、東国の方へ落ち延びて行った。手塚太郎(てづかのたろう)が討ち死にした。手塚の別当(べっとう)は落ち延びた。 |
| 木曾殿、今井四郎ただ主従二騎になつて宣ひけるは |
|
義仲殿が、今井兼平と主従二騎きりになったとき |
| 「日比(ひごろ)は何とも覚えぬ鎧が今日は重うなつたるぞや」 |
|
「日頃は何とも思わぬ鎧(よろい)が今日は重たく感じる」 |
| と宣へば、今井四郎申しけるは、 |
|
と言うと、兼平は、 |
| 「御身(おんみ)も未だ疲れさせ給ひ候はず。御馬も弱り候はず。何によつて一領の御着背長(おんきせなが)を俄(にわか)に重うは思し召され候ふべき。それは御方(みかた)に御勢が候はねば臆病(おくびやう)でこそさは思し召し候ふらめ。兼平一騎をば余(よ)の武者千騎(むしやせんぎ)と思し召し候ふべし。此処(ここ)に射残したる矢七つ八つ候へば、暫(しばら)く防ぎ矢候はん。あれに見え候ふは粟津の松原と申し候ふ。君(きみ)はあの松の中へ入らせ給ひて静かに御自害候へ」 |
|
「お体もまだお疲れとは思えません。馬も弱っておりません。どうして一領(いちりょう)の大鎧(おおよろい)を急に重たいなどと思われるのですか。それは殿に味方の勢(せい)がなくて臆病(おくびょう)でそのように思われるのでしょう。この兼平一騎(かねひらいっき)を、他の武者千騎とお思いください。ここに射残しの矢が七つ八つありますから、少しの間は防(ふせ)ぎ矢できます。あそこに見えるのは粟津(あわづ)の松原というところです。殿はあの松の中へお入りになって静かに御自害(ごじがい)なさいませ」 |
| とて打ちて行くほどに、また新手の武者五十騎ばかり出で来たり。 |
|
と進んで行くと、また新手(あらて)の武者が五十騎ほど現れた。 |
| 「兼平はこの御敵(おんかたき)暫(しばら)く防ぎ参らせ候ふべし。君はあの松原へ入らせ給へ」 |
|
「私はこの敵をしばらく防ぎます。殿はあの松原へお入りください」 |
| と申しければ、義仲、 |
|
と言うと、義仲殿は、 |
| 「六条河原にていかにも成るべかりしかども、汝(なんぢ)と一所(いつしよ)でいかにも成らん為にこそ多くの敵に後ろを見せてこれまで遁(のが)れたなれ。所々(ところどころ)で討たれんより一所(ひとところ)でこそ討死(うちじに)をもせめ」 |
|
「六条河原で果てるべきところを、おまえと一緒に死ぬために、多くの敵に後ろを見せてここまで逃げてきた。離(は)ればなれで死ぬよりも、一緒(いっしょ)にここで戦って死のう」 |
| とて馬の鼻を並べて、駆(か)けんとし給へば、今井四郎馬より飛び下り、主(ぬし)の馬の水附に取り付き、涙をはらはらと流いて、 |
|
と馬の鼻を並べて、駆(か)けようとすると、兼平は馬から飛び降り、主(ぬし)の馬の水附(みずつき)にすがりつき、涙をほろほろ流して、 |
| 「弓矢取(ゆみやとり)は、年比日比(としごろひごろ)いかなる高名候へども、最後に不覚しぬれば永き瑕(いとま)にて候ふなり。御身(おんみ)もは疲れさせ給ひ候ひぬ。馬も弱つて候ふ。御方(みかた)に続く御勢も候はねば、大勢に押し隔(へだ)てられ、云ふかひなき人の郎等(らうどう)に組み落されて討たれさせ給ひ候ひなば、さしも日本国(につぽんごく)に鬼神と聞えさせ給ひつる木曾殿をば、何某等郎等(なにがしららうどう)の手に懸(か)けて討ち奉りたり、など申されん事、口惜(くちお)しかるべし。ただ理を枉(ま)げてあの松の中へ入らせ給へ」 |
|
「武人というものは、普段いかに名を上げていても、最後に不覚(ふかく)をとれば永久に不名誉(ふめいよ)な傷となってしまいます。お体もお疲れです。馬も弱っております。味方に続く軍勢もいませんから、大勢に包囲(ほうい)され、つまらぬ者どもに組み落され討たれでもして、『わが国に鬼神(きしん)と名高い木曽殿をどこそこの家来の何某(なにがし)が手にかけて討ち取ったぞ』などと言われては悔(くや)しくてなりません。どうかお願いです、あの松の中へお入りください」 |
| と申しければ、木曾殿、 |
|
と言うと、義仲殿は、 |
| 「さらば」 |
|
「わかった」 |
| とてただ一騎粟津の松原へぞ駆け給ふ。 |
|
と、ただ一騎で粟津の松原に駆(か)け込(こ)まれた。 |
| 今井四郎取つて返し、五十騎ばかりが勢(せい)の中へ駆け入り、鐙踏(あぶみふ)ん張(ば)り立ち上がり、大音声(だいおんじやう)を揚(あ)げて、 |
|
兼平は引き返し、五十騎ほどの敵勢(てきぜい)の中へ駆け込み、鐙を踏ん張って立ち上がり、大声を張り上げて、 |
| 「遠からん者は音にも聞け。近からん人は目にも見給へ。木曾殿の乳母子(めのとご)に今井四郎兼平とて生年(しやうねん)三十三に罷(まか)り成る。さる者ありとは鎌倉殿までも知(し)ろし召(め)されたるらんぞ。兼平討つて兵衛佐殿(ひやうゑのすけどの)の御見参(げんざん)に入れや」 |
|
「遠くにいる者はよく聞け。近くにいる者はとくと見よ。木曽殿の乳母兄弟(めのときょうだい)・今井四郎兼平、生年三十三、ここに参上した。おれのことは頼朝殿もご存じだ。この兼平を討ち取って頼朝殿にお見せしろ」 |
| とて射残したる八筋の矢を差し詰(つ)め引き詰め散々(さんざん)に射る。死生(ししやう)は知らず、矢庭(やには)に敵(かたき)八騎射落し、その後太刀を抜き斬(き)つて廻(まわ)るに、面(おもて)を合はする者ぞなき。 |
|
と、射残したる八筋(やすじ)の矢を番(つが)えては引き、さんざんに射た。敵の生死はわからないが、たちどころに敵八騎を射落とし、その後太刀(たち)を抜いて斬(き)り回れば、面(めん)と向かってくる者はいなかった。 |
| 「ただ射取れや、射取れ」 |
|
「とにかく射殺せ、射殺せ」 |
| とて矢先を揃(そろ)へて雨の降るやうに差し詰め引き詰め散々に射けれども、鎧よければ裏(うら)かかず、開間(あきま)を射ねば手も負はず。 |
|
と、矢先を揃えて夕立のようにつがえては引き、つがえては引き、さんざんに射たが、鎧が良いのか突(つ)き抜(ぬ)けず、隙間(すきま)も射られていないので、手傷(てきず)も負わない。 |
| 木曾殿はただ一騎粟津の松原へ駆け給ふほどに、比(ころ)は正月二十一日入相(いりあひ)ばかりの事なるに、薄氷は張つたりけり。深田ありとも知らずして、馬をさつとうち入れたれば、馬の首も見えざりけり。煽(あふ)れども煽れども、打てども打てども働かず。かかりしかども、今井が行方(ゆくゑ)の覚束(おぼつか)なさに、振り仰ぎ給ふ内甲(うちかぶと)を、相模国の住人三浦石田次郎為久追つかかり、よつ引いてひやうと放つ。木曾殿内甲を射させ、痛手(いたで)なれば、甲の真甲(まっこう)を馬の首に当て俯(うつぶ)し給ふ処(ところ)を石田が郎等(らうどう)二人落ち合つて、木曾殿の御首をつひに其処(そこ)にて賜(たま)はつてけり。やがて首をば太刀の鋒(きつさき)に貫き高く差し上げ、大音声を揚げて、 |
|
義仲殿はただ一騎粟津の松原へ駆け込まれると、時節は一月二十一日の黄昏時(たそがれどき)のことだったので、薄氷(うすごおり)が張っていた。深田(ふかた)があることも知らずに馬をざっと乗り入れると、馬の首も見えなくなった。横腹を蹴(け)っても蹴っても、鞭(むち)を打っても打っても、動かない。そんなときでも兼平のことが気がかりで、振(ふ)り仰(あお)げば、その内兜(うちかぶと)に相模国(さがみのくに)の住人・三浦石田次郎為久(みうらのいしだのじろうためひさ)が追いかかり、引き絞(しぼ)ってひゅっと放った。義仲殿は内兜を射られて深手を負い、兜(かぶと)の眉庇(まびさし)を馬の首に当ててうつ伏(ふ)したところを、石田の家来二人が連合し、義仲殿の首を取った。そして首を太刀の切っ先に貫(つらぬ)き高く差し上げ、大声を張り上げて、 |
| 「この日比(ひごろ)日本国に鬼神と聞えさせ給へる木曾殿をば三浦石田次郎為久が討ち奉るぞや」 |
|
「近頃日本国に鬼神と名高い木曽殿を、三浦の石田次郎為久が討ち取ったぞ」 |
| と名乗りければ、今井四郎軍(いくさ)しけるが、これを聞きて、 |
|
と名乗ると、今井四郎は戦の最中であったが、これを聞き、 |
| 「今は誰を庇(かば)はんとて軍(いくさ)をばすべき。これ見給へ、東国の殿原(とのばら)、日本一の剛(かう)の者の自害する手本よ」 |
|
「もはや誰を守るために戦(いくさ)をするのか。これを見よ、東国の武者ども、日本一の勇者が自害する手本(てほん)だ」 |
| とて太刀の鋒(きつさき)を口に含(ふく)み、馬より倒(さかさま)に飛び落ちて、貫(つらぬ)かつてぞ失(う)せにける。さてこそ粟津(あはづ)の軍(いくさ)は無かりけれ。 |
|
と、太刀の切っ先を口に咥(くわ)えると、馬からさかさまに飛び落ちて、串刺(くしざ)しになって死んでいった。こうして粟津の戦いは終わったのである。 |