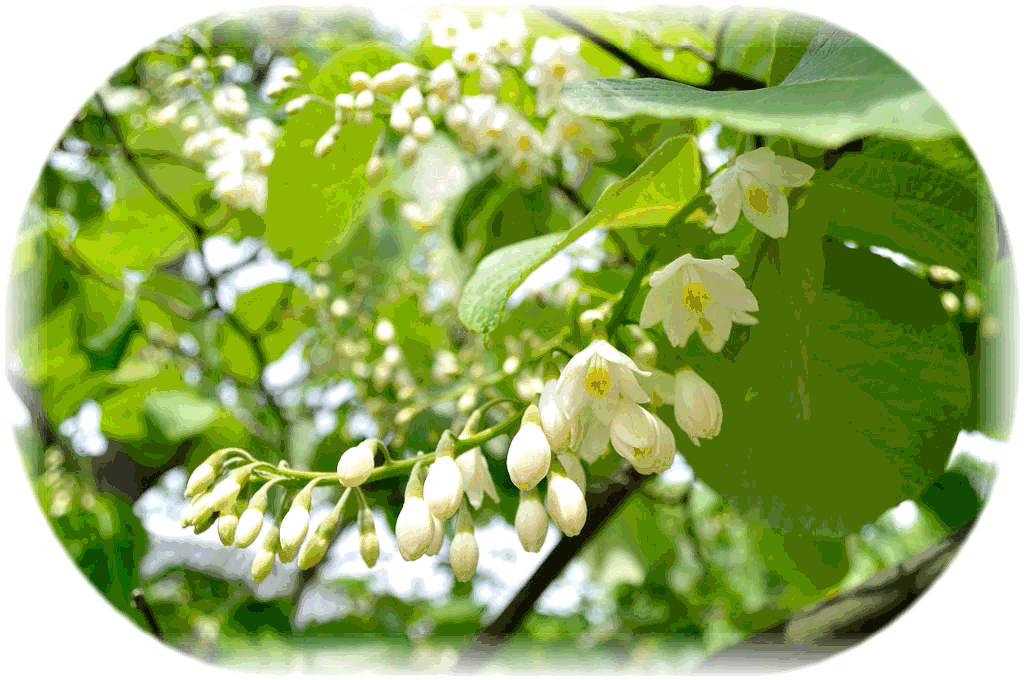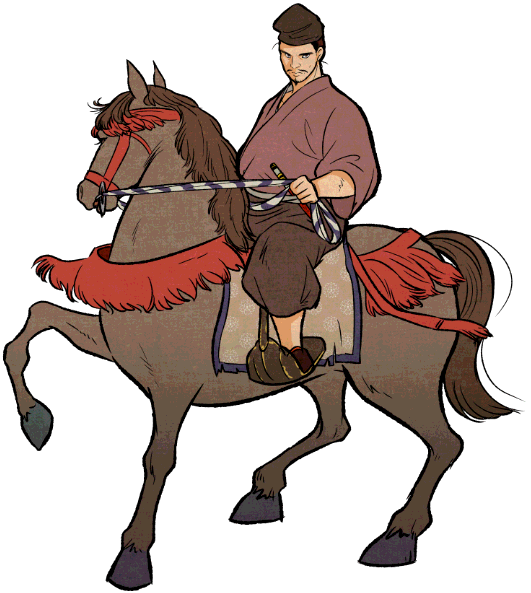|
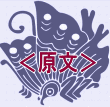
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり。 |
|

天竺(てんじく)の祇園精舎(ぎおんしょうじゃ)の鐘(かね)の音は、諸行無常(しょぎょうむじょう)の響(ひび)きをたてる。 |
| 娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)を顕(あらは)す。 |
|
釈尊(しゃか)入滅(にゅうめつ)の折に白く変じた娑羅双樹(さらそうじゅ、しゃらそうじゅ)の花の色は、盛者必衰(じょうしゃひっすい)の道理を表す。 |
| 奢(おご)れる人も久しからず、ただ春の夜の夢の如(ごと)し。猛き者もつひには滅びぬ、偏(ひとへ)に風の前の塵に同じ。 |
|
驕(おご)り高ぶる人の勢いも長くはない、春の夜の夢のようである。勇猛(ゆうもう)な者もついには滅ぶ、風の前の塵(ちり)に等しく。 |
| 遠く異朝を訪(とぶら)へば、秦の趙高、漢の王莽、梁の周伊、唐の禄山、これらは皆旧主先皇の政(まつりごと)にも従はず、楽しみを極め、諫めをも思ひ入れず、天下の乱れん事を悟らずして、民間の憂(うれ)ふる所を知らざりしかば、久しからずして亡(ぼう)じにし者共なり。 |
|
昔の異国を見てみれば、秦の趙高、漢の王莽、梁の周伊、唐の禄山、これらは皆前の君主や帝の治世にも従わず、豪奢(ごうしゃ)を極め、諫(いさ)めをも聞き入れず、天下が乱れることを悟らず、民衆の訴えにも素知らぬ顔をしたがゆえに、ほどなくして滅んだ者たちである。 |
| 近く本朝を窺(うかが)ふに、承平の将門、天慶の純友、康和の義親〔ヨシチカ〕、平治の信頼 〔ノブヨリ〕、これらは猛き心も奢れる事も皆とりどりにこそありしか、間近くは六波羅の入道、前太政大臣平朝臣清盛公と申し人の有様、伝へ承るこそ、心も詞(ことば)も及(およ)ばれね。 |
|
近頃の我が国に目を向ければ、承平の平将門、天慶の藤原純友、康和の源義親、平治の藤原信頼、この者たちは、猛(たけ)き心も驕れるさまもそれぞれであったが、近頃の六波羅(ろくはら)の入道・前太政大臣平朝臣清盛公(さきのだじょうだいじんたいらのあそんきよもりこう)という人のありさまは、伝え聞くほどに理解の限りを逸脱(いつだつ)し、語る言葉も追いつかない。 |
| その先祖を尋ぬれば、桓武天皇第五の皇子、一品式部卿葛原親王九代の後胤、讃岐守正盛が孫、刑部卿忠盛朝臣の嫡男なり。かの親王の御子高視王、無官無位にして失せ給ひぬ。 |
|
その先祖を見てみると、桓武(かんむ)天皇第五の皇子(おうじ)、一品式部卿(いっぽんしきぶきょう)・葛原親王(かづらはらのしんのう)九代の後胤(こういん)、讃岐守(さぬきのかみ)・平正盛(たいらのまさもり)の孫(そん)、刑部卿忠盛朝臣(ぎょうぶきょうただもりのあそん)の嫡男(ちゃくなん)である。その親王の御子(おんこ)・高視王(たかみのおう)は無位無官のまま亡くなった。 |
| その御子高望王の時、初めて平の姓を賜はつて、上総介に成り給ひしより、忽ちに王氏を出でて人臣に列なる。その子鎮守府将軍義茂、後には国香と改む。国香より正盛に至るまで、六代は諸国の受領たりしかども、殿上の仙籍(せんせき)をば未だ許されず。 |
|
その御子・高望王(たかもちのおう)のとき、初めて平(たいら)の姓(しょう)を賜(たまわ)って上総介(かづさのすけ)になられると、すぐさま皇族を離れて臣下として籍(せき)を置いた。その子・鎮守府将軍良望(ちんじゅふのしょうぐんよしもち)は、後には国香(くにか)と名を改めた。国香から正盛に至るまでの六代は諸国の受領(じゅりょう)であったが、殿上(てんじょう)への参内(さんだい)はまだ許されていなかった。 |