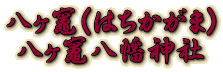
大方竈 他
平家の子孫
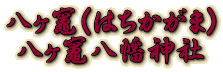 |
度会郡南伊勢町 大方竈 他 |
<人物> 平家の子孫 |
|
平家の子孫は、南伊勢町まで南下し、「竃(かま)」を構成して隠れ住んだようです。いずれも入り江の奥まったところにあり、近くに川と山がひかえています。人々は、ここで塩焼き竈を築いて製塩業を行い、生計をたてて暮らしていました。赤崎竈は、安政元年(1854)の津波で流されて廃村となり、現在は新桑竈(さらくわがま)、棚橋竈(たなはしがま)、栃木竈(とちのきがま)、小方竈(おがたがま)、大方竈(おおがたがま)、道行竈(みちゆくがま)、相賀竈(おおかがま)の七つになってしまいました。
|
|||