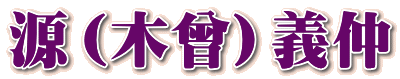
(みなもとの(きそ)よしなか) |
<登場する章段>
6の5・13
7の1・5・10
8の2・6・8・10・11
9の1・2・3・4 |
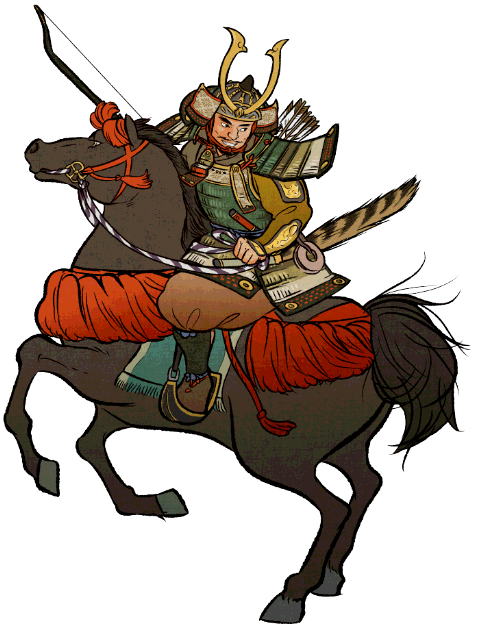 |
| <プロフィール> |
| 信濃源氏の武将。以仁王(もちひとおう)の命を受けて挙兵し、倶利伽羅峠(くりからとうげ)の戦いで平家軍を破って入京する。平家一門を都落ちまでに追い込んだが、治安維持の失敗と大軍による食糧事情の悪化、皇位継承への介入などにより後白河法皇や源頼朝と対立する。寿永三年(1184年)、征夷大将軍となったものの、頼朝が送った源範頼・義経軍によって、近江国(おうみのくに)粟津(あわ)の戦いで討たれた。 |
| <エピソード> |
源頼朝・義経兄弟とは従兄弟にあたる。朝日将軍と呼ばれた。山村に育った義仲は、貴族化した平氏一門や幼少期を京都で過ごした頼朝とは違い、宮中の政治・文化・歴史への知識や教養がない人物として描かれる段もあるが、乳母子(めのとご)兼平との人間的なつながりも表現されている。義仲の墓所は、朝日山義仲寺(滋賀県大津市)にある。この寺に江戸時代の俳人・松尾芭蕉の墓があるのは、芭蕉が義仲の人柄にひかれ、義仲の隣に葬ってほしいとの遺言からである。※「義仲の寝覚(ねざめ)の山か月かなし」(芭蕉) ※「木曾人は海のいかりをしづめかねて 死出の山にも入りにけるかな」(西行)
|
| <名言> |
(生没年) 1189〜1189.閏4.30 |
|
<意味>
これまではなんとも思わなかった鎧が、今日は重くなったぞ。 |
| ついに主従二騎になると、義仲は今井四郎兼平にこう言う。兼平は近くの松原で自害するよう義仲に勧める。義仲31歳、後を追って自害した兼仲33歳であった。 |
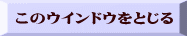 |