
(けんれいもんいんとくこ) |
<登場する章段>
3の1・3
6の13
7の13
11の10
灌頂の1・2・3・4・5 |
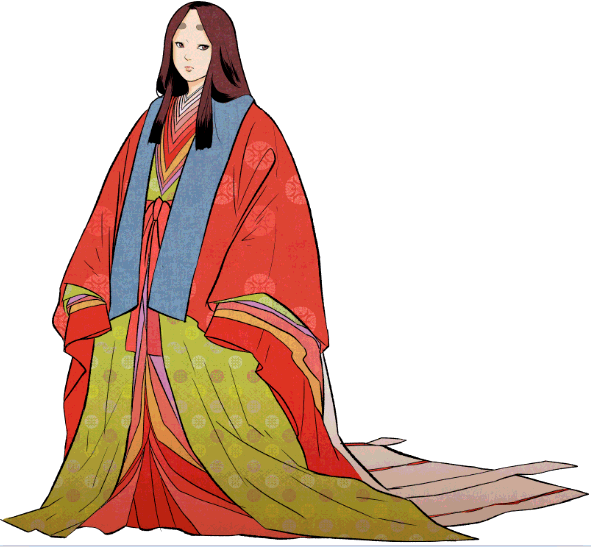 |
| <プロフィール> |
| 父は平清盛、母は平時子。清盛には8人の娘がいたが、高倉天皇(11歳)に15歳で入内し、7年後に皇子を産む。安徳天皇の即位後は国母となるが、壇ノ浦の戦いで安徳天皇と、母の時子は入水、平氏一門は滅亡する。海中に身を投ずるが引き上げられ、生き残った徳子は京へ送還(そうかん)されて出家し、大原寂光院(おおはらじゃっこういん)で安徳天皇と一門の菩提(ぼだい)を弔(とむら)った。 |
| <エピソード> |
| 高倉上皇が21歳の若さで崩御(ほうぎょ)した時、後白河法皇の後宮にという話が出たが、徳子は拒絶し、後白河法皇も辞退した。従順だった徳子が両親の意向に逆らったのは、この時だけだったと思われる。建礼門院に仕えた女房で平資盛(たいらのすけもり)の恋人、右京大夫が大原を訪れた時、「都ではわが世の春を謳歌(おうか)して美しい着物を着重ねて仕えていた女房が、60人余りいたけれど、ここには見忘れるほどに衰(おとろ)えた尼姿(あますがた)で、僅(わず)かに3、4人だけがお仕えしている」と涙を流し、歌を詠んでいる。(「建礼門院右京大夫集」) |
| <名言> |
(生没年) 1155〜1213.12.13 |
|
<意味>
海に沈んだ先帝の面影は忘れようとしても忘れられず、悲しみを忍ぼうとしても、忍ぶ事ができません。 |
| 後白河法皇に問われるままに、女院は都落ちから一門入水までを涙ながらに物語る。 |
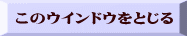 |