
(たいらのときこ)
|
<登場する章段>
6の7
10の4・13
11の9 |
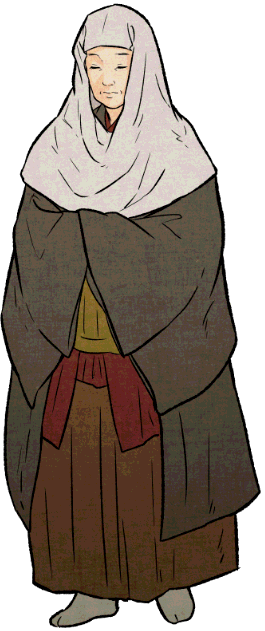 |
| <プロフィール> |
| 中級貴族の平時信の娘。清盛の妻。清盛との間に宗盛、知盛、徳子(建礼門院)、重衡らを生む。清盛とともに43歳で出家する。娘徳子が高倉天皇に入内(じゅだい)した際に従二位となり、二位尼(にいのあま)と称される。中宮の母として徳子の出産や、高倉帝の皇子女の出生や成長儀式にも深くかかわり、皇室との関係を結ぶ役割も果たしたが、壇ノ浦で安徳天皇を抱いて入水する。 |
| <エピソード> |
| 清盛の死後は、息子の宗盛とともに一門を率いる立場となる。息子の重衡は「おぼえの御子(お気に入りの子)」であり、一の谷で捕虜となった息子からの手紙を抱いて悲嘆(ひたん)にくれる姿が描かれている。下関市にある赤間神宮は安徳天皇を祀っている。壇ノ浦を望む水天門は鮮やかな竜宮造り。「海の中にも都はある」という二位尼の願いを映したものといわれている。この神宮では現在まで平家一門の慰霊祭が続いている。また山口県長門市日置町には、二位尼の遺体が黒潮に乗り流れ着いたという「二位ノ浜」と呼ばれる浜辺がある。ハマユウに守られるように、二位ノ局の碑が建っている。 |
| <名言> |
(生没年) 1126〜1185.3.24 |
|
<意味>
波の下にも都がございますよ。 |
| 泣きながら念仏を唱えられた安徳天皇を慰めると、二位尼は深い海底へと身を投げた。 |
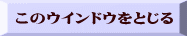 |