
(たいらのただのり) |
<登場する章段>
4の16
5の11・13
7の16
8の3
9の14 |
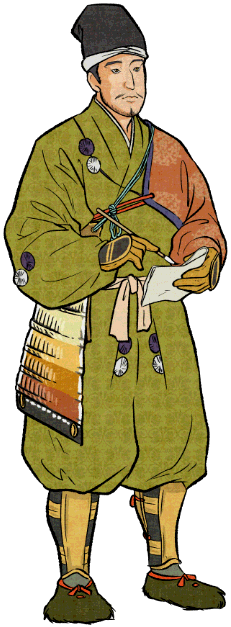 |
| <プロフィール> |
平忠盛の六男。平清盛の異母弟。治承4年(1180年)正四位下・薩摩守(さつまのかみ)。武芸だけでなく、歌人としても優れており藤原俊成(ふじわらのしゅんぜい)に師事した。平家一門と都落ちした時、自分の歌が百余首おさめられた巻物を俊成に託した。「千載集」をはじめ勅撰集に計十首選ばれている。富士川の戦い、倶利伽羅峠の戦い等に出陣。一ノ谷の戦いで、源氏方の岡部忠澄と戦い41歳で討死。その首は八条河原に並べられた。
|
| <エピソード> |
| 小学唱歌「青葉の笛」(大和田建樹作詞、作曲・田村虎蔵)の二番は、平忠度の都落ちを歌う。また、世阿弥の能「忠度」は、「忠度都落」「忠度最期」がもとになっている。忠度の霊が「千載集」の「読み人知らず」とある自分の歌に作者名を入れよと、俊成の子である定家に頼む姿が描かれている。なお、「新勅撰和歌集」以降は薩摩守忠度の名で歌が選ばれている。当時、勅撰和歌集に和歌が選ばれることは大変な名誉であった。
文武に優れた忠度の討ち死は、敵味方に惜しまれた。忠澄は忠度の菩提(ぼだい)を弔(とむら)うため、埼玉県深谷市の清心寺に供養塔を建立している。 |
| <名言> |
(生没年) 1144〜1184.2.7 |
|
<意味>
今は西海の底に沈むのなら沈んでもよい、山野に死体をさらすのならさらしてもよい、この世になんの未練もありません。 |
| 師の俊成に歌の巻物を託した忠度は、いさぎよく心静かな様子で都を落ちて行った。 |
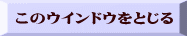 |