
(たいらのしげひら) |
<登場する章段>
3の3
4の16
5の12・14
8の2・9
10の1・2・3・4・5・6・7
11の19 |
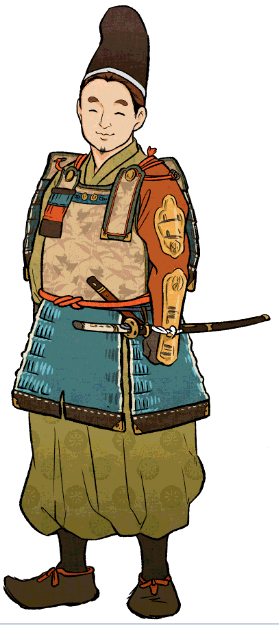 |
| <プロフィール> |
| 清盛の五男。母は平時子。三位中将と称された。平氏の大将の一人として各地で戦い、南都攻略を行って東大寺大仏や興福寺(こうふくじ)を焼亡させた。墨俣川(すのまた)の戦いや水島の戦いで勝利して活躍するが、一ノ谷の戦いで馬を射られて捕虜(ほりょ)になり、鎌倉で頼朝と対面する。平氏滅亡後、南都衆徒に引き渡され、木津川畔(こずがわはん)で斬首。その首は、奈良坂にさらされた。 |
| <エピソード> |
| その将才は「武勇の器量に堪ふる」(「玉葉」)と評される一方、「建礼門院右京大夫集」や「平家公達草紙」によると、重衡は人のために心遣いをする人物であり、いつも冗談を言い、怖い話で女房を怖がらせたり、退屈していた高倉天皇をなぐさめるために、強盗のまねをして天皇を笑わせたという。容姿は「なめまかしくきよらか」と書かれ、牡丹の花に例えられた。重衡の妻は、壇ノ浦で入水したが助け上げられ、夫が護送される途中の日野で再会を果たした。重衡の遺体と首をもらい受けて日野に墓を建てた。(京都市伏見区の団地に残っている。)能「重衡」は、奈良坂の墓地にある石製の笠塔婆から迷い出た重衡の霊が旅の僧に供養を頼む描写がある。須磨寺駅付近に「平重衡とらわれの松跡」の碑がある。 |
| <名言> |
(生没年) 1157〜1185.6.23 |
|
<意味>
弓矢を持つ武士の常だから、敵の手にかかって命をなくす事は全く恥のようであって、ほんとうの恥ではない。ただご恩には、さっさと頭を斬られよ。 |
| 鎌倉で頼朝に対面した重衡は、毅然(きぜん)として言い放つ。その場に居並ぶ人々は立派な大将軍だと涙した。 |
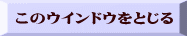 |