
(もんがく) |
<登場する章段>
5の7・8・9・10
12の7・8・9
|
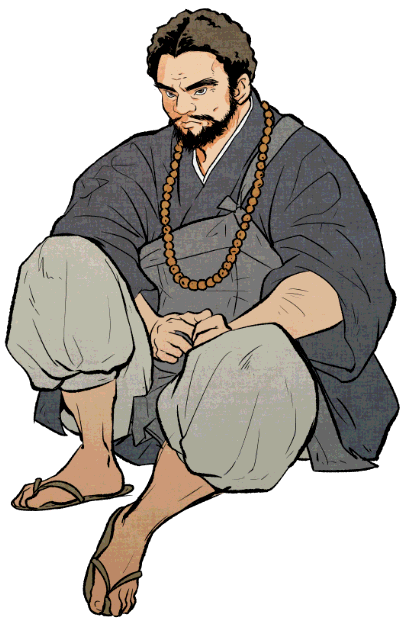 |
| <プロフィール> |
| 平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武士・真言宗の僧。俗名は遠藤盛遠(えんどうもりとお)。後白河院の御所に押しかけ、荘園寄進を強要して伊豆に流罪となった。源頼朝や後白河法皇の支援を受けて神護寺、東寺、東大寺
など、各地の寺院を勧請(かんじょう)し、所領を回復したり建物を修復した。 また頼朝のもとへ弟子を遣わして、平維盛の遺児六代の助命を嘆願し、神護寺に保護した。 |
| <エピソード> |
| 三十日間の断食(だんじき)、二度までも死にかけた熊野の那智(なち)での滝行(たきぎょう)のすさまじさや暴風雨を静める力など、常人とは思えない霊力(れいりょく)が描かれる。また、権力に逆らって行動する人物として描かれる。鎌倉幕府を開いた頼朝は、文覚に護持僧(ごじそう)という役割を与えて重用したというが、六代の助命については「文覚の言葉に逆らえば神仏に見放される」と頼朝をおどし、後鳥羽院に対しては「毬杖(ぎっちょう)遊びの若僧」と悪口を言っている。文覚が出家するきっかけとなった話は芥川龍之介の小説「袈裟(けさ)と盛遠(もりとお)」がある。 |
| <名言> |
(生没年) 1139〜1203.8.29 |
|
<意味>
いまこそ謀反を起こして、日本国を統一されたがよい。 |
| 後白河法皇によって流された伊豆の地で、「重盛亡き後、源平両家の中で頼朝こそが将軍にふさわしい骨相をもっている」と、文覚は、義朝の髑髏(どくろ)を見せて挙兵を迫る。 |
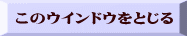 |