
(たいらのあつもり) |
<登場する章段>
9の16
|
 |
| <プロフィール> |
| 清盛の弟・経盛の末子。位階は従五位下。官職にはついておらず、無官大夫(むかんのたいふ)と称された。笛の名手であり、祖父・平忠盛が鳥羽院より賜(たまわ)った『小枝(さえだ)』という笛を譲(ゆず)り受ける。17歳で一ノ谷の戦いに参加。源氏側の奇襲(きしゅう)を受け、熊谷直実に首を取られた。その腰には錦(にしき)の袋に入れた笛が差されていた。※謡曲での笛の名前は「青葉」。
|
| <エピソード> |
| 世阿弥(ぜあみ)の謡曲「敦盛」、幸若舞(こうわかまい)「敦盛」などの題材となった。織田信長の好んだ歌「人間五十年、下天のうちをくらぶれば、夢幻の如くなり。一度生を享け滅せぬもののあるべきか
」は幸若舞『敦盛』の一節である。小学唱歌「青葉の笛」の一番は、敦盛の最期を歌って広く知られる。須磨寺には敦盛の首塚や首洗い池がある。(芭蕉の句に「須磨寺や吹かぬ笛聞く木下やみ」)また、敦盛と直実が背中に背負っていた母衣(ほろ)に花の形が似ているということで、「クマガイソウ」「アツモリソウ」と名づけられたランの仲間や、「クマガイウオ」「アツモリウオ」と名づけられた魚もいるほど、2人のエピソードは有名である。 |
| <名言> |
|
|
|
|
<意味>
ただ、早く早く首を取れ。 |
| 味方が迫ってきたので、私の手におかけして、後の供養をいたしましょうという熊谷に対して答えた、敦盛の最期の言葉である。 |
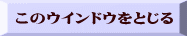 |

