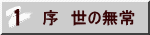 |
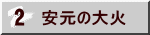 |
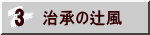 |
| 人の世のはかなさを、さまざまな例えで表現しています。その中でも冒頭の一文「ゆく河の流れは」は、「方丈記」全体を流れる思想を一言で表現した文章として有名です。人間の生と死、私たちの住まいについて考えてみませんか。 |
長明が見たり聞いたりした「世の不思議」(天変地異)が次々と語られていきます。まずは長明23歳の年、大火災によって京都の三分の一が焼き尽くされました。その現場がどのような様子であったか、長明の表現から想像してみましょう。 |
長明26歳の年、昼下がりに発生したつむじ風の様子が語られています。つむじ風とは竜巻のことです。中御門京極あたりは京都の東北部にあたります。ここで発生した竜巻が南南西の方向へ吹き移ってゆきました。どのような様子だったのか見てみましょう。 |
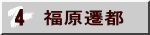 |
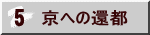 |
 |
| 同じ年の6月、長明26歳の年、平安京から福原へ都が移されました。福原は現在の神戸市中央区あたりです。平清盛の政策によるものでした。引越しをする人々の様子や、建設中の新都の様子まで長明は自らの足で歩いて確かめています。 |
新しく都となった福原の様子が描かれています。ところが、福原遷都は災いをもたらすという世の中の声が高まり、遷都は一年もせず中止となりました。遷都は真夏、還都は厳冬の時期でした。人々の生活や思いはどのようなものだったでしょう。 |
長明27、28歳の年、養和の飢饉がありました。養和元年(1181)から翌年にかけて起こった飢饉で、京都を始め西日本一帯が飢餓に苦しみました。天候異変の他に、源平の戦いが都の人々にどのような影響を与えたか考えてみましょう。 |
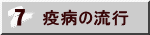 |
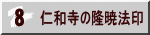 |
 |
| 長明28歳の年、飢饉に苦しむ人々をさらに追い詰める出来事が起こりました。疫病(えきびょう・伝染病)の流行です。京都の街の様子とともに、生き残るために人々がどのようなことをしたのか、その様子も詳しく述べられています。 |
長明は2か月間かけて東の京(左京全域)の死者数を数え、記録に残しています。食糧難の深刻さがわかります。また、夫婦や親子の様子、仁和寺の隆暁法印という方の行動についても語っています。それはどういう理由からでしょう。 |
養和の飢饉より3年後、文治元年(1185)、長明31歳の年、3月に平家が壇ノ浦の戦いで源氏に破れて滅亡しました。同じ年の7月9日正午頃、京都とその周辺に大地震が起きました。長明は、武者の姿から何を伝えたかったのでしょう。 |
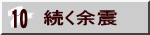 |
 |
|
| 8、9月には本震に続き、余震が繰り返し起こっています。人々の不安はつのり、この地震は滅亡した平家の怨霊(おんりょう)によるのではといううわさまで広がりました。災害に対する世間の人々の反応に注目して読んでみましょう。 |
|
|
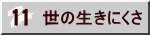 |
|
ここから後半の序になる文が始まります。20代から30代までの体験は長明にどのような影響を与えたのでしょうか。天変地異や人のはかなさをふまえて、世の中の生きにくさについて語っています。平安時代末期と現代の日本社会を比べながら読んでみましょう。 |
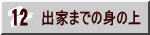 |
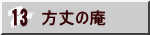 |
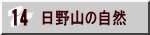 |
| 50歳で出家するまでのいきさつを語っています。長明の父は下鴨神社の総禰宜(そうねぎ)という重要な地位に就いていました。ところが、その父を18歳の時に亡くします。その後、彼の生活や住まいはどうなっていったでしょう。 |
承元2年(1208)、54歳の頃に、長明は大原から日野に移り、最後の住まいとなる「方丈」の庵を建てました。生まれた家の百分の一という狭さです。家の中にはどのようなものを置いたのでしょうか。彼が理想とした住まいをのぞいてみましょう。 |
「方丈」の庵の周りはどんな様子だったでしょう。四季の自然や、長明の日々の生活ぶりが語られています。山の風景、動物や植物、風の音など、長明が心ひかれたものをみていきましょう。彼の趣味もわかります。 |
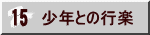 |
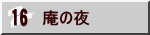 |
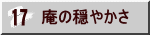 |
| 60歳の長明が、10歳の少年と一緒に遊んだり、散策したり、時には遠くまで出かけています。地図を参考にして、そのあしどりをたどりながら、四季の自然を楽しみましょう。彼が尊敬した古人もわかります。 |
ある風景を見て誰かの歌を思い出したり、昔の人の気持ちに共感したりしたことはありませんか。長明は和歌や古典の知識が豊富でした。この段は、古詩や古歌をふまえた美文だといわれています。関連する文学を参考にして、庵の夜を味わいましょう。 |
「方丈」の庵の意義を語っています。人間は何のために住まいを作るのでしょう。将来、あなたが家を建てるとしたら、どんな家に住みたいですか。兼好法師も「徒然草」で人の生き方や無常について語っています。「方丈記」と読み比べてみましょう。 |
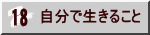 |
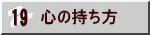 |
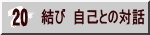 |
| 長明が祖母の家で暮らしていた頃には、大邸宅に住み、召使のいる生活が当たり前だったはずです。ところが、50歳を過ぎて「自分で生きる」ことを決意したのです。友人や召使についての考え方を読んでどう思いましたか。 |
「方丈」の庵での生活について、結論を述べています。「この世の中のあらゆることは、その人の心の持ち方一つで決まる。」閑居の味わいを伝えるためにさまざまな例えを使っています。 |
建暦二年(1212)、長明58歳の年に「方丈記」は完成しました。最終章では、自分を客観的に見つめようと自問自答しています。特に結末の一文は昔から意味が分かりにくく、口語訳が難しいと言われていますが、あなたなら長明の心境をどう解釈しますか。 |


![]()