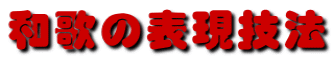|
項目 |
説 明 |
百人一首の和歌の例 |
和歌の
リズム |
句切
くぎれ |
日本語の五音、七音はリズムのある音数ですが、言葉の並べ方や選び方によって生き生きとした和歌になります。意味や調子の切れ目を句切れといいます。句切れのない歌や、句切れの2つある歌もあります。
二句切れ 四句切れ
5 / 7 / 5 / 7 / 7
初句切れ 三句切れ
①五七調=二句切れ・四句切れの和歌。「万葉集」に多く、のびのびとした雄大なリズムです。
②七五調=初句切れ・三句切れの和歌。「古今集」「新古今集」に多く、優美でなだらかなリズムです。
※「古今集」に三句切れが多いので、三句までを上(かみ)の句、それ以下を下(しも)の句といい、句切ってよむ習慣ができました。 |
●句切れなし
4番「田子の浦に うちいでて見れば 白妙(しろたへ)の 富士の高嶺(たかね)に 雪は降(ふ)りつつ」
●二句・四句切れの歌
2番「春過ぎて 夏来にけらし/白妙(しろたへ)の 衣ほすてふ/天(あま)の香具山 」
●二句切れ
35番「人はいさ 心も知らず/ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける 」
40番「忍ぶれど 色に出でにけり/わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで」
●三句切れの歌
28番「山里は 冬ぞさびしさ まさりける/人めも草も かれぬと思へば 」 |
|
歌枕
うたまくら |
歌に詠まれた土地や名所の地名のことを「歌枕」といいます。「万葉集」には約1200の地名が出てきます。「古今集」以降には、和歌のテクニックの一つとして、国内の地名を和歌に詠みこんで歌うことで、ある意味を持たせる技法が大流行しました。歌枕の地名は特定のイメージを持つようになっていきます。
「須磨」→都から遠く離れた寂しい場所。
「難波」→葦。「難波潟」→葦の茂った、荒れ果てて寂しい風景。
「小倉山」→紅葉
「吉野」→桜・雪
「初瀬」→鐘
「竜田川」→紅葉
「末の松山」→心変わり
「飛鳥川(あすかがわ)」→流れが定まらない川であったので、明日はどうなるかわからない、人の世の無常のたとえ。 |
●2番「天(あま)の香具山」●4番「富士・田子の浦」●7番「三笠(みかさ)の山」
●8番「うぢ山」●10番「逢坂(あふさか)の関」●13番「筑波嶺(つくばね)の峯・みなの川 」
●14番「陸奥(みちのく)・ しのぶ」●16番「いなばの山 」●17番「竜田(たつた)川」
●18番「住の江」●19番「難波潟(なにはがた) 」●20番「難波(なには)」
●25番「逢坂(あふさか)山」●26番「小倉山」●27番「みかの原・泉川」
●31番「吉野」●34番「高砂」●42番「末の松山」●46番「由良 」
●51番「伊吹」●58番「有馬山・猪名」●60番「大江(おほえ)山・いく野・天(あま)の橋立 」
●61番「奈良」●62番「逢坂の関」●64番「宇治の川」
●69番「三室(みむろ)の山・竜田(たつた)の川」●72番「高師(たかし)の浜 」
●74番「初瀬(はつせ)」●78番「淡路島・須磨」●88番「難波江」
●90番「雄島」●92番「沖(おき)の石」●94番「み吉野」
●97番「まつほの浦 」●98番「ならの小川」 |
和歌の
表現技法 |
枕詞
まくらことば |
枕詞は、主に歌の最初において、次の言葉を引き出すかざりのような言葉です。この時代、歌は耳から入ってくるものだったので、歌の聞き手に次の言葉のイメージをふくらませる時間を与える働きがありました。もともとは意味のある語でしたが、やがて印象を強めたり、音の響きを整えたりする役割になりました。奈良時代には約630語でしたが、平安時代、江戸時代にも増えて、約1200語もあるそうです。ほとんどは5音ですが、4音、6音の枕詞もあります。
「あしひきの」→山・峰などをかざる。
「あまのはら」→ふりさけみ
「高砂の」→松をかざる。
「白妙の」→布と白い色のもの(衣・袖そで・雪・雲・波・袂たもと・帯おび・紐ひも・砂)をかざる。
「ちはやぶる」→神・宇治などをかざる。
「ひさかたの」→天空に関係あるもの(天・雨・空・月・雲居・日・雪)などをかざる。
「あをによし」→奈良などをかざる。 |
●2番「春過ぎて 夏来にけらし 白妙(しろたへ)の 衣ほすてふ 天(あま)の香具山 」
●3番「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかも寝(ね)む」
●7番「天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠(みかさ)の山に いでし月かも 」
●17番「ちはやぶる 神代(かみよ)も聞かず 竜田(たつた)川 からくれなゐに 水くくるとは 」
●33番「久かたの 光のどけき 春の日に しづ心なく 花の散るらむ 」
●76番「わたの原 漕ぎ出でて見れば 久方の 雲居にまがふ 沖つ白波」
|
|
序詞
じょことば |
言葉に具体的なイメージを与える表現です。ある言葉を導き出すために、その前に置かれる語句です。リズムを整えたり、印象を強める働きをします。枕詞に似ていますが、枕詞のほとんどが5音なのに対して、序詞は五音以上が普通です。長さが制限されず作者が工夫して自由に作ることができます。何となくその語が出てくるムードを盛り上げるための序奏(イントロ)のようなものです。
・比喩や掛詞を使った、意味の上で働きがあるもの、
・同音をくりかえす、音の響きを整えるもの、゜
があります。 |
●3番「あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の」
「ながながし」を導き出すために、どれだけ長いかをイメージさせています。
●14番「みちのくのしのぶもぢずり」
「乱れ」を導くための序詞です。「もぢずり」の乱れ模様は恋に乱れる気持ちを連想させます。
●18番「住み江の岸に寄る波」
「寄る」と同音の「夜」を導きだす序詞になります。岸辺に打ち寄せては返す波のイメージによって、ゆらゆらとたよりなげな恋の姿が描かれています。
●27番「みかの原 わきて流るる 泉川(いづみがは)」
泉川の水の動きのイメージが、恋心を効果的に伝える働きをしています。
●39番「あさぢふの 小野のしの原」
「忍ぶ」を導くための序詞です。「篠原」が「しのぶ」にかかる、同音反復の用例です。茅(ちがや)がところどころに生えている篠原は、荒涼とした風景なので、かなう見こみのない恋を連想させます。
●46番「由良の門(と)を わたる舟人 かぢをたえ」
「ゆくへも知らぬ」を導き出す序詞です。櫂(かい)をなくして漂う船乗りの心細い気分がそのまま、下の句の不安な恋の気分へとつながっています。 |
|
見立
みたて |
見立てとは、あるものを別のものにたとえて示すことです。日本庭園では、富士山に見立てて山を築いたり、垂直に立てた岩を滝に見立てるなどがあります。和歌では、想像という制限のない中で、より美しい表現を求めて見立てを用います。春の満開の桜は雲に、散る花は雪に、秋の紅葉は錦に見立てられてきました。「古今集」において確立した美意識です。
他にも、雪→花、波→花、雨→涙、露→玉、女郎花→女などがあります。
|
●69番「あらし吹く 三室(みむろ)の山の もみぢ葉は 竜田(たつた)の川の にしきなりけり」
川面に浮かぶ紅葉の美しさを、竜田川が織り上げた錦(金銀など五色の色糸を使って模様を描き出した華やかな織物)だと表現しています。
●35番・紀貫之の他の歌を例を挙げると、
「桜花 散りぬる風の なごりには 水なき空に 波ぞ立ちける」(風が吹きつけて桜の花が散ったあとには、水もない空に波が立っていることだよ)
落花を海の波にたとえています。
●「雪ふれば 冬ごもりせる 草も木も 春に知られぬ 花ぞ咲ける」(雪が降って一面の銀世界になった。寒さのために冬眠をしている草も木も、春には見ることのできない花を咲かせている。)
枝や葉に積もった雪を花に見立てています。 |
|
掛詞
かけことば |
1つの言葉に2つ以上の意味をもたせる技法です。音が同じで、意味の違う言葉(同音異義語)を使います。一方は自然の風景を表し、もう一方は人の心の様子を表すなどがあります。言葉遊びの一つで、今のダジャレにつながるものです。31文字の和歌で、さまざまな内容や気持ちを表現するのに便利です。「古今集」「新古今集」に多く使われています。 |
●9番「花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世(みよ)にふる ながめせし間に 」
ふる=「経る」と「降る」
ながめ=「眺め」と「長雨」
●16番「立ち別れ いなばの山の 峰(みね)に生ふる まつとしきかば 今かへり来む 」
いなば=「往(い)なば」と「因幡(いなば)」
まつ=「松」と「待つ」
●28番=「山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人めも草も かれぬと思へば」
かれ=「枯れ」と「離れ」
●51番「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」
いふ=「言ふ」と「伊吹」
●60番「大江(おほえ)山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天(あま)の橋立」
いくの=「生野」と「行く野」
ふみもみず=「踏みもみず」「文も見ず」
●72番「音に聞く 高師(たかし)の浜の あだ波は かけじや袖(そで)の 濡(ぬ)れもこそすれ 」
たかし=「高師」と「高し」
●88番「難波江(なにはえ)の 芦(あし)のかりねの 一よゆゑ みをつくしてや 恋ひわたるべき」
かりね=「刈り根」(蘆を刈り取った後の根っこ)と「仮寝」(旅先での、仮の宿でねること)
一よ=「一節」(蘆の節と節の間)と「一夜」
みをつくし=「澪標」(船のための標識)と「身を尽くし」(身を滅ぼすほどに恋い焦がれること)
●97番「来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩(もしほ)の 身もこがれつつ」
まつ=「松」と「待つ」 |
|
縁語
えんご |
ある語と意味につながりのある言葉を入れて、調子を整え、連想させて表現効果を高める技法です。掛詞と一緒に使われることが多いです。
「古今集」「新古今集」に多く使われています。 |
●28番=「山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人めも草も かれぬと思へば」
「草」の縁語=かれ、もゆ
●46番=「由良の門を わたる舟人 かぢをたえ 行く方を知らぬ 恋の道かな」
「道」の縁語=わたる・ゆくへ・まどふ・ふむ
●51番「かくとだに えやは伊吹の さしも草 さしも知らじな 燃ゆる思ひを」
「さしも草」の縁語=もゆる、火
●55番「滝の音は 絶えて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞えけれ」
「滝」の縁語=音・流れ・聞こゆ
●60番「大江(おほえ)山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天(あま)の橋立」
「橋」の縁語=踏み
●72番「音に聞く 高師(たかし)の浜の あだ波は かけじや袖(そで)の 濡(ぬ)れもこそすれ 」
「浜」の縁語=波・ぬれ
●80番「長からむ 心も知らず 黒髪の 乱れて今朝は ものをこそ思へ」
「髪」の縁語=長・乱れ
●88番「難波江(なにはえ)の 芦(あし)のかりねの 一よゆゑ みをつくしてや 恋ひわたるべき」
「芦(あし)」の縁語=よ、ふし、ね
「難波江」の縁語=かりね・ひとよ・みをつくし・わたる
●89番「玉の緒よ 絶なば絶えね ながらへば 忍ぶることの よわりもぞする」
「緒」の縁語=絶ゆ・ながらふ・弱る
●97番「来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩(もしほ)の 身もこがれつつ」
「藻塩」の縁語=焼く・こがる |
|
体言止
たいげんどめ |
句の終わりを体言(名詞)で止め、すべてを言い切らないことで、深い余情を残す技法です。
「新古今集」に多く使われています。 |
●31番「朝ぼらけ 有明(ありあけ)の月と 見るまでに 吉野の里に 降れる白雪 」
●60番「大江(おほえ)山 いく野の道の 遠ければ まだふみもみず 天(あま)の橋立」
●64番「朝ぼらけ 宇治の川霧(かわぎり) たえだえに あらはれわたる 瀬々(せぜ)の網代(あじろ)木 」
●70番「さびしさに 宿を立ちいでて ながむれば いづこも同じ 秋の夕ぐれ」
●76番「わたの原 漕(こ)ぎいでて見れば 久かたの 雲ゐにまがふ 沖(おき)つ白波」
●78番「淡路島 かよふ千鳥の 鳴く声に いく夜ねざめぬ 須磨(すま)の関守(せきもり)」
●79番「秋風に たなびく雲の たえ間より もれ出づる月の 影のさやけさ 」
●87番「村雨(むらさめ)の 露(つゆ)もまだひぬ まきの葉に 霧(きり)立ちのぼる 秋の夕ぐれ」
●95番「おほけなく うき世の民に おほふかな わが立つ杣(そま)に すみ染(ぞ)めの袖(そで)」 |
|
倒置法
とうちほう |
言葉の順序を入れ替えて、意味を強調する技法をいいます。 |
●28番「山里は 冬ぞさびしさ まさりける // 人めも草も かれぬと思へば 」
下の句が上の句の理由を説明するかたちになっています。
|
|
本歌取
ほんかどり |
本歌取りというのは、昔の有名な歌の一部を引用したりさまざまにアレンジして新しい歌を作る技法です。和歌の古典だけでなく、漢詩の一部を借りることもありました。本歌を知っている人には、もとの歌のイメージが、新しく作られた歌に二重写しのように伝わり、歌に広がりが出たり、余情を豊かにします。
百人一首の撰者、97番・藤原定家の時代に流行しました。定家は「詠歌大概(えいがのたいがい)」という歌論書の中で、本歌取りの注意を記しています。
①三代集(「古今集」「後撰集」「拾遺集」)にある名人の歌を本歌とする。
②本歌の言葉を用いる時は二句までにする。
③場面の設定を本歌と変える。例えば「四季の歌」から「恋の歌」に変える、「冬の歌」から「秋の歌」に変えるなどです。
また、源実朝(みなもとのさねとも)のために記した「近代秀歌」の本歌取りの条でも、「最近に詠んだ歌については、ほんの一句でも、これは現代歌人のあの人が詠んだあの歌の語句だとわかるようなことは、必ず避けたい」と書いています。 |
●28番「山里は 冬ぞさびしさ まさりける 人めも草も かれぬと思へば 」→
本歌「秋くれば 虫とともにぞ なかれぬる 人も草葉も かれぬと思へば」(藤原興風)
本歌「山里は 秋こそことに わびしけれ 鹿の鳴くねに 目をさましつつ」(壬生忠岑)
●69番「あらし吹く 三室(みむろ)の山の もみぢ葉は 竜田(たつた)の川の にしきなりけり 」→
本歌「竜田川 もみぢ葉流る 神なびの 三室の山に 時雨ふるらし」(よみ人知らず)
●90番「見せばやな 雄島のあまの 袖(そで)だにも 濡(ぬ)れにぞ濡れし 色は変はらず」→
本歌「松島や 雄島の磯にあさりせし あまの袖こそ かくは濡れしか」(源重之)
●92番「わが袖(そで)は 潮干(しほひ)にみえぬ 沖(おき)の石の 人こそ知らね 乾く間もなし」→
本歌「わが袖は 水の下なる石なれや 人に知られで かわく間もなし」(和泉式部)
●93番「世の中は 常にもがもな 渚(なぎさ)こぐ あまの小舟(をぶね)の 綱手かなしも」 →
本歌「川上(かはのへ)の ゆつ岩群(いはむら)に 草生(む)さず 常にもがもな 常乙女(とこをとめ)にて」(「万葉集」)
本歌「陸奥(みちのく)は いづくはあれど 塩釜(しほがま)の 浦こぐ舟の 綱手(つなで)かなしも」(「古今集」)
●94番「み吉野の 山の秋風 小夜(さよ)ふけて ふるさと寒く 衣うつなり」→
本歌「み吉野の 山の白雪 つもるらし ふるさと寒く なりまさるなり」(坂上是則)
●97番「来ぬ人を まつほの浦の 夕なぎに 焼くや藻塩(もしほ)の 身もこがれつつ」→
本歌「万葉集」の笠金村(かさのかなむら)の長歌
●98番「風そよぐ ならの小川の 夕暮(ゆふぐれ)は みそぎぞ夏の しるしなりける」→
本歌「みそぎする ならの小川の 川風に 祈りぞわたる 下に絶えじと」(「古今六帖」)
本歌「夏山の 楢の葉そよぐ 夕暮は 今年も秋の 心地こそすれ」(「後拾遺集」) |
和歌で
注意する語句 |
|
①かな=「~だなあ、~ものだなあ。」感動・詠嘆を表す。
②けり=「~た、~そうだ」事実を過去のこととして回想する。
「~だなあ。~したことよ。」今まで意識しなかったことに初めて気づいたおどろきや感動を表す。
③かも=「~だなあ、~のことよ。」感動や詠嘆の意味を表す。
④もがな=~したいなあ、~であったらなあ、~てくれたらなあ。かなわないことや困難なことに対する願い、疑問、詠嘆を表す。
⑤らむ=「今頃は~ているのだろう。」目の前にない事実の現在の状況の推量。
「~なので~なのだろう。」目の前の現在の事実にもとづいた推量。
⑥つつ=「~ては」動作の反復を示す。
「~し続けて」動作・状態の継続を示す。
「~ながら」同時進行していることを示す |